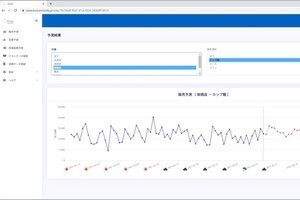日常的に利用するであろうAmazonや楽天をはじめたEC。消費者の生活の利便性が向上したものの、日本の小売業界が抱える課題は少なくない。そんな中、課題解決に向けてコニカミノルタではAIデータ予測プラットフォーム「AIsee(アイシー)」を提供している。このたび担当者に取材の機会を得たので、レポートする。
カジュアルに利用してもらうサービス「AIsee」
昨今、小売業界では特徴的な品揃えの強化やリアル店舗ならではの購買体験、デジタルも含めたアクセス性の向上、会員プログラムの見直しをはじめ、クリエイティブ業務の比重が大きくなっており、コロナ禍に加えてECビジネスの台頭による課題を抱えている。
一方で、現場のベテラン社員は定常業務に追われ、時間が割けていない状態になっているという。こうした状況の中、同社では先行してデータ統合プラットフォームの「カスタマージャーニーDMP」の提供を開始し、その後発サービスとして昨年8月にAIseeの提供を開始した。
コニカミノルタ ジャパン マーケティングサービス事業部 プラットフォームビジネス推進統括部 営業推進部 部長の荒井勇輝氏は「カスタマージャーニーDMPは、オンライン上のユーザー行動接点やポイントカードをはじめとしたオフラインの行動接点を1つのログとして扱うことができ、どちらかというとSI色が強いです。一方、AIseeはカジュアルに利用してもらうサービスです。特に小売業はコロナ禍の影響を大きく受けて、業態の変化が求められており、一部ベテラン社員の方にしかできなかった“先読み”の業務を標準化することが解決策になると考えました」と、製品の位置づけについて説明する。
1カ月の無償トライアルも用意
AIseeはAIのスキルは不要ですぐに利用できるほか、データ入力が手軽・柔軟であり、低コストでの利用が可能だという。具体的には、初期構築作業を不要としており、4クリックで予測の実行が完了し、6カ月先まで予測可能な予測結果はダッシュボード形式で表示することで、見やすくしている。
また、需要予測対象の過去データから特徴・傾向・周期と、説明変数(曜日祝日、天候、六曜)との関係性をAIseeが学習し、Excel処理では把握できない細かな特徴を学び、データをもとに説明変数を付加して需要を予測。
対象となるデータはPOSデータや売上実績データ、販促データ、来場客数などの実績データ、予測に必要な外部要因データ(曜日祝日、天候など)は事前に実装済みだ。1カ月の無償トライアルを利用できる。最低3カ月分の連続データが必要になり、予測は可能ではあるものの季節変動をふまえていないため、1年以上のデータを準備してもらうことを推奨している。
現状の予測モデルは、発注業務など在庫の変動をアイテム別に予測する「在庫予測モデル」、販促業務、報告業務といったアイテム・カテゴリ・店舗・地域単位で受注・売上を予測する「販売在庫モデル」、シフト業務をはじめとした店舗・地域単位で来場者・スタッフ人数を予測する「来場者予測モデル」の3つ。今後もユーザーの要望に対応しつつ、予測モデルを拡充していく方針だ。
初期費用は無料、月額費用は5万円(5ユーザーアカウント)、オプションとしてIP制限とMFA(多要素認証)のセキュリティオプションに加え、テクニカルサポートが8万円/8時間、同社のデータサイエンティストによるデータ活用サポートが12万5000円/同など導入後の支援メニューも用意し、SaaS(Software as a Service)で提供している。
幅広い中堅・中小企業のデータハブに
AIseeについて、荒井氏は「データ量が多ければ多いほど、パターンマッチングをかけられることから、精度は向上します。基本的には時系列分析がメインですが、日別のデータを取得しているのであれば小売業だけでなく、出社率の予測など幅広い業種で利用できます。容易な操作性とコスト面が他社製品と比較したメリットですね」と、説明した。
ユースケースとして食品・飲料など製造業における量販店への提案付帯用販売予測、生産・部材調達最適化に向けた予測、人材派遣サービスでは派遣社員の応募・確定件数の予測、会員制サービスは新規会員数・解約者数の予測、コールセンターにおけるクレームなどの入電件数の予測などを挙げている。
提供開始から1年が経過するが、現在では導入とトライアルを含めて中堅・中小企業90社以上から引き合いがあるという。
荒井氏は「当面は複合機ビジネスの販売チャネルを含めて、サービスの販売・利用を幅広い業種にわたり拡大していくことが目標です。ユースケースをはじめとしたノウハウを蓄積して一定のユーザー基盤を構築し、事業を安定させていくことを目指します。最近では他社も含めて多くの需要予測サービスがあります。また、市場規模も年々拡大していくことが見込まれているため、シェアを獲得していきます」と今後について意気込みを述べた。
また、同氏は「サービス基盤の安定後には、大手コンビニエンスストアのようなデータ網を幅広い業種の中堅・中小企業でも利用できるようなデータハブに当社がなれればと考えています。例えば、おすすめ商品を扱うと売上拡大するなど、類似した近隣店舗のデータを活用するなど、個人商店や小さな店舗に対してでも大企業と遜色ないようなデータ基盤を提供したいですね」とも語っていた。