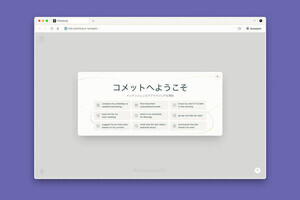「Web3」――最近よく耳にする言葉だが、どういう意味なのかはいまいち理解できていない……。Web3を検索エンジンで調べてみようと試みても、「ブロックチェーン」や「NFT」、「メタバース」といった、またしても文字面でしか理解できていない言葉が次々と出てくる。
初心者に優しそうな人気シリーズの解説本に手を伸ばしてみたが、とあるECサイトで「デタラメなことを堂々と書いてある」「疑心暗鬼になる」といった散々な口コミを見てしまったため、そっと元の場所に戻した。
この単語に関する理解を深めて、「Web3ってなんなん?」と疑問を持つ人から嘆声を引き出したい。そんな筆者が抱える思いに共感する方も少なくないだろう。
実業家の前澤友作氏は5月にWeb3やメタバース領域の企業やプロジェクトを対象に投資を行う「MZ Web3ファンド」を設立した。投資総額は約100億円に上る。また、DMM.comは7月にWeb3事業への参入を発表、関連事業を展開する新会社を8月頃に設立する予定だ。
さまざまな人や企業、自治体が注目するWeb3。いったいどのような概念なのだろうか。知識ゼロの状態で、Web3事業などを展開するMintoの代表取締役社長である水野和寛氏に直撃した。
--いきなりすみません……。Web3って何ですか。
水野氏:Web3.0と表記されることもあるWeb3は、2014年にイーサリアムの共同設立者であるギャビン・ウッドが2014年にとりまとめた構想がベースになっています。「Web3とはこういうことだ」と一言で表現することは難しいですが、Web“3"というくらいですから、もちろんWeb1(1.0)とWeb2(2.0)も存在します。
人によって表現の仕方はさまざまですが、私はWeb1のことを「1995年~2005年までのホームページが主流だった時期」と表現しています。インターネットが1995年から普及し始めて個人や会社がホームページで盛り上がりました。片方向で情報を発信するツールとしてインターネットを活用していた時代がWeb1です。情報の発信者と受け取り手がはっきりと分かれていました。
次のWeb2は、TwitterやYouTube、Facebook、InstagramなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)が存在感を強めていった2005年~2018年の時代を指します。一方通行の情報発信しかできなかったWeb1と違い、双方向でコミュニケーションすることができるようになったのです。
Web1の時代では、例えばTwitterのように「自分が情報発信してそこに100万人集まる」といったことはあり得ませんでした。SNSを起点にして、個人間で、フォローしたりフォローされたりするような関係を築けるようになりました。これがWeb2の最大の特徴です。
一方で、Web2の時代の双方向性はGAFAM(Google、Amazon、Meta:旧Facebook、Apple、Microsoft)などのネット企業が中間に入ってユーザーデータなどを管理して、成立させる必要がありました。
そして、昨今盛り上がっているWeb3。これは簡単に言ってしまうと、ブロックチェーン技術を活用した分散型のウェブサービスの総称のことを指します。最近、耳にする機会が増えている「暗号資産」や「分散金融」などがこれにあたりますね。
Web2の時代は、GAFAMのようなネット企業が大きな役割を果たしていましたが、ブロックチェーン技術でこのような役割を代替しようという動きになっています。
切っても切れないブロックチェーンとの関係
--やっぱり出てきましたね、ブロックチェーン……。詳しく教えてください。
水野氏:Web3を理解する上で、まずはブロックチェーンの理解が必要不可欠です。ブロックチェーンとは、一言で表すと「インターネット経済圏を完成させる技術」と言えます。
もう少し具体的に言うと、ブロックチェーンは、全体を管理するサーバが存在せず、多くのコンピューターが相互に接続して、取引履歴をやり取りしながら暗号化・分散処理し、1つのサーバが存在するかのように管理する技術となります。
ブロックチェーンは、インターネット上の取引履歴を暗号化しブロック単位で格納していきます。例えば、暗号資産のイーサリアムであれば12秒経過するごとに、取引履歴を格納していきます。ブロックとブロックをチェーンでつなぐので、この技術はブロックチェーン(分散型台帳)と呼ばれているのです。
そして、ブロックチェーンの最大の特徴は、データの信頼性を担保している点です。ブロックチェーン上のデータを改ざんするには、つながっている過去のデータをすべて改ざんする必要があり、簡単には改善できない仕組みになっています。今のところ、世界中でブロックチェーンの暗号を解読して改ざんできた人は誰ひとりとしていません。
ブロックチェーンの代表的な2つの承認方法
--ブロックチェーン上のデータは時間が経てば経つほど、より複雑になるということですね。では、どのようにしてデータを分散処理、分散管理しているのですか?
水野氏:取引や送金が発生したとき、そのデータはノード(承認者)によって承認されて初めてブロックチェーンにつながります。代表的な承認方法は2パターンあります。
1つはPoW(Proof of Work:プルーフ・オブ・ワークス)と呼ばれる方法。世界中のマイナーと呼ばれる承認者がサーバを使って計算し、他のマイナーに計算結果が正しいと判断してもらって、計算競争に勝ち抜いたマイナーがデータ承認を行い、報酬として暗号資産を得る仕組みです。暗号資産を代表するビットコインやイーサリアムなどがこの方法で管理されています。
もう1つの方法がPoS(Proof of Stake:プルーフ・オブ・ステーク)です。この方法は、ステーキング(保有)する暗号資産の量に応じて、ブロックを新たに承認する権利が得られる仕組みをとっています。つまり、暗号資産をたくさん持っている人が、たくさん承認できるようになります。大量の電力消費を伴うPoWに比べ、環境への影響が少ないと言われていて、イーサリアムは2022年後半にPoSへ移行する予定です。
ブロックチェーンの仕組みは、銀行などの金融機関に置き換えて考えてみると分かりやすいです。お金を降ろすときに使うATMの手数料は銀行に払っていますよね。でも、この暗号資産の手数料は、データを承認したマシンを持っている人の懐に入ります。一般的に、ブロックチェーンに取引履歴を記録する際の手数料のこと「ガス代」と呼びます。膨大な量の計算の見返りとしてガス代が支払われているのです。
この仕組みがあるからこそ、銀行という中央集権的な存在がいなくても、資産の取引が成立するのです。自動的にプログラムとしてエコシステムを円滑に回せるこの技術は、とても美しく次世代で必要不可欠な存在だと思います。
ブロックチェーンの種類
--承認者が世界中に分散しているのですね。ブロックチェーンに種類はあるのですか?
水野氏:「パブリックチェーン」と「プライベートチェーン」の2種類があります。
パブリックチェーンに代表されるブロックチェーンは、ビットコインとイーサリアムが挙げられます。ビットコインは通貨に特化したブロックチェーンで、イーサリアムは通貨以外の機能を持っているブロックチェーンです。
これらのブロックチェーンは世界中のノードで分散処理しています。そのため、大量の電力消費を伴っており、ガス代が1回数千円かかっている点が特徴です。100円のものを取引するときも数千円かかってしまいます。さらにトランザクション量も多いため、取引承認に時間がかかってうのがパブリックチェーンの難点です。
一方のプライベートチェーンは、ノードの数を少なくして固定しているブロックチェーンです。パブリックチェーンはノードが万単位ありましたが、プライベートチェーンではノードの数を10~20、場合によっては4~5にまで抑えています。その分、ガス代が安くなり、承認に要する時間もかかりません。LINEや楽天のブロックチェーンはこれにあたります。本来のメリットを少なくする代わりに、ガス代と承認時間を節約しているということですね。