一都三県でグルメ回転寿司チェーン「すし銚子丸」などを運営する銚子丸。“海の香り”をコンセプトに、産地直送のネタにこだわった寿司をはじめ、劇場型の店舗づくりでも知られている。そんな同社は2021年10月、改めて接客サービスを見直すべく、「おもてなし部」を創設。スタッフ教育の強化を目的に動画型マネジメントシステムを導入し、サービス向上の取り組みを進めているという。
接客サービスの指導は主に口頭で行われることも多い中、動画の活用に留まらず、システムの導入にまで踏み切ったのはなぜか。想定した効果は得られたのか。おもてなし部 副部長の三浦正嗣氏に話を伺った。
“味は美味しいけれど……”、顧客サーベイから見えた課題
すし銚子丸では、一店舗当たり3~7名の寿司職人を配置。日本各地の漁港から仕入れた鮮魚を用い、高い調理技術を持った寿司職人が握る寿司は、多くの顧客の心を掴んできた。三浦氏によると、自社で行う顧客サーベイ(アンケート)でも「鮪が美味しい」などといった味・質・量に対する評価は高スコアを維持し続けているという。しかし一方で、「『味は美味しいけれど、接客面が……』という厳しいお声をいただくこともありました」と、三浦氏は振り返る。
飲食店には繁忙時間帯があり、特に週末の食事時は大勢の来店者で賑わう。多い時には、寿司職人1人あたり約20名~30名のお客さまの対応をすることもあり、所作や立ち振る舞い、丁寧さに少し欠けてしまうこともあった。また、コロナ禍による、回転寿司店ならではの変化も、接客サービスが課題視されるようになった理由の一つだ。従来、回転寿司店では店内に設置されたレーンに寿司が乗って回っており、来店者は自ら気に入った一皿を取る。しかし、非接触が推奨されるコロナ禍では、寿司をレーンに流すことが難しくなり、銚子丸も全店タッチパネルの導入に踏み切った。これにより注文数が1.5倍以上になったことから、提供時間の遅れが発生したり、オーダー伝票が滞ってしまったりといった課題が発生したのだという。
この状況を打開すべく2021年10月に設立されたのが、「おもてなし部」である。改めて銚子丸の接客サービスを見直すため、同部がまず取り組んだのが、おもてなしを中心とした動画マニュアルの再整備と階層別の業務ランクを設けた教育システムの導入だった。
動画マニュアルの在り方を見直し、効果的な教育を実現
同社では4年前より、スタッフ教育にe-ラーニングを取り入れていた。握り寿司をきれいに手際良く握る人、鮮魚を丁寧に早く正確に捌ける人、笑顔が素敵な人といった社内でお手本となるようなスタッフを動画で撮影し、社内プラットフォームにアップしていたという。しかし「スタッフに『動画を視聴してください』とお伝えはしていましたが、実際に一人一人が何をどこまで視聴しているかまでは把握することはできていなかった」(三浦氏)のが実態だった。そこで改めて、動画マニュアルの在り方を検討。ClipLine社が提供する動画型マネジメントシステム「ClipLine」を導入することに決めた。決め手になったのは、飲食店に特化したサービスであったことや、個人ごとの視聴履歴が見られること、動画を介して双方向のコミュニケーションができることだったという。
「スタッフはClipLineにアップされたお手本動画を繰り返し視聴した後、店舗で実践を続けながら『これならお手本動画と同じレベルに達した』と自信を持てたら動画を撮影し、ClipLineに投稿します。投稿直後に上長である店長やマネージャーのPCなどへ動画が届きます。上長は送られてきた動画をお手本と見比べて遜色がないかを確認をし、フィードバックを行います。ClipLine上で行うので遠隔地においても容易に確認することができます。また、フィードバックはより具体的な内容で(手順と動作と時間)返すようにして、できたら褒めるという仕組みで運用されています」(三浦氏)
銚子丸では、スタッフ3,300名にアカウントを発行するとともに、階層別の業務スキルに応じてランク付けを行う教育システムを構築した。もともと「さぁ、おいしい舞台へ」をコンセプトに掲げるすし銚子丸では、顧客を観客に見立て、店舗を「劇場」、スタッフを「劇団員」と呼んでいる。“観客(顧客)に楽しんでほしい”という想いから、ランク名には以下のように落語の階級名を採用した。
ClipLineを浸透させるためにもまず、真打を目指すことになったのは、店長経験のあるエリアマネージャーたちだ。マネージャーへのフィードバックは三浦氏を含むおもてなし部が担当しエリアマネージャーが率先垂範の姿勢を見せることで店舗への浸透を図った。実際に動画を視聴・投稿したマネージャーからは、「改めてお手本動画と自分自身を比較して見ることで間違えて認識していたものもあり、学び直しに繋がった」といった感想も上がってきた。早い人で約3カ月程度で真打に昇格し、現在はマネージャーと店長の約70名が真打になっている。その後、このシステムは店長、社員、パートやアルバイトまで、対象の範囲を広げていく予定だ。2021年10月にClipLineを導入した当初は、370本の動画マニュアルをリリースしたが、現在は、420本ほどに増えている。これは、スタッフの間でポジティブな連鎖が生まれたからだと三浦氏は語る。
「例えば、衛生管理課が手洗いの動画をアップすると、それを視聴したスタッフの中から、お手本をも超えるような、より正確な手順で誰もが感心する衛生的な手洗いをする人が出てくるのです。すると、次はその人の動画が、新たなお手本になります。お手本となり得る人はパートやアルバイトの方も含め、全て店舗で働いているスタッフたちです。だからこそ、視聴しよう、私もやってみようというモチベーションになったのではないでしょうか」(三浦氏)















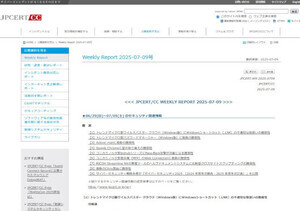





![旭化成ファーマが全従業員に対し、Uniposを導入[事例]](/techplus/article/20220311-2288719/index_images/index.jpg/iapp)
![NEC、サントリービールにAIを活用した設備の異常予兆検知システムを提供 [事例]](/techplus/article/20220228-2279800/index_images/index.jpg/iapp)

