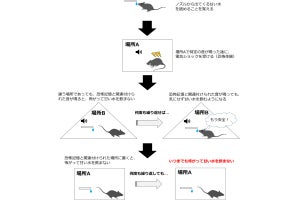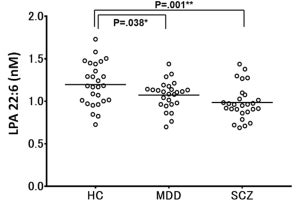東京慈恵会医科大学(慈恵医大)は7月11日、2種類の「セロトニン受容体」がそれぞれ異なった様式で、アルツハイマー型認知症(AD)と密接に関係する「前脳基底核」内の興奮性シナプス伝達を調節していることを明らかにしたと発表した。
同成果は、慈恵医大 薬理学講座の西條琢真博士研究員(現・愛知県医療療育総合センター 発達障害研究所 分子病態研究部門)、同・鈴木江津子講師、同・籾山俊彦教授らの研究チームによるもの。詳細は、「Journal of Physiology」に掲載された。
ADは日本国内における認知症患者の7割弱を占め、厚生労働省が発表した資料などによれば、将来的にはさらに増加することが予想されている。ADの特徴の1つとして、認知機能、記憶や睡眠サイクルなどに関連する重要な神経伝達物質「アセチルコリン」が減少することが知られており、現在では、認知症の進行を遅らせる治療薬として、脳内のアセチルコリン濃度を上昇させるものが主に利用されているという。
脳内に広くアセチルコリンを放出する神経細胞「コリン作動性ニューロン」(CN)が多く存在しているのが、前頭葉底部の後方に位置する前脳基底核だが、CNはAD患者では減少していることが報告されているほか、この前脳基底核を損傷すると記憶障害の「健忘」が生じることも知られている。また、前脳基底核内には、別の脳領域の背側縫線核から、うつ病や不安障害といった精神疾患と関連する神経伝達物質「セロトニン」が放出されていることも知られており、ADとうつ病は併発することもあり、セロトニンがどのように前脳基底核CNの活動に影響するのかを明らかにすることが、2つの疾患のクロスポイントを知る上で重要視されてきたという。
これまで、研究チームでは、数種類あるセロトニン受容体(サブタイプ)のうち、「セロトニン5-HT1B受容体」の作用により前脳基底核CNへの抑制性神経伝達が抑制されることを報告しており、シナプス前部からの神経伝達物質放出が抑制されることによるものまでは分かっていたが、興奮性シナプス伝達に対するセロトニンの調節作用は未解明のままだったという。