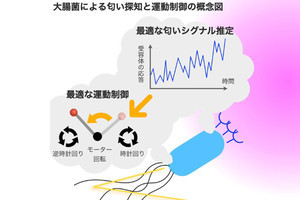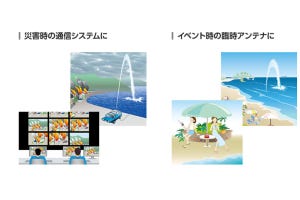世界の平均気温が将来何度上昇するのか、そんな予測にさまざまな気候モデルが使われてきた。
しかし、気象モデルの間でばらつきがあるという課題があった。このばらつき、つまり不確実性を低減しようと国内外ではさまざまな研究が行われきたのだが、そのうちの世界の平均降水量変化予測の不確実性については、これまで誰も低減することが出来なかったという。
そんな中、国立環境研究所、東京大学らの研究チームから2022年2月24日、21世紀後半までの降水量変化予測の不確実性を低減することに初めて成功した、そんなプレスリリースが発表された。
今回は、国立環境研究所、東京大学らの研究チームが成し遂げたすごい研究成果について、国立環境研究所の塩竈秀夫 博士から伺うことができたお話も含めて紹介したいと思う。
この研究の成果について
これまで降水量変化予測の不確実性低減が難しかった最大の原因は、過去の降水量トレンドに温室効果ガス濃度増加だけでなくエアロゾル(大気汚染物質)排出量増加の影響が多く含まれており、温室効果ガス濃度増加による将来の降水量変化と過去の変化の要因が異なるため、過去の変化から将来予測の不確実性を低減するための情報を得ることが困難だったのだという。
今回発表された研究では、世界平均エアロゾル排出量が増減しない1980年~2014年のモデルに着目し、この期間の気温変化と降水量変化を観測データと比較。将来予測の信頼性を評価することで、初めて世界平均降水量変化予測の不確実性を低減することに成功したというものだ。
降水量増加の予測幅の上限の6.2%を5.2%~5.7%へ引き下げることができ、また予測の分散も8%~30%減らすことができたという。
この研究成果は、これまで不確実性が低減できなかった重要な気候変数(降水量)に関してブレークスルーをもたらすと期待されている。
今後さらに証拠を積み上げていくことで、気温だけでなく、ほかの変数に関しても不確実性幅を低減できる可能性があり、また、気候変動対策の政策決定者などに対して、より正確な情報を提供できるのだ。
なお、同研究成果は、2022年2月24日付で学術誌「Nature」に掲載された。
この研究成果で未来はどうなる?
今回の研究成果は、気候変動に関する政策決定、意思決定に使われる重要なものだ。一方で、1つ目線を下げて未来のわたしたちの身近な生活がどのように変わるのだろうか。
国立環境研究所の塩竈秀夫 博士からこんなお話を伺うことができた。
現在、気候変動に関する対策は、政治の世界だけでなく、民間企業においても重要な課題となり、あらゆる場面で気候変動対策とのシナジーを考えることが当たり前になりつつあるという。
ここでいう対策は、気候変動が進むことを抑えるための温室効果ガス排出量削減策(緩和策)だけでなく、排出削減をしても現れてしまう悪影響を低減するための適応策(例えば稲の高温耐性品種の開発や護岸整備など)も含まれる。このような対策を考える際に、基礎となるのが気候モデルによる予測データであり、その不確実性が低減できれば、対策の精度を上げられるようになり、コストの削減やサービスの向上につながる。そうなれば、一般の方々も納税者、株主、消費者、住民などとしてさまざまな場面でメリットを受けられることになるというのだ。
また、最終的に目指されている研究の目標・成果を伺うと、塩竈博士は「気候変動予測は完璧ではなく、気候変動の対策は不確実性の中で意思決定を行っていく必要がある。気候変動がどんどん進行する中で、予測の精度を出来るだけ上げていくことが意思決定のサポートのために重要で、それがひいては自分自身と子供や孫の世代の未来を守ることにつながるのだと考えて、研究を進めていく」とお話いただけた。
いかがだっただろうか。塩竈博士にお話を伺う前までは、このような上位概念の気象研究は、国際レベル、国レベルの大きな政策決定のみに役立つものと考えていた。
しかし、この研究成果は、民間企業レベル、強いてはわたしたちの国民の身近なレベルまでつながっていくことを知ることができたとても貴重な機会だった。