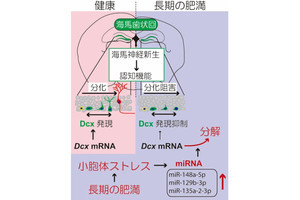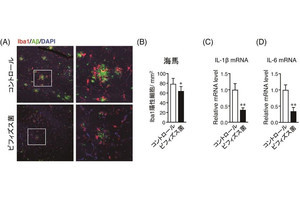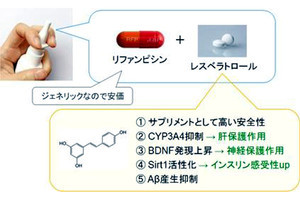エムは2月18日、都内で記者説明会を開き、未病段階の認知症リスクを評価する脳健康測定プログラム「MVision brain(エムビジョンブレイン」を開発したと明らかにした。なお、同プログラムは、2022年4月から東京ミッドタウンクリニック特別診察室で提供開始(テストラン)を予定しているほか、スマートスキャンが手がけるスマート脳ドックでの提供(同)についても同社と協議を進めている。
3万枚のMRI脳画像ビッグデータをAIで分析した脳健康評価プログラム
MVision brainは、米ジョンズホプキンス大学がAI技術を活用し、開発したソフトウェアをベースに日本国内に存在する3万枚のMRI脳画像ビッグデータをAIにより分析することで、認知症や脳梗塞患者に広く認められる特徴である脳の萎縮と血管性変化を総合的に評価する脳健康測定プログラム。
エム 創業者/技術顧問の森進氏はジョンズホプキンス大学 医学部放射線科の教授。MVision brainの開発者でもあり、同プログラムは機械学習を活用している。同社は2021年に創業し、医療画像のAI分析によるデータ解析・検診、医療向けソフトウェア開発を手がけている。
同氏は「MVision brainは、脳室拡張や脳各部位の大脳皮質の体積を数値化し、同年代の受診者と比較することで脳の萎縮度合いの経年推移を評価していく『脳の包括的萎縮評価』と、白質病変領域の体積を数値化して同年代の受診者と比較し、脳の血管性病変において経年推移の評価を行う『血管性病変評価』により、脳の健康状態評価、行動改善アドバイスなどのレポートを出力する。病変のAI解析により、脳健康リスクの測定を可能にする脳ドック、健診センター用のプログラムだ」と説く。
高齢者の5分の1が認知症に罹患し、巨額な社会的コストも発生
認知症と脳血管性疾患は健康寿命を奪う要因となっており、中でも認知症の発症者数は年々増え続け、2025年には65歳以上人口の約5分の1が認知症になると予測されている。
認知症をはじめとする脳疾患の多くは、発症の10年以上も前から徐々に進行し、元に戻ることは難しい生活習慣病となっており、早期にその予兆を検出し、生活習慣を正すことが重要だという。また、認知症患者を介護するための費用や治療のための医療費は、2014年時点で約14兆6000億円に達しており、こうした社会的費用は今後も増加することが見込まれている。
これに対し、政府も2004年に「認知症を知り地域をつくる10カ年の構想」、2019年には「認知症施策推進大綱」を発表し、共生と予防を両輪とした施策を推進しているが、予防のうち認知機能の低下のないプレクリニカル期において発症を遅らせる取り組み(一次予防)においては、有効な対応策が未確立だった。
エム 代表取締役CEOの関野勝弘氏は「厚生労働省の資料によると、介護に至るまでの要因として半数が認知症と脳卒中が占めており、最近では認知症は生活習慣病の1つであることが分かりはじめている。従来、脳の健康維持手法は初期症状が出てからの対処がメインであり、未病段階の早期対策システムは今後確立が必要なフロンティア領域だ。国内では40~74歳の方が5800万人いることから、こうした方たちにどうのように利用してもらえるかを考えていきたい」と力を込める。
従来、脳の健康を知る有効な方法である脳ドックは脳腫瘍や脳動脈瘤といった、稀ではあるものの早急な対処を必要とする重篤な疾患の検出を主な目的としていた。MVision brainはこれに加え、未病段階での行動改善による認知症などの脳疾患につながるリスク低減を目的に開発され、受診者に対して早期の段階から脳の健康を管理する機会を提供する。
脳ドックなどの頭部MRI検診に追加することで、認知症をはじめとする脳疾患 に繋がるリスクを早期から評価し、受診者がとるべき脳の健康維持・改善方法を提示する。
認知症の予知につなげる
MVision brainの特徴として「脳の多角的な対象構造・指標の選定」「統計的に有意なサンプル数からの健康度評価」「低い機種依存度・短い測定時間」の3点を挙げている。
脳の多角的な対象構造・指標の選定については、脳内505構造の同定および体積測定を可能とし、かつ幅広いMRIスキャン条件に対応。その中で、脳全体の健康状態をモニタリングすることができる構造物として脳室という構造を用いた脳萎縮の測定と白質変化と言われる脳血管の劣化状況の測定を行っている。
健康度評価に関しては、国内でこれまで目を向けられてこなかった脳ドックMRIの脳画像ビッグデータを約3年かけて分析し、それをもとに各年齢における日本人の正常値や異常値の検出を可能とした。大規模データをベースに多角的に脳の健康度を評価し、認知症に見られる特徴を早期から検出できる製品は業界初だという。
製品化にあたり、東京ミッドタウンクリニックとの共同研究により、健常人3万件以上の健診データをもとに解析を行い、開発に活かしている。
同プログラムのテストランを行う東京ミッドタウンクリニック院長の田口淳一氏は「東京ミッドタウンクリニックおよびグループが持つMRI画像を提供し、共同研究を行った。今後、検診において認知症をどのように予防していくのかが課題となっており、認知症になってから治療するのではなく、早い段階で予兆を検知することが必要だ。これまでは海馬にフォーカスすることがあったが、脳全体を評価することを可能としている」と説明する。
低い機種依存度・短い測定時間では、ビッグデータをもとに機種や撮影条件への依存性を解析し、幅広い撮影条件のデータをキャリブレーションにより活用できる技術を確立した。現存する脳MRI解析ソフトの多くが1ミリ程度の解像度を必要とする中、現在脳ドックで用いられている3~7.2ミリの解像度のデータも活用できるという。
MVision brainの普及により、プロダクトの進化・深化→受診機会の提供→受診者へのインセンティブ付け→受診者のフォローアップ・行動変容という、脳健康維持のためのエコシステムを確立していく。
未病段階の脳の健康状態を把握することで、認知症の予知につなげ、1人でも多くのハイリスク者の早期発見と、生活習慣・社会習慣の改善による発症の低減を目指す方針だ。