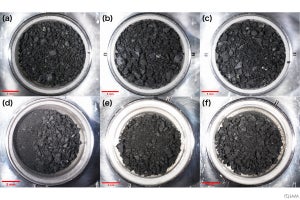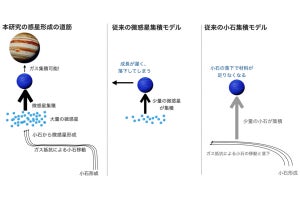宇宙航空研究開発機構(JAXA)は1月7日、小惑星帯に位置する直径114kmの小惑星「596 シーラ(シャイラ)」において、2010年12月に起きた天体衝突の前後に取得した近赤外線のスペクトルを比較したところ、色がより赤く変化したことが確認され、衝突後は、長期間にわたって宇宙空間にさらされてきた小惑星の古い表層が、衝突でクレーターから放出された地中の新鮮な物質に覆われたことを示していると発表した。
同成果は、JAXA 宇宙科学研究所(ISAS)の長谷川直主任研究開発員を中心とする、マサチューセッツ工科大学、ヨーロッパ南天天文台、ハワイ大学、ソウル大学、京都大学、チェコ・カレル大学、神戸大学、仏・マルセイユ天体物理学研究所の研究者が参加する国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天文学会が刊行する学術誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。
地球をはじめとする岩石惑星や準惑星、数多くの衛星、そのほか小天体の表面には、数え切れないほど生じた天体衝突の揺るがぬ証拠として、無数のクレーターが残されている。地球以外の天体については、月面での発光現象が目撃されるなど、いくつかの例が考えられているが、地上から観測可能なほどのサイズを持った天体の衝突する瞬間が観測されたことは現在のところないという。
火星と木星の間のメインベルトに位置する小惑星は数が多いため、実際には衝突が起きているものと考えられるが、微小な破片が衝突した程度では、地球から観測するのは難しく、ある程度のサイズの天体同士が衝突する必要がある。それが実際に確認されたのが、2010年12月に起きたシーラへの天体衝突であったという。
シーラは直径114kmほどであり、大型望遠鏡を駆使しても恒星のような点源にしか見えない。それが2010年12月に突然、彗星のようにコマや尾を持つようになったことから、塵が放出されているのが確認された。小天体によっては、それまで小惑星と思われていたものが、太陽光の当たり方が変化するなど、何らかのきっかけで突然塵を吹き出し、彗星となるようなケースもあるが、その後の観測から、シーラのコマは通常の彗星のコマとは異なる形状であり、またその彗星的な活動(塵の放出)も一過性のものであることが明らかとなった。
-

(左)石垣島天文台・むりかぶし望遠鏡で得られたシーラの画像。(右)モデル計算によって、忠実に再現された衝突現象 (Ishiguro et al. 2011 ApJ 741,L24での研究結果を改変。(C) 国立天文台) (出所:JAXA Webサイト)
そこで当時、観測で得られた物理量と、宇宙科学研究所の超高速衝突実験施設で得られた衝突現象の知見を基にして現象のモデル化を実施し、この突然の彗星的活動が起こった原因が調査されたところ、シーラに直径30~50mの天体が衝突することによって引き起こされたことが導き出されたという。
シーラはスペクトルで分類すると、衝突現象が観測される前は「T型」であったという。T型小惑星は、メインベルトや地球近傍軌道の小惑星では少数派であり、組成など不明な部分も多いが、そのスペクトルの特徴は、炭素の多いC型小惑星「リュウグウ」よりも赤いことだという。
C型小惑星よりもさらに始原的とされているほか、小惑星帯において、直径100km以上の小惑星は破滅的な破壊から免れていると一般的に考えられていることから、シーラのような小惑星は太陽系形成初期に形成された微惑星の生き残りと考えられるという。
ただし、生き残った微惑星である可能性があったとしても、太陽風などにさらされたり、微小な小惑星による衝突などの影響から始原的な状態が維持されているとは限らないということに注意が必要とされるほか、木星や土星の重力の影響を受け、形成初期の軌道から大きく移動したことなども考えられ、それにより天体の組成が異なっていく可能性も考える必要があるという。
研究チームが実施してきたのは、近赤外線の分光データを中心とした、メインベルトの直径100km以上の小惑星を対象とした分光サーベイで、小惑星帯形成時に、どのような組成の始原的な微惑星が、どのように分布していたのかを解明することを目的としたもので、近赤外線を用いるのは、観測データがこれまで取得されてこなかったためだという。今回、研究チームが過去のデータを精査したところ、シーラの近赤外分光観測が2010年の衝突現象の前後に実施されていたことが判明。そのほかの過去の文献データも含め、衝突前後のスペクトルのより詳細な調査を行ったところ、衝突前後において、可視光と3μmの波長のスペクトルでは変動していなかったが、近赤外域の0.8~2.5μmの波長スペクトルにおいて変動が検出された。具体的には、近赤外スペクトルの傾きは衝突後にさらに赤く変動し、スペクトル型としては、T型からD型に変化したという。
-

衝突前後でシーラのスペクトルの変化が示された図。横軸が波長、縦軸が波長0.55μm規格化した反射率の強度。波長が長くなるにつれ、強度が上がると、「赤く」なるといえる。逆に波長が長くなるにつれ、強度が下がると、「青く」なるといえる (Hasegawa et al. 2022より改変 (C)JAXA) (出所:JAXA Webサイト)
衝突前後でスペクトルが変化する理由はいくつか考えられ、最も可能性が高いのは、宇宙風化作用による変化だという。これは衝突前までは宇宙風化を受けた状態の表層だったが、天体衝突によって形成されたクレーターから放出された新鮮な(宇宙風化を受けてない)物質に表層が覆われることで見た目が若返り、それによってスペクトルが変化したというものである。
今回の観測により、赤いスペクトルを持つ小惑星の表層は、宇宙風化によりスペクトルが青く変化するという結果が出た。また、始原的な組成を持つと考えられる炭素質コンドライト隕石に対して行われた過去の宇宙風化模擬実験から今回の結果と同様に、宇宙風化が進むとそのスペクトルが青くなるという結果が出ていることから、これらの一致は、今回の研究の正当性を支持するものと研究チームでは説明している。
今回のシーラに起きた規模の衝突現象は、おおよそ数千年~数万年に1度という頻度で起こっているものと考えられるという。もし、今回の程度の衝突現象で、シーラの表層が定期的に一新されるのだとすると、宇宙風化の変化のタイムスケールは長くても数千年~数万年以下であることが推定されるとしている。
また、小惑星帯のほかの小惑星について考えてみると、現在観測で見えている表層は宇宙風化された表層であることは間違いなく、スペクトルが青くなっていったものと考えられるという。よって、今回の研究成果から考えると、始原的な組成を持つと考えられる炭素質コンドライトと同様なスペクトルを持つC型、T型、D型、P型(スペクトルが赤い小惑星のタイプの1つ)の各小惑星の新鮮なスペクトルは、小惑星が形成された当初はもっと赤かった可能性があるとしている。
それに対し、海王星よりも外側の太陽系外縁領域の天体は、宇宙風化の原因と考えられている太陽風の影響力も小さく、微小隕石の衝突発生頻度が小惑星帯よりもはるかに少ないと考えられることから、宇宙風化を受けていないと考えられている。実際、この領域では、T型、D型、P型のスペクトル持つ天体やさらに赤いスペクトルも持つ天体が大半を占めており、青くなっていないことから、小惑星帯に存在しているT型、D型、P型や、一部のC型小惑星は本来はもっと赤いスペクトルであり、起源は太陽系外縁領域だったことが推測されるという。
ただし、はやぶさ2の衝突実験によってリュウグウ表面に形成された人工クレーターや、同小惑星表面にもともと存在していた自然クレーターに対して行われた分光観測では、新鮮な場所のスペクトルの方が青く、古い場所は赤いという、今回の研究成果とは逆の結果が出ている。このような逆の結果が出た原因としては、「シーラとリュウグウのスペクトル型が異なるから」、「リュウグウは小惑星帯から地球近傍に移動してきたときに太陽にかなり近づいていた時期があるかもしれなくそこで加熱されたから」といった2点が考えられるとしており、反対の結果が出たといっても必ずしも矛盾しているというわけではなく、その要因を考えることによって、リュウグウの進化の歴史にさらに迫ることができるだろうとしている。
なお、JAXAの火星衛星探査計画「MMX」の探査候補天体であるフォボスは、衝突現象後のシーラと同じD型のスペクトルを持つ天体であるとされており、もう1つの衛星であるダイモスとともに、火星への巨大隕石の衝突によるもの(火星起源説)と、小惑星が捕獲されたもの(小惑星起源説)が提案されており、どちらもスペクトルはD型とされている。
今回の研究によって、宇宙風化によってスペクトルが青くなることが示されたことから、フォボスの新鮮なスペクトルはD型よりもさらに赤い可能性があり、そうだった場合は、太陽系外縁領域にある天体と類似しているということになるとする。一方、フォボスの表面には相対的に「青い」部分があり、その原因として、そこでは表面の宇宙風化した砂が除かれていつも新鮮な表面が現れているからという説もある。この前提は、D型小天体が宇宙風化により赤くなるというもので、今回の結果と異なるものであることから、研究チームでは今後、解決するべきポイントだと考えられるとしており、こうした観点も含め、フォボスの起源に決着をつけるには、MMXによるフォボスの「地表」と「地下物質」双方からのサンプルリターンが待たれるとしている。