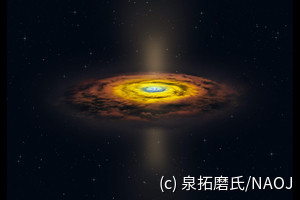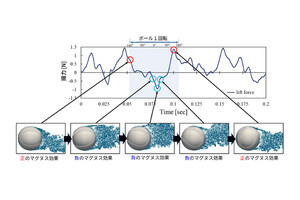東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)は3月26日、ブラックホール外側の「光子球面上」で周回する光子の相関関数が発散して無限大となり特異点を生み、物理的予言と矛盾するという従来指摘されてきた問題を、超弦理論の考え方に基づき光子を点粒子ではなく「閉じた弦」として考えることで解決できることを理論的に明らかにしたと発表した。
同成果は、Kavli IPMUの大栗博司機構長兼主任研究者、マシュー ドーデルソン特任研究員らの研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会発行の学術雑誌「Physical Review D」に掲載された。
ブラックホールといえば、光すら脱出できない強大な重力で、あらゆる物質を飲み込む暗黒の天体として知られるように、直接観測できる存在ではないため、未知の部分も多い天体である。
その強大な重力の源は、その中心に位置する「特異点」で、太陽の20倍以上の質量を思った大質量星が超新星爆発を起こした際に、中心核が重力崩壊を起こすことで誕生する(中性子星が誕生する場合もある)とされているが、その重力崩壊が限界を超えて1点に収縮して誕生するのが特異点であり、現代の知識では破綻してしまって取り扱うことが困難とされている。
ブラックホールごとに異なるが、その特異点を中心としてシュヴァルツシルト半径の距離に存在するとして理論的に導き出されているのが「事象の地平面」だ。この事象の地平面を超えて内側に入ってしまうと、光すら脱出できなくなってしまう。一般的には、この事象の地平面を“表面”として、そこから内側がブラックホールとして扱われている。
2019年4月に、イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)プロジェクトによって、おとめ座方向約5500万光年の距離にある楕円銀河「M87」の中心にある超大質量ブラックホールの直接観測画像が公開された。黒い円の「ブラックホール・シャドウ」と、その周囲の明るいリングが写っている画像を覚えいている人も多いはずだ。
光を発しないために事象の地平面を撮影することは不可能だが、この明るいリング=「光子球面」は、ほぼそれに等しいものである。光子球面は、ブラックホールに対して水平方向に入ってきた光が、その重力によって引き付けられてブラックホールの周囲を通って進むことのできる限界を表している。これより内側に入ってしまった光はブラックホールに吸い込まれてしまい、二度とその外に出てこられないとされる。
光子球面は、ブラックホールの強い重力によって時空が曲げられているために存在することが可能だ。そして重力や時空というと、アインシュタインの一般相対性理論の世界である。その一般相対性理論が扱えないのがミクロの世界であり、それを扱えるのが量子論だ。そのため、量子論にとって重力は関係ないように思われるかもしれないが、実は量子論においても重要な存在である。
量子論で素粒子を点粒子として扱う際に、ある地点の粒子がある別の地点に伝搬する確率を測る相関関数が重要だ。2つの点を真っ直ぐ結ぶ軌道を描く際には、相関関数が発散し無限大となる特異点が生み出されてしまう。(この特異点とはブラックホールの特異点のことではなく、計算が破綻してしまう点という意味)。ただし平坦な時空においては、特異点が生まれてしまうにも関わらず、この唯一独特な軌道の存在は例外的に許されている。
しかし時空が曲がっている時には、2点を結ぶ多くの軌道が存在する可能性があるので、話は異なってくる。そして曲がっている時空といえば、ブラックホールの周辺の空間であり、そうした曲がっている時空では、光によっては光子球面上を何回も周回する軌道を描く可能性があるとされてきた。
ところが、問題となるのが、光子球面上を周回した後に通り過ぎていく光の相関関数が発散し無限大となって特異点を生み出してしまうことである。これでは、物理的な予言と矛盾してしまい、この矛盾こそが素粒子論の問題としてこれまで指摘されていた。
そうした背景のもと、大栗機構長らが今回の研究で改めて着目したのが、超弦理論(超ひも理論)である。超弦理論は、クォークなどよりも遥かに小さい、真の最小単位の素粒子を、これまでのように点として考えるのではなく、長さのある弦とするという考え方が根幹にある仮説だ。なお弦には、開いているものもあれば、閉じているもの(輪)もある。
このような超弦理論の考え方に基づき、大栗機構長らが光子を点粒子ではなく閉じた弦として考えたところ、上述した矛盾点を解決できることが理論的に明らかとなった(超弦理論にもさまざまなタイプがあるが、主流の考え方としては閉じている弦は未発見の重力子とされ、光子なども含めてそれ以外の粒子は開いてる弦とされている)。
超弦理論では、すべての粒子を弦の特定の励起状態とみなして考える。粒子を点ではなく長さを持った弦とすることで、ブラックホール近くを通過する際に粒子は重力の働き方の差異で生まれる潮汐効果によって弦が引き伸ばされる。そして、引き伸ばされたことをきっかけとして、ブラックホールから遠ざかる際に今度は振動を始めると考察された。
-

ブラックホール近くを通過する際の「閉じた弦(輪)」の様子を描いたイメージ。閉じた弦は、ブラックホールに近づくにつれ段々と引き延ばされる。そして、引き延ばされた弦はブラックホールから遠ざかる際に反動で振動を始める。イメージの背景画像は、EHTプロジェクトによる、楕円銀河M87の中心にある超大質量ブラックホールの直接撮影画像。暗い部分は「ブラックホール・シャドウ」と呼ばれ、その周辺の光の輪が「光子球面」だ。(c) EHT Collaboration; Kavli IPMU(Kavli IPMU modified EHT’s original image) (出所:Kavli IPMU Webサイト)
この効果によって、物理的な期待と矛盾せず、ブラックホールの光子球面上を周回する光子の相関関数は無限大とならず、特異点は生まれないことが示されたのである。
この結果は、ブラックホール周辺の強大な重力が作用する特殊な環境下において、超弦理論で記述される弦の振る舞いを知る手がかりとなる成果の1つであり、今後の発展が期待されるという。
さらには、「量子重力理論」において素粒子の状態を記述する上で、超弦理論の考え方を含めることが欠かせないことを示す証拠となるものだともしている。量子重力理論とは、素粒子や素粒子同士の相互作用といったミクロな世界を記述する量子論と、天体の運動や時空といった重力に関係するマクロな世界を記述する一般相対性理論の2つを結びつけて、電磁気力、強い力、弱い力、重力をすべて統一する超大統一理論として期待されているものだ。
今回の研究成果に対して大栗機構長は、「我々の論文では、ブラックホールの近くで超弦理論の効果が大きく表れることを明らかにしました。この効果そのものは、EHTプロジェクトで観測できるほど大きくないですが、このような研究からブラックホールを使った超弦理論の検証への道が現れることを期待しています」とコメントしている。
最小の素粒子が弦であるということを、現代の技術では観測することはできないため、超弦理論は長らく仮説の域を出ていない。しかし今回の成果によって、将来的には検証できる可能性が出てきた。今回の成果は超弦理論にとっても大きな前進となったといえるだろう。