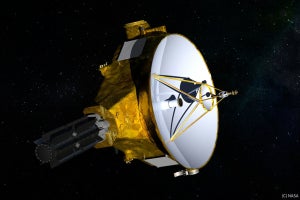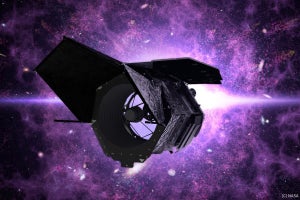学習院大学は、太陽の8倍以上の大質量星が形成される領域のひとつである「IRAS16562-3959」において、ALMA望遠鏡を用いた各星間分子の化学組成や空間分布についての詳細な観測を行った結果、酸素を含む有機分子と窒素を含む有機分子の空間分布には、大きな違いがあることを発見したと発表した。
また、各星間分子の輝線の特徴を用いて、同大質量星形成領域の構造やコア(原子星に発展する可能性のある星間物質の集中している領域)の進化段階についても明らかにし、その上で、今回の観測結果に化学反応ネットワークシミュレーションの結果を組み合わせたところ、従来の赤外線観測では発見できていなかった、ガスやダストに埋もれた生まれたての若い恒星の存在を示すことができたことも同時に発表された。
同成果は、同大学理学部物理学科の谷口琴美 助教を中心とした、国立天文台の齋藤正雄 教授、大阪府立大学/国立天文台の徳田一起 研究員、National Institute of Science Education and Research(インド)のLiton Majumdar 助教らで構成される国際共同研究グループによるもの。詳細は、米国の天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。
恒星の多くは集団で誕生し、太陽も46億年前にそのようにして誕生したと考えられている。そうした恒星が形成される領域は、同時に大質量星が誕生する領域でもあることが多いという。つまり、大質量星形成領域を研究することは、我々の太陽系がどのような環境下で生まれてきたのかを理解することにもつながってくるのだ。
また星形成領域の化学組成は、周囲の物理環境や天体の進化段階と深く関わっており、各恒星がどのような環境下でどのような進化を経て現在に至ったのかを推定するのに役立つとされる。さらに、大質量星形成領域の化学組成とその進化を追うことは、太陽系内の隕石や彗星から検出されたアミノ酸を含めた生体関連分子の生成メカニズムを解明するためにも、重要な手がかりとなるという。
しかし、大質量星は進化が速い(寿命が短い)こと、恒星が集団で誕生している領域は地球から比較的遠方にあるために観測が難しいという課題もあった。そこで今回、谷口助教らはALMA望遠鏡の電波干渉計を用いて観測を実施。大質量星形成領域「IRAS16562-3959」における分子輝線の解析を行い、化学的・物理的な環境調査を行ったという。
「IRAS16562-3959」領域の中心部では、大質量原始星「G345.5+1.47」(コアA)が発見されているが、その周辺の恒星についての情報は不足していた。そこで分子輝線のデータを用いて、同領域の化学組成と各分子の空間分布などの情報を基に、同領域内にあるコアの進化段階について調査を行ったとする。
今回の観測では、多くの有機分子が検出されたが、それらは星が生まれる前の低温・高密度の環境下にある星間ダストの表面で生成されるという。恒星が核融合反応を開始すると、その熱によって有機分子は星間ダストから昇華するようになり、その結果として、電波望遠鏡で検出され、各分子の空間分布がわかるようになる。「IRAS16562-3959」領域の場合、各分子の空間分布は分子ごとに異なっており、そうした事実から、同領域の中心に位置するコアAの近傍には、もうひとつの若い恒星(コアB)が存在し、連星系を形成していることが判明したという。さらに、この連星系より北側にコアCが位置していることも明らかとなったとする。
有機分子についての観測では、窒素を含むものがコアA~Cのすべてで検出されたのに対し、酸素を含むものはコアBとCからしか検出されなかった。これはコアAとBが化学組成的に違っており、つまり進化段階が異なっていることを意味するという。
なお、コアAで酸素を含む有機分子が検出されなかった理由は、原子星としてすでに紫外線の放出を始めており、周囲のガスを光解離・イオン化する段階にあるからだという。そこで、水素原子の電子再結合線が電離水素領域(水素イオンを主体とするガスで構成される領域)の目印となることを利用し、コアA周辺に形成された電離水素領域のサイズも調査。その大きさを確認することに成功したとする。
さらに、一酸化硫黄(SO)の同位体種「35SO」の輝線の空間分を調査したところ、35SOのピークが水素の電子再結合線の分布において外周と一致することも判明。これは、拡大する電離水素領域が周囲のガスと衝突することで生じた衝撃により、一酸化炭素が増加したことをと示しているという。
加えて、コアBとコアCの化学組成の比較も実施したところ、コアBの方がコアCに比べて有機分子の存在量が約10倍、中には約100倍も多いものもあることが確かめられたとする。これは、コアBとCも化学組成が違うということであり、コアBの方がより進化した段階にあることを示しているとのことで、コアBの方が、有機分子が星間ダストから昇華するのに十分な時間があるか、気相中でさらに生成するのに十分な時間が経っていることが考えられるとしている。
なおコアCについては、これまで明確な赤外線源が同定されていなかった。そこで今回の観測結果に化学反応ネットワークシミュレーションの結果を加える形で検討を実施。その結果、コアCにはすでに原始星が誕生している可能性があるとの結論を得たとしている。また、コアCの原子星が赤外線では発見できない理由は、まだ非常に若いため、濃いガスやダストに埋もれていることが考えられるとしている。
今回の結果から、化学組成を用いることで、従来の原始星同定の手法では見つけられないほど若い段階にある原始星も確認できることが確かめられたとのことで、谷口助教らは、コアBやCなどのように、非常に若い段階にある天体の周囲にあるガスやダストを研究することで、大質量星がどのような環境で生まれているのかの研究に繋がっていくことが期待されるとしている。
また谷口助教らは今後、ALMA望遠鏡が取得した他の大質量星形成領域における高空間分解能データを用いて、各領域の詳細な研究と、それらを統合して統計的な研究を進めていく計画だとしているほか、赤外線波長域の星間ダスト表面における氷の化学組成と、電波領域の気相における化学組成という2つのデータを組み合わせ、原始星におけるダスト表面と気相の化学的な関係について調査する計画も立てているとしており、これまでに解明されていない大質量星の形成過程について、化学的な観点から明らかにすることを目指していきたいとしている。