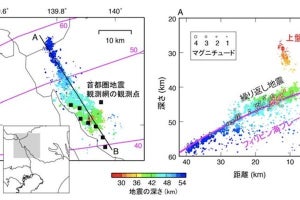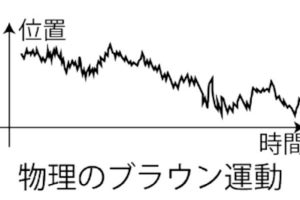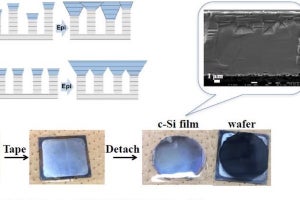東京工業大学(東工大)は、都市と周辺の道路網の構造によって都市の活性度を評価する手法を開発したことを発表した。
この成果は、東京工業大学 科学技術創成研究院のペッター・ホルメ(Petter Holme)特任教授らによるもので、12月20日、英国誌「Nature Communications」に掲載された。
この成果は、中心地理論(中心都市とその周辺地域の機能と規模を幾何学的な分布で示す地理学上の理論)で関するものである。日本でも高度成長期には各地の都市計画などに利用された。 従来は中心都市とその周辺地に関する多数の経済的、地理的データなどが必要であったが、今回の研究成果ではこれらの繁雑な準備が不要となり、新しい中心地理論として注目される。
都市中心地と周辺部の結合の強さを表現するため、幾何学的尺度Innessを定義し、出発点と目的地の最短と最速経路を評価・分析することで、都市とその周辺部の結合度を幾何学的分布で示した。さらに、同手法を世界の92の大都市とその周辺に適用し、都市の発展レベルを3種類に分類して社会経済的な相関を示すことに成功し、Inness は都市の地理的な評価のみならず、 社会経済的な指標にもなり得ることが確かめられた。
これにより、都市の活性度が道路網から容易にわかるようになった。都市とその周辺の活性度は普通、人口や物流、生産高 などの社会的、経済的な指標に着目するのに対し、今回開発した手法はより簡便に把握することができる。
今後、同方式で中心地理論を展開するには、基本的にはインターネット上の最新の地 図情報(Open Street Map database)があればいい。研究グループは、現状の都市周辺の活性度を評価するだけでなく、将来の道路網整備が地域全体に与える効果を予測する手段となる可能性があると説明している。