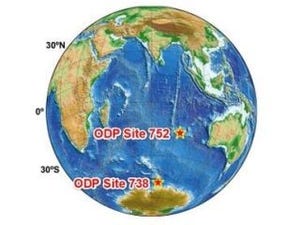東京大学(東大)は9月20日、雲の生成・消滅を詳細に計算できる全球大気モデルNICAMに、全球気候モデルMIROCの海洋部分を連結させた気象-海洋モデル「NICAM-COCO(NICOCO)」を開発し、熱帯域を東進する巨大な雲群マッデン=ジュリアン振動(MJ0)と、東太平洋の海面温度が通常より高くなるエルニーニョ現象との相互作用の再現を可能にしたと発表した。
同成果は、東京大学大気海洋研究所の宮川知己特任助教、佐藤正樹教授、理化学研究所計算科学研究機構の八代尚研究員、海洋研究開発機構の鈴木立郎技術研究員、建部洋晶主任技術研究員からなる共同研究チームによるもの。詳細は米国の学術誌「Geophysical Research Letters」掲載された。
エルニーニョ現象には、ときとして極端に強まった「スーパーエルニーニョ」と呼ばれる状態のものがあり、継続的な観測が始まって以来、1981-1982年, 1997-1998年, 2015-2016年の3度現れている。特に、1997-1998年のものは急激に終息し、場所によっては1か月に8℃も海面温度が低下した。
この急激な海水温の低下は、強まった東風と地球の回転の影響を受けて東太平洋赤道域の海水が極向きに輸送されることによって、入れ替わりに冷たい海水が下から上がってきたことが主な原因と考えられている。しかし、東風が強まった原因が何であったかについては、スーパーエルニーニョの存在によって通常と様相の違った季節進行など、複数の説があった。MJOとおぼしき降水域がスーパーエルニーニョの終息期に太平洋を通過する様子が衛星観測から指摘されていたことから、この降水域に伴う東風の影響も議論されていた。しかしMJOは数値シミュレーションでの再現が難しく、十分な裏付けは得られていなかった。
今回の研究では、MJO再現性能を持つ大気モデルのNICAMに、気候モデルMIROCの海洋部分を連結させた気象-海洋モデルNICAM-COCO(NICOCO)を開発し、スーパーコンピュータ「京」上で動作させることで、1998年5月に起きたスーパーエルニーニョの急激な終息とMJOとを同時に再現することを試みた。実験開始日を4月20日から4月28日まで1日ずつずらした9本の実験を行い、MJOに伴う東風の強弱と海面水温低下との関係を調べた。
その結果、1998年5月事例の実験データでは、MJOの雲活動の中心位置がインドネシア多島海付近にあって勢力の強かった5月半ば頃に、東太平洋赤道域において東風の強まりとともに冷たい水が海面へ上昇してくる様子がよく再現されていたほか、9本の実験それぞれにおいて再現されたMJOは東進などのおおまかな性質は一致している一方で、その振幅には実験間でばらつきが見られたとしている。
これを利用して、スーパーエルニーニョ終息の際に冷水塊が現れる東太平洋赤道域の大気下層東風のうち、MJO由来の成分と海面水温の変化との関係を調べた。その結果、MJO由来の東風が強いほど海面水温の低下が大きく、スーパーエルニーニョの終息を早めていることが明らかになったという。
また、モデルごとに固有の気候平均場の誤差を見積もるため、および、先行研究で示したNICAMとの性能比較のため、先行研究と同じく2003年-2012年に検出された19のMJO事例について、MJO中心の初期位置が異なる3つの予測開始日を設定した54本の実験を行った。さらに、1998年5月事例について従来のNICAMを用いて前述の9本に対応する同等の実験を行いった。
実験データを解析し、1998年5月事例のMJOについてNICOCOと従来のNICAMを比較した結果、両モデルとも実験開始後1週間程度経過した頃の再現性は高い一方で、海洋の変動による影響が大きくなる実験後半では性能差が明確に現れた。NICAMでは実験開始後25日以降急激に予測スコアが低下しているのに対して、NICOCOは有効な予測の目安となる0.6を実験開始後40日程度まで維持していたという。
今回の成果を受けて研究グループは、MJOとエルニーニョが引き起こす地球規模の大気変動の動向の早期把握に繋がるため、直接的な影響下にある熱帯域における降水予測や台風などの熱帯低気圧発生予測はもちろんのこと、日本付近など中・高緯度の地域における季節予測の精度向上にも貢献することが期待できるとコメント。また、今後、この実現のために必要となるモデル固有の気候平均場の誤差分を補正する機能を追加すると共に、先行研究で知られているエルニーニョ発生の引き金となる事例など、さまざまな状況における大気-海洋の相互作用の検証を進めて行くとしている。