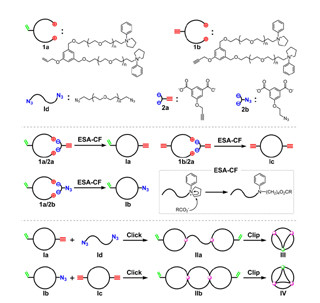スタンフォード大学の研究チームは、二酸化炭素(CO2)と水からエタノールを生成できる高性能な銅触媒の実現をめざした研究を進めている。触媒の働きを詳細に調べるため、これまでにない大面積の単結晶試料を作製する技術の開発も行った。研究成果は、米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載された。
銅は常温でCO2からエタノールを生成できる数少ない触媒の1つである。ただし、エタノール以外にも、メタンや一酸化炭素など15種類の化合物が同時に生成されることが銅触媒の問題点であると研究チームは説明する。これらの生成物の分離プロセスにはコストがかかり、多くのエネルギーが必要になる。
このため、エタノールやプロパノールのような高付加価値の化学品を副生成物なしで、CO2から選択的に生成できる新しい銅触媒の開発が望まれている。今回の研究では、このような触媒の設計をめざし、まずは触媒が実際にどのように働くのかを詳しく解明することに取り組んだ。
研究チームは、結晶の表面形状が異なる3種類の銅のサンプル、銅(100)、銅(111)、銅(751)について、ファセット(平らに成長した結晶面)の違いが電極触媒性能にどのような影響を及ぼすかを調べた。
先行研究では、面積1mm2の小さな銅の単結晶試料が使われていたが、今回は6cm2という大面積の試料を用いた。通常の単結晶銅の600倍の大きさである。このように大面積の単結晶ライクな銅をシリコンおよびサファイア基板の表面に形成する技術は、研究チームがSLAC国立加速器研究所と共同で開発した。
これら3種類の大面積の銅を電極として、水に浸し、CO2に接触した状態にして電流を流した。その結果、一定の電圧をかけた場合にエタノールやプロパノールなどの液体が選択的に生成される傾向は、銅(100)や銅(111)と比べて、明らかに銅(751)で高くなることが分かったという。
試料を大面積化する新手法は、銅だけでなく、ニッケルなど他の金属にも適用することができるため、触媒表面で起こる化学プロセスへの理解を深めていく上で有効であると研究チームは強調している。今後は触媒機構の解明と新規触媒の設計を進め、最終的には、再生可能な電力あるいは太陽光を直接利用した人工光合成プロセスによってCO2からのエタノール生成をめざすという。