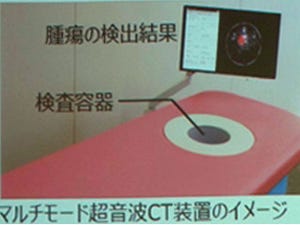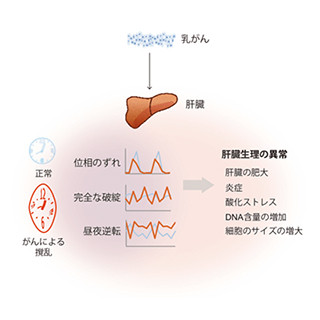京都大学は、乳がんの手術前に化学療法を行い、手術後にも抗がん剤の一種であるカペシタビンを投与すると治療後の生存期間が延びることを確認したと発表した。同研究は、京都大学大学院医学研究科の戸井雅和教授らの研究グループによるもので、同研究成果は、6月1日に米国の科学誌「The New England Journal Medicine」に掲載された。
乳がんにおいて、手術前に化学療法を施しても組織に広がる癌が残ってしまう場合は、治療後の経過が思わしくないのが現状となっている。同研究では、乳がんの手術前にアントラサイクリン系薬剤やタキサン系薬剤、またはその両方を用いた化学療法を施しても組織に広がる乳癌の病巣が残ってしまう症例の中でも、ヒト上皮増殖因子受容体2型1(HER2)陰性乳癌患者910例を対象に解析を行った。
同研究チームは、手術後に行う標準的な化学療法にカペシタビンを追加する群(カペシタビン群)と追加しない群(対照群)に無作為に分け、治療後の無病生存期間や全生存期間を評価対象として2群間の比較を行った。カペシタビン群と対照群の年齢層はどちらも25歳~74歳で、中央値は48歳であった。症例は2007年から2012年の間に登録されたもので、日本から606例(62施設)、韓国から304例(22施設)が集まった。
最終解析では、カペシタビン群の無病生存期間は対照群の無病生存期間よりも長く、治療後5年の時点でカペシタビン群では74.1%に再発や他の病気が見られなかったのに対し、対照群では67.6%にとどまった。全生存期間もカペシタビン群では治療後5年の時点で89.2%が生存していたのに対し、対照群では83.6%と有意に優れていたという。ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)受容体陰性かつHER2陰性のトリプルネガティブ乳癌患者においても、カペシタビン追加の意義が観察されており、治療後5年の時点での無病生存率ではカペシタビン群が69.8%に対し対照群56.1%、全生存率ではカペシタビン群が78.8%に対し対照群は 70.3%と明らかな予後の改善が認められた。副作用に関しては、カペシタビンに関連する最も頻度の高い有害事象である手足症候群が73.4%の症例で現れた。
同研究は、HER2陰性乳がんに対し標準的な手術前の化学療法を行った後も、組織に広がる癌病巣が残っている患者に対しては、手術後の化学療法でカペシタビンを投与することで無病生存期間、全生存期間が延長できると考えられるという結果となった。今回の研究成果は、HER2陰性乳がん患者の予後の改善に寄与するとともに、今後の乳がん治療の進展に貢献することが期待されるということだ。