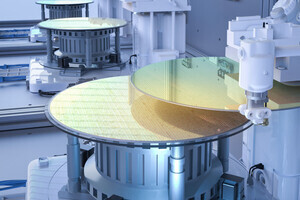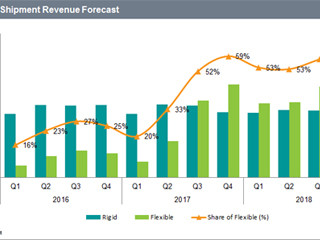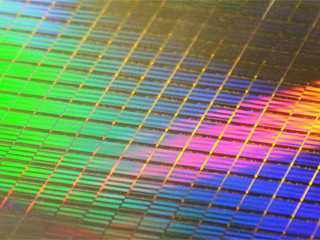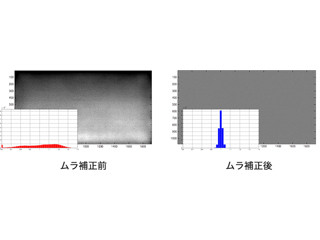ケンブリッジ大学、イースト・アングリア大学、東フィンランド大学などの研究チームは、高い発光効率を示す新しい有機EL材料を開発したと発表した。材料分子がプロペラのように回転する性質を利用して発光効率を高めたという。
真空装置を使わずに、溶液プロセスによって100%近い内部量子効率の有機ELを実現できるという利点があり、実用化に向けた製造コストの低減が期待できる。研究論文は、科学誌「Science」に掲載された。
有機EL材料に電気エネルギーを与えると、材料中で電子と正孔のペアが高エネルギー状態に励起した「励起子」が生成される。その後、励起子が低エネルギーの安定状態(基底状態)に戻るときに、差分のエネルギーの一部が光となって放出される。励起子には、電子のスピン方向の違いによって「一重項励起子」と「三重項励起子」があるが、有機EL発光に寄与するのは通常、一重項励起子だけである。三重項励起子のエネルギーはほとんどの場合、熱に変換されてしまい、発光には利用できない。
一重項励起子と三重項励起子が生成する比率は1:3になることが理論的にわかっている。蛍光発光型の有機EL材料では、発光に一重項励起子しか利用できないので、内部量子効率は25%程度が上限となる。これに対して、三重項励起状態も発光に利用できるようにした有機EL材料が、りん光発光型や熱活性化遅延蛍光型(TADF)と呼ばれるもので、一重項励起子と三重項励起子の両方を発光に利用できるため、100%近い内部量子効率を得ることができる。
りん光型有機EL材料では、三重項励起状態から基底状態に戻るときの差分のエネルギーが熱に変換されずに光として利用できるが、イリジウムや白金などのレアメタルを使用する必要があるためコスト面に問題がある。一方、TADF材料では、低エネルギーの三重項励起状態が高エネルギーの一重項励起状態に移動する逆項間交差と呼ばれる過程が利用され、三重項励起子がいったん一重項励起子に変換されてから蛍光発光する。TADF材料は、2012年に九州大学の安達千波矢氏らのグループが開発に成功した比較的新しいタイプの有機ELであり、レアメタルを使わずに100%近い内部量子効率を実現できるため研究開発が活発に進められている。
今回ケンブリッジ大などが開発した有機EL材料も、基本的には、TADF材料と同じメカニズムで逆項間交差を利用して三重項励起子を発光に使うタイプである。これまでのTADF材料と異なるのは、三重項励起状態から一重項励起状態への逆項間交差を経て蛍光発光までにかかる時間が、常温で350ナノ秒以内と短いことである。TADF材料では三重項状態を経て発光するまでに時間がかかることから、遅延蛍光という名称が付いていた。今回の材料では、発光時間が短縮されることで、より高輝度の有機EL発光が実現できると考えられる。
このような発光過程の急速化が可能になった理由は、電子供与体(ドナー)のアミドと電子受容体(アクセプター)のカルベンが銅を介して結合している同材料の分子構造にあるという。コンピュータでの計算によると、この構造ではドナー分子とアクセプター分子が、銅を軸にしてプロペラのように回転すると考えられる。この分子の回転運動が影響して、一重項励起状態と三重項励起状態のあいだのエネルギーギャップが0に近い値になるため、三重項励起状態から一重項励起状態への逆項間交差が起こりやすくなるという。
同材料は、真空装置を使用しない溶液プロセスに適しており、研究チームは実際に溶液プロセスで作製した有機ELデバイスで、100%近い内部量子効率、27%以上と高い外部量子効率を実証している。これは真空プロセスで作製された最高性能の有機ELに匹敵する値であり、溶液プロセスによるデバイスとしてはこれまでに報告されている中で最も良いものであるとしている。
研究チームのDawei Di博士は今回の研究について、「励起状態の電子スピンと分子運動が組み合わさることで有機ELの性能に大きな影響を与えることを示した。これは、基礎科学としての量子力学が、大きな市場を有する商業的応用に直接つながることを実証するものだ」とコメントしている。