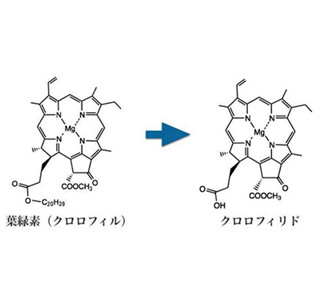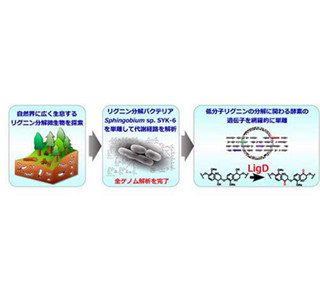名古屋大学は4月24日、シロイヌナズナとう植物を用いた実験で、細胞死をもたらす新しい細胞融合現象を発見したと発表した。
同成果は丸山大輔 YLC特任助教と東山哲也 教授らのグループによるもので、4月23日付(現地時間)の科学誌「Cell」のオンライン版に掲載された。
花粉には精細胞を胚のうへと届けるための花粉管という細胞を持つ。花粉管は長い管状で、先端内部に2個の精細胞をもっている。花粉が雌しべに受粉すると、この花粉管が伸びて雌しべ内部へ入っていき、種の元になる胚珠と精細胞を届ける。この時に、卵細胞の隣に2つある助細胞が花粉管を正確に胚珠に導くための誘引物質を放出する。
花粉管が胚珠にたどり着くと、片方の助細胞の破壊と引き換えに内部の2つの精細胞を放出する。このうち1つは卵細胞と受精し幼植物となる「胚」をつくり、片方は中央細胞と受精して胚への影響を供給する「胚乳」という細胞をつくる(重複受精)。この2つの受精の後で、生き残った方の助細胞は素早く不活性化され、花粉管の誘引停止が起こるが、その仕組について詳しいことはわかっていなかった。
今回の研究では、受精後に残った方の助細胞の不活性化について調べるために、シロイヌナズナという植物を用いて、ミトコンドリアを緑色蛍光タンパク質(GFP)でラベルした助細胞の経時観察を行った。その結果、助細胞のミトコンドリアが隣に位置する胚乳へ移動することが判明した。電子顕微鏡で助細胞と胚乳を隔てる部分を調べると、受精前には無かった穴が発見され、受精後に助細胞と胚乳が融合し、助細胞の内容物が胚乳へと流れ出ていることがわかった。
また、助細胞が作り出していた花粉管の誘引物質をGFPでラベルして観察したところ、誘引物質も胚乳へ移動しており、助細胞での濃度が急激に低下していた。したがって、細胞融合によって誘引物質の供給が途絶えることによって、2本目以降の花粉管が目標を定められない状態となっていることがわかった。さらに、助細胞の核を観察した結果、胚乳核の分裂に合わせて分裂しようとするものの、最終的に分裂できず変性することも判明した。これらにより、助細胞の不活性化は、細胞融合による誘引物質などの希釈と核の崩壊という二段階の仕組みで発生していると結論づけられた。
植物の細胞は堅い細胞壁に覆われているため、卵細胞と中央細胞の受精以外で植物細胞同士が融合するとはこれまで考えられていなかった。また、成長過程での細胞死は、死ぬべき細胞自身が自殺プログラムを実行していると考えられていた。今回の現象は細胞融合によって融合相手が不活性化するという新しい細胞融合があることを示したもので、同研究グループは「教科書を書き換えるほどの成果といえる」としている。