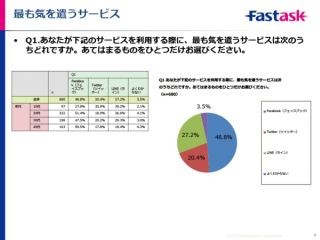SNSの広がりは今更説明するまでもないが、企業内におけるSNSの有用性も近年認められてきている。採用企業は次第に増加しており、MicrosoftのYammerやsalesforce.comのchatterがその代表格だ。今回、Yammerの創業者でCTOのAdam Pisoni氏が来日し、インタビューをする機会を得たので、その内容をお届けしたい。
最大の魅力はOfficeとの連携
インタビュー内容について触れる前に、Yammerがどのようなサービスを提供しているかについて触れておきたい。
Yammerは2008年にサービスを開始した社内SNSで、2012年6月には米Microsoftが同社を12億ドルで買収した。買収後は、主にOffice 365との連携が進められており、単なるコミュニケーションサービスではなく、社内情報ポータルとしての強みも持つ。
2013年6月の時点でYammerユーザーは800万人を超えており、現在はOffice 365の法人契約者を合わせて更にユーザーが伸びているという。また、米国Fortune誌が毎年発行している売上の上位500社を表わす「Fortune 500」に掲載されている企業のうち、85%以上がYammerを利用しており、多くの企業がYammerを支持していると同社では説明している。
――米Microsoftに買収されたことは良かったか。
もちろん、そう思っているよ。6年前にYammerが始まったとき、Enterprise SNSは誰も知らなかった。しかし、時を経るにつれてビジネスの中、進め方の中に組み込まれてきていることを感じる。E-mailやOfficeといったビジネスのキーとなるソリューションと統合できることがMSによる買収で得た強み。グローバルに存在するMSの何十億という企業、ユーザーに対するリーチが容易になったことでインパクトが与えられるようになるだろう。
――では、Yammerとして一番期待しているMSとの統合メリットはOffice連携なのか?
そうだ。Outlookのチーム、Wordのチーム、それぞれと連携・統合を行っている。SharePointとの統合も進んでいるが、統合効果だけではなく、ユーザー数の増加が加速したのはMSのお陰だと思っている。営業体制などもしっかりと構築されているという点が大きいと思う。
――LINEのようなスタンプがコミュニケーションに導入されたが、意識しているのか?
(LINEがあまり広がりを見せていない)米国でも広く使われているコミュニケーション方法だし、特に意識したことはない。フレンドリーでもっとクリーン(簡潔)なメッセージングを提供したいと考えてやってと思い導入した。
(Facebookにユーザーインタフェースが似ているとの問いには)昔はもう少し似ていたかもしれない(笑)。これは意識している面もある。ユーザーが戸惑うことなくサービスを利用できるように配慮した結果なんだ。
――競合であるsalesforce.comのSalesforce1ではモバイル端末との連携が非常に有効だと感じた。それに対するYammerのアドバンテージを教えていただきたい。
Yammerの利用者は分断されていたコミュニケーションを、働き方を変えたいということで導入している。最も重要な要素でいえば、社内におけるコミュニケーションの質と数の向上を図るために企業は社内SNSを導入する。その際に、社内で利用しているツールとの融合が重要視されるわけだが、Salesforce1はカスタマーサービスとの統合という面では良いものを持っていると思う。その一方でYammerは全社横断的にコミュニケーションの深化ができる。例えば、レストランの現場で働いている人と、マーケティング部門の人間が直接、気軽にやり取りができるというようにね。そして改めての話になるが、世界で10億人が利用するOfficeとの連携が最大の魅力だろう。
――SMBやSOHOといった企業にも導入メリットは存在するのか?
もちろん、5名規模の1つのオフィスで完結する企業では必要ないかもしれない。しかし、一つのグループでは完結できなくなる、20~30名規模になると、Yammerの導入効果が見えてくるのではないか。別部門との繋がりを通して、新たな需要を見つけていくことが、Yammerの導入によって容易になる。実際にYammerを導入している企業は半分が大企業だが、もう半分は中小企業だ。
――なぜフリーミアムモデルを採用しているのか。中小企業が導入しやすいようにする配慮か?
フリーミアムには2つの理由がある。財務基盤が弱い中小企業のみを狙ったものではなく、大企業についてもフリーで試してもらう意味合いはあると感じる。それが1つ目の理由だ。
2つ目はそれほど明確な理由ではないが、コンシューマー製品と比較してエンタープライズ向けの製品はあまり質が良くないと思っている。導入する際にまとまって購入するため、どこも品質改良などを積極的に行なっていないと思う。私たちは、ユーザーに見てもらって、試してもらい、選んでもらうことがベストだと思っている。
――Yammerは導入すれば、ユーザーが能動的にコミュニケーションを深めるものなのか、それとも運用側が促す必要があるのか?
ある程度の規模を持つ会社では、運用者がコミュニケーションを喚起する必要があると思うが、基本的にはSNSに親しみを持つ若年層からボトムアップで広がっていく傾向にある。
もし、エンタープライズSNSに問題があるとすれば、それは技術的な問題ではなく、行動の変革に繋がっていないところに問題がある。
そこで私たちはCSM(Customer Success Manager)を派遣し、利用率の向上やコミュニケーションの増加など、いかに展開していくかをアドバイスしている。
例えば、トップマネジメントの人間が関わることでコミュニケーション、コラボレーションが活性化されているという数字が出ており、結果としてエンゲージメントも上がっている。例えば、昨年導入していただいた中古車販売大手のガリバーは、トップがYammerを通して販売店にまで深く関与しており、社内の様々な意見・アイディアの交換が行なわれていると聞いている。
――とはいえ、日本企業では自分の意見をあまり言いたがらない人が多いように思いますが……。また、産業別などでもコミュニケーションの違いなどがあるのでは?
産業別のコミュニケーションについては特にないと思う。まんべんなく(様々な企業で導入されて評判に繋がり)広がりが見えている。確かに国別では差が見えてきている。オーストラリアでは立ち上がりが速くて、採用数がすぐに上がっていった。
そして日本のケースでは、エグゼクティブが積極的に関与していく必要があるのかなと感じている。その一方で、若い人たちが多い会社では積極的な採用、活用例が多いと思う。
企業の中には硬直的で階層ができあがっているところがある。コミュニケーションを望まない企業もあるが、そういうところは良い働き方ができないのではないか。
特に大企業は新しいものを恐れて、社員に権限や発言権を与えることに及び腰になりがちだ。「何か会社について悪影響を与える発言をしたり、文句を言うのではないか」と無駄な心配をしているが、多くの企業を見る限りそんなことはない。社員に対して尊敬の念を持ってコミュニケーションを進めてほしい。
――日本企業のYammerに対する反応はどうか
日本については日本マイクロソフトのプレゼンスが高いため、多くの関心をいただいている。日本の企業はコミュニケーションや社内コラボレーションの重要性に気付いており、臨機応変、コンペティティブ(競争心)を持ってやるためにYammerを採用しようという気概がある。
(日本企業はおとなしいというイメージもあるがとの問いに)米国だからといって、誰でもコミュニケーションを積極的に行なうわけではなく、苦労している現実がある。6年前にYammerを始めたときは、アメリカでも「こんなものは上手く行かない」と言われた。企業によっては自分の携帯電話を持ち込むことすら許されていなかったからね。それが時代の変化と共に、グローバルに展開できるまで成長することができたんだ。
――Yammerを導入した場合、どれほどの効果があったのかと金額換算はできるものなのか?
確かに金額換算は難しい話だ。意思決定の迅速化が強みの一つだが、それを金額に変えられるかというと難しい。ただ、米国のクローガ―というスーパーマーケットチェーンでは、地域を分けてYammerを導入し、利用した地域と導入しなかった地域を比較して導入効果を試算していた。
それと、ROI(投資対効果)でいえば、20年前はE-mailなんて利用していたのはごく一部だっただろう。どこの企業もE-mailの価値なんて理解していなかったと思うが、現在は当たり前の存在だ。SNSもそのような位置づけになると思っているよ。
――グループウェア企業内BBSはなくなると思うか?
今までのコミュニケーションツールは長年使われてきたので、すぐになくなるということはないと思う。一方で新しい"SNS"という存在は、人と人との"ネットワーク"をベースとしている。もし社内の知らない人であっても、そこに情報があれば利益を享受することができるし、コミュニケーションが生まれる。
今、Yammerが目指しているのはエンタープライズグラフの構築。会話やオブジェクトの全てを関連付け、エンタープライズグラフ全体を見通して、どこにどのようなものがあるか把握できるようにしたい。また、関連する似たようなトピックスとの紐付けも考えている。まだできていないが、楽しみにしてほしい。
――ありがとうございました。
なお、Yammerは1月にアジア圏としては初めてとなるイベント「Working Social Tour」を東京・新橋で開催した。Pisoni氏のほか、日本マイクロソフト オフィスビジネス本部 エンタープライズプラットフォームグループ シニアマネージャー 寺田 和人氏とYammer最高製品責任者Pavan Tapadia氏が登壇。多数の来場者に対してYammerのコンセプトやモバイル端末との親和性の高さ、Office 365との連携機能などを説明していた。