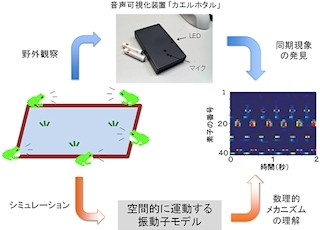北海道大学(北大)は2月6日、クワガタムシのオス/メスの性別を決定するために必要な遺伝子の同定に成功したと発表した。
同成果は、同大の後藤寛貴氏、宮川一志氏、三浦徹 准教授、石川麻乃氏、石川由希氏、杉目康広氏、ワシントン州立大学のLaura C. Lavine氏、モンタナ大学のDouglas J. Emlen氏らによるもの。詳細は「PLoS Genetics」に掲載された。
生物の中にはオスとメスで大きく異なった姿をしている種類が多く存在しているが、なぜそうした差が発生しているのかはよくわかっていなかった。そこで今回研究グループは、オスは大きな「ハサミ」と呼ばれる一対の大顎を持つが、メスではそうした大顎の発達が見られないクワガタムシに着目。その性決定遺伝子の1つである「doublesex (dsx)遺伝子」に注目し研究を行ったという。
具体的には、これまでの研究からクワガタムシでは幼若ホルモン(juvenile hormone:JH)がオスの大顎発達を引き起こすことが報告されていたことを受け、性決定遺伝子が大顎のJH応答性制御を通して、雌雄の大顎発達の違いを生じさせているという仮説を立て、材料として用いた「メタリフェルホソアクワガタ(Cyclommatus metallifer)」より、dsx遺伝子を単離し、配列の同定を実行。その後、RNA干渉(RNAi)法を用いてdsxの機能阻害を行い、その機能を解析したほか、dsxの機能阻害とJH処理を組みあわせた実験を行い、dsxの機能阻害で大顎のJH応答性が変化するかの調査を行ったという。
配列同定と発現解析の結果、同クワガタではdsxは少なくとも4種類の異なるタンパク質へと翻訳されることが判明し、そのうち2つは主にオスで作られ、残りの2つは主にメスで作られることも確認されたとのことで、これにより、性特異的に作られるオス型とメス型のdsxタンパクは、それぞれオスへの分化とメスへの分化を促進することが示されたとする。
また、幼虫の期間中(成虫の形態が形成される前)にRNAiによりdsxの機能阻害を行ったところ、dsxの機能を抑制した個体では、オスでもメスでも、雌雄の中間的な特徴を持つ成虫になることも確認された。
さらに、dsxの機能阻害とJH処理を組み合わせた実験として、dsxの機能阻害を行っていない場合では、オスではJH処理により大顎の過剰発達が引き起こされたが、メスでは大顎サイズに変化はないことを確認したほか、dsxを機能阻害した場合では、オスでもメスでもJH処理により大顎の発達が引き起こされることも確認。
この結果から、dsxが働かない状態ではオスでもメスでも大顎はJHに応答して発達を起こすことが示され、メスで発現するメス型dsxに大顎のJH応答性を抑制する働きがあることが示唆された。
今回の成果について研究グループでは、「性決定遺伝子が大顎のJH応答性制御を通して、雌雄の大顎発達の違いを生じさせている」という仮説を支持するものであり、性決定遺伝子とホルモン経路の関係についてのこの新たな知見により、さまざまな昆虫で雌雄間の形態差を生じさせる発生メカニズムに関する研究が進むことが期待されるようになるとコメントしている。