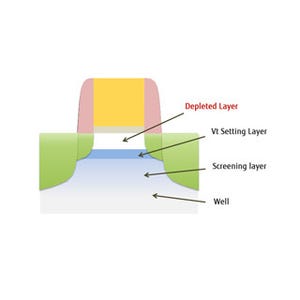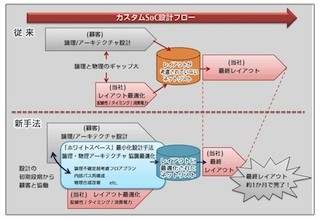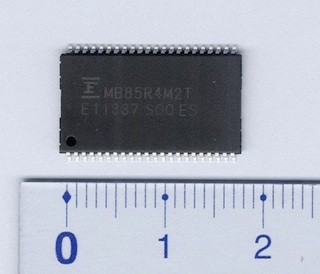富士通研究所と台湾の研究機関である工業技術研究院(Industrial Technology Research Institute:ITRI)は1月8日、防災分野において人手を介さずに機器同士が情報伝達を行う自律型センサネットワーク技術に関する共同研究を開始したと発表した。
近年、風水害などによる自然災害が世界各地で発生している。従来の防災・減災に関連する技術では、例えば地すべりなどに対する地質のデータ収集や、予兆の分析手法としてレーザ計測や、斜面を掘削して高精度ひずみ計を埋設させて測定分析を行う技術などがあった。しかし、測定機器自体が高価なことに加え、配線や設置、電池交換などの手間がかかるため限られたエリアの測定しかできず、結果的に広域で網羅的なデータを取得することができなかった。
今回、富士通研究所とITRIは、測定地域を面として広域かつ網羅的にデータを収集する技術開発を行うという。自己発電を行う多数のセンサを無線で結合し、自律的に連携するM2Mネットワークにより、崩落が発生しそうな場所のデータを収集するシステムの構築を目指す。
ITRIは主にセンサノードの開発を担当し、センサ、通信ネットワーク、無線ソフトウェア、電力制御の研究開発を行う。センサノードを地すべりが発生しそうな場所に多数配置し、サーバに送信されたデータを現地大学の土木工学の専門家の協力を得ながら分析する。さらに、自主開発したソーラーアンテナ技術を用い、効率の良い通信と発電を両立させる。
富士通研究所は主に多数のセンサノードを自律制御するソフトウェアの開発を担当し、遠隔制御やセンサ間の通信エラー回避の研究開発を行う。組み込みソフトウェアや分散処理技術により、無線通信時のノイズやセンサ故障が発生しても周りのセンサ同士が連携できる仕組みを構築する。これにより、環境変化に起因する故障に強いシステムが実現するとしている。
これら、双方の技術の長所を融合することで、自律型センサネットワーク技術を確立し、将来、防災・減災に関するデータ収集と分析を行うシステムとして活用する。さらに、防災に限らず、幅広い分野に応用していきたいとしている。