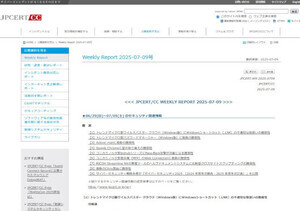モノ作りに携わるクリエイターは、多くの人々が憧れる職業のひとつだ。しかし、実際にクリエイターとして活躍できるのは、才能やセンス、運など、様々なハードルをクリアした限られた人材であることも否めない。今回は、デジタルハリウッド・デジタルコミュニケーションアーティスト専攻(全日1年制)の担任講師であり、WEB制作会社アンティー・ファクトリーの代表取締役社長でもある中川直樹氏をはじめ、中川氏の担任するコースの卒業生でアートディレクターの平野北斗氏、おなじくデザイナーの若澤亮氏、そしてデジタルハリウッド・デジタルコミュニケーションアーティスト専攻(全日2年制)に現在所属している現役学生 大内仁美氏といった様々な立場から、クリエイターに必要なスキルなどを探っていく。
――平野さんたちは転職して、クリエイターないしは、今の職種になられたとのことですが、以前は、どのような仕事をしていたのですか?
平野氏:僕は、屋外広告系グラフィックのデザインを担当していました。しかし、このままグラフィックデザイナーとして、歳を重ねていくことに漠然とした不安を感じたんです。そこで、今後の将来を見据え、新しいインタラクティブなコンテンツ制作などについて学ぶため、改めて学校でデザインの勉強をすることにしました。
若澤氏:もともとは、総合大学の美術科でグラフィックデザインについて学び卒業後に、営業職として印刷関連の会社へ入社しました。そこで2年間営業として勤務していたのですが、ある日「僕は、何をやっているんだ!」と一念発起し、改めてデザイナーへの道を目指すことにしました。
大内氏:私は高校時代、デザイン科に通っていたのですが、卒業後、印刷関連の会社で一般事務として3年間働いていました。高校時代にデザイナーを目指していたこともあり、就職してから一般事務として働いている現実とクリエイターを目指していた自分とのズレに悩んでいました。そんなとき高校時代の恩師から、デジタルハリウッドを紹介されたんです。それが仕事を辞め、学校に入学するキッカケになりましたね。
――― みなさんがクリエイターになると決意したとき、なぜ、デザイン会社などへすぐに就職するのでなく、学校でデザインを再び学ぶという道を選んだのですか?
平野氏:デジタルサイネージやプロジェクションマッピング、AR技術といった先端の広告手法などを学びたかったことが最大の理由ですね。当初は、週末だけの通学も考えていたのですが、最終的には1年間の集中的なカリキュラムでみっちりとデザインを学べる「デジタルハリウッド・デジタルコミュニケーションアーティスト専攻(全日1年制)」への入学を決意しました。決め手は、自分がやりたかった先端広告手法に関する授業や、実務トレーニング(企業実案件をグループワークにて制作)などが用意されている点、第一線で活躍している現役クリエイターが講師を務めている点、幅広く実践的なスキルを習得できるカリキュラムなどですね。
若澤氏:当然、そのままデザイナーとして就職を目指すという選択肢もありました。しかし、前の会社を辞めるとき、大学時代の講師や先輩と相談し、「デザインという現場は日々進化しているものであり、お前が知らないことも沢山ある。それをしっかり学んでからデザイナーを目指しても遅くはない」というアドバイスをもらったんです。また、自分自身、印刷業界に身を置き、多くのことを学んだのですが、一方で視野が狭くなっていると感じた部分もあったんです。そのため、再度学校に通って本格的にデザインについて学び直すことにしました。僕は、当初から集中して1年間のみ最新のデザインについて総合的に学びたいと思い、その条件に合ったのが、「デジタルハリウッド・デジタルコミュニケーションアーティスト専攻(全日1年制)」コースでした。
大内氏:地元ではクリエイターやデザイナーなどの求人が圧倒的に少なく、希望する職種での就職が困難だったんです。また、私が転職することを決めたときに、ちょうど「デジタルハリウッド・デジタルコミュニケーションアーティスト専攻(全日2年制)」が新設され、このコースでは、デザインを基礎からしっかりと学び、最先端のデザインに至るまでを習熟できるということで、就職でなく学校への入学を決めました。
――皆さんが通われていた(通っている)デジタルハリウッド・デジタルコミュニケーションアーティスト専攻では、どのような授業が行われているのですか?
中川氏:現在、クリエイティブの現場で活躍している平野君と若澤君は、私が担任をしているデジタルコミュニケーションアーティスト専攻(全日1年制)の第1期卒業生なのですが、当初から現在まで一貫しているのは「現場で即戦力となる人材を育成する。そして、自分が自身の会社で欲しいと思える人材を育てる」ということです。全日1年制コースは、デザインなどの経験者を想定したハイレベルなクラスとなっており、その指導方法などについても私が自社のスタッフを育てるときとほぼ同等の感覚で臨んでいます。そのため、厳しいと感じるようなことも多いかもしれません(笑)。
日々、変化/進化を続ける「デジタルコミュニケーション」の世界で今必要とされているのは、デザイナーという枠に囚われない幅広い知識とスキルを備えた人材です。多彩なカリキュラムの中から、個人の特性や適正にマッチした様々な可能性を探っていけるのも、デジタルコミュニケーションアーティスト専攻のアドバンテージといえるでしょう。
平野氏:就職後、想像以上に、学校で身につけたスキルが役立っていることに驚きを感じています(笑)。例えば課題で行ったグループワークでは、プロジェクトのマネージメント、デザイン、ディレクションといった企画から制作に至るまでのワークフロー全体を学ぶことができたのですが、それをそのまま仕事で応用することが可能だったんです。また、授業では、企業実案件を扱う実務トレーニングなども用意されており、各企業との取組みにおいては、デザイナーとしてだけでなく、プランナーやマネージャー、ディレクターなど様々な役割を経験できたのも貴重な体験でした。
若澤氏:僕は、現在東芝マーケティングコンサルタントのデザインセンターで、主にインフラ系のデザインを担当しています。そのデザインには、グラフィックデザインをはじめ、Flashアニメーションや動画など様々な知識と技術をフル活用する必要があり、学校で学んだことが、それらすべてにおいて役立っています。なので、他の学校に比べて高い授業料にも納得しています(笑)。デジタルハリウッドでの実践的な授業は、厳しいことも多かったのですが、授業時間外でも相談にのってくれた先生には今でも感謝しています。
大内氏:他の専門学校などでは経験できないような実践的な授業や課題、コミュニケーションスキルなど様々なことをトータルに学べるのが、私にとっては大きい魅力だと今、実感しています。自ら仮想のクライアントを設定し、常に"実務"を意識して制作に取り組んでいます。また、カリキュラムの一環としてだけでなく、デジハリを卒業し、現役で活躍しているデザイナーの先輩たちから直接作品についてアドバイスをもらえたり、アルバイトとして仕事をもらったり、とてもありがたいですね。時には自分の作品に対し、諸先輩方から辛辣なコメントをもらって、かなりヘコみそうになることもありますが、それを糧に作品のクオリティを上げていけたらいいなと思います。
――デザイン現場と教育現場の両サイドにおられる中川氏から、今後のクリエイターにとって必要なことなど、アドバイスをいただけますか?
中川氏:ソーシャルメディアの普及とウェブテクノロジーの発展により、デザインの世界はボーダーレスに広がりを見せ、グローバル化してきています。これからのクリエイティブの現場でのコンペティターは、必然的に日本にとどまらず世界になっていくでしょう。そんな中で、世界のデザインのトレンドを理解しながら、日本人としてカルチャーやアイデンティティを、デジタルコンテンツの中でいかにアピールしていくかも大切なポイントなりそうです。私の教える授業では、そんな世界に求められるクリエイティブな人材を育成する場として確立させていきたいと考えています。
――最後に、若きクリエイターの皆さんから、今後の目標や展望などをお聞かせください。
平野氏:卒業してからアートディレクターとして仕事をしている中で、建築業界やウェディング業界の方々とコラボレーションし、デジタルコンテンツを制作する機会に恵まれました。異業種の方々との共同作業とデジタル技術によって新たな価値観を生み出せるデザインワークは、まさに僕が入学前にやりたいと思い描いていたものです。これからも幅広い視野を持って、もっと様々な業種の方々とコラボレーションしていきたいですね。
若澤氏:デザイナーとして独立して、ひとりでも仕事をやっていけるような実力を身につけたいです。その上で、中川先生のような第一線級の方々と一緒に仕事ができたらと考えています。現在は社会インフラに関する仕事をしており、まだまだ学ぶべきことも沢山あるので、まずはこの分野のエキスパートとして、その道を極めていきたいと思いますね。
大内氏:私は、現在のところ卒業制作に没頭する毎日を送っています。今後は、憧れの諸先輩方を見習いながら、デザインの現場で役立つ様々なことを幅広く吸収して自分のスキルを磨いていきたいと思っています。
撮影:佐藤徹三