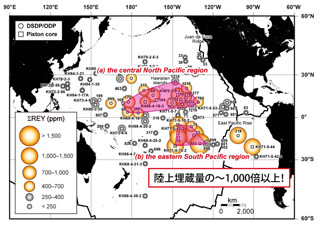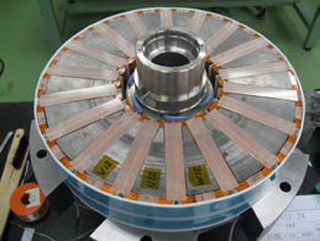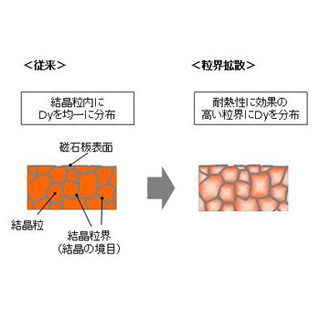東北大学は12月5日、液晶パネルやLEDなどの生産で用いられるアンチモン(Sb)やインジウム(In)といったレアメタルが中国大陸から大気降下物として飛来していること、またその蓄積速度がこの30年間で急激に増加していることを秋田県と岩手県をまたいで広がる八幡平山岳湖沼の湖底堆積物分析から明らかにした。
同成果は同大 占部城太 郎教授、愛媛大学 加三千宣 講師、槻木玲美 研究員らによるもので、詳細は微量金属に関しては環境科学の国際誌「Science of the Total Environment」に、山岳湖沼の富栄養化に関しては生態学の国際誌「Ecological Research」にそれぞれ掲載される。
これまで近過去(100~200年前までの過去)の生態系の様子や現在に至る変遷や変化はモニタリングデータがないため知るすべはなかったが、研究グループでは湖の底から柱状堆積物を採集し、鉛放射性同位体およびセシウム放射性同位体を用いた年代測定と堆積物に含まれるプランクトン遺骸や化学物質の分析を行うことで、100~200年間の湖沼の生物相の復元や環境の変遷を解明するための技術開発を行なってきており、今回、日本の山岳湖沼の現状の近年の変化を把握するモニタリング研究の一環として、それら技術を用いて八幡平の八幡沼と蓬莱沼の環境変化を解析したという。
この結果、八幡平の山岳湖沼でアンチモン(Sb)やインジウム(In)の他、すず(Sn)、ビスマス(Bi)などのレアメタルの堆積速度が1960年以後、急激に増加していることが判明した。
これらのレアメタルは日本での採掘は現在行われておらず、湖底での堆積速度増加は集水域や近隣から混入することは考えられないことから、解析と平行して鉛の安定同位体比を調べたところ、1960年ごろから大陸起源の大気降下物が増加し湖底に堆積していることが明らかとなった。鉛の安定同位体比は石炭の産地を指標することが判っており、八幡平の湖沼堆積物の鉛同位体比は日本ではなく、中国の石炭燃焼の際に発生する鉛同位体比と一致したとのことで、これらのレアメタルが中国大陸から飛来し湖沼の湖底に堆積していることが裏付けられたという。
各種のレアメタルは半導体を中心とするエレクトロニクス産業で活用されているが、その多くが中国で産出、精製されており、その多くが石炭の燃焼とともに浮遊微粒子(エアロゾル)として大気に放出されている。今回の研究では、中国大陸を起源とする浮遊微粒子が広く飛散し、大気降下物として日本列島に飛来・蓄積している影響により、居住者がほとんどおらず手付かずの自然が残されていると考えられてきた山岳地帯においても、過去30年の大陸からの降下物の影響で窒素やリンが増加し、植物プランクトンのほか、それを餌とするミジンコも増加するといった富栄養化が進行していることも判明したという。
ただし、湿原土壌は栄養物質のなかでもリンを吸着する性質があるため、湿原に囲まれた八幡沼では富栄養化の進行は顕著ではないとのことで、山岳地帯にある湿原が大気降下物の影響を緩和するうえで重要な機能を担っていることを示唆する結果となったと研究グループでは説明する。
なお、SbやInは人に対する毒性も報告されている物質だが、今回の調査により判明したレアメタルの大気降下の増加が実際に人の健康や生態系にどのような影響を及ぼしているのかはまだ良く分かっていないとのことで、今後、研究を進めていく必要があると研究グループではコメント。また、八幡平での大気降下物による富栄養化の進行は、大陸起源の大気降下物が日本の自然や生態系に対して影響を着実に及ぼしつつあることを示すものであり、生態系の保全には地域だけでなく大気降下物の発生地域を含めた広域的な取り組みが必要であることが示されたことは、大気降下物の起源・由来や降下量だけでなく、その生態系への波及効果の解明が人の健康や日本の自然生態系を保全していくために重要になってくると指摘している。