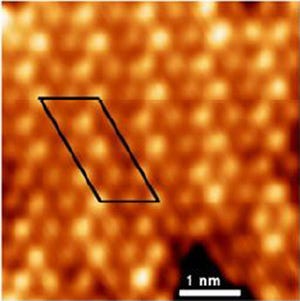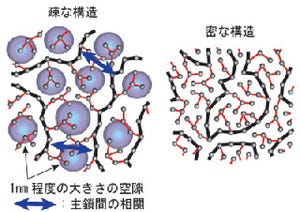慶應義塾大学(慶応大)医学部の永井重徳 助教らの研究グループは、自己免疫疾患の原因となる免疫細胞が増える、新たな免疫調節の仕組みを発見したと発表した。同成果は、米国オンライン科学雑誌「Cell ReporTs」に掲載された。
ヒトの免疫システムでは、免疫細胞と呼ばれる細胞がさまざまな病原体を監視して病気にならないように働いている。免疫細胞の一種であるヘルパーT(Th)細胞は、病原体の種類に応じてTh1、Th2、Th17細胞に分化することが知られており、これらの細胞によって効率良く病原体が排除される。Th17細胞は、炎症反応を引き起こして病原体を排除するが、自己免疫疾患である関節リウマチや炎症性腸疾患などを悪化させる細胞であるとも考えられており、このTh17細胞の分化の仕組みが分かればTh17が原因の自己免疫疾患の治療につながる可能性があるため、その解明が求められている。
未分化なT細胞がTh17細胞へと分化するためには、抗原による刺激とともにインターロイキン6やTGFβなどのたんぱく質(サイトカイン)が必要であり、これらの刺激によって発現するRORγという転写因子がTh17細胞の分化に必須であることはすでに知られている。また、脂質リン酸化酵素の一種であるPI3Kはさまざまな細胞で細胞分裂や代謝などの細胞機能を調節する重要な役割を担っており、免疫細胞においても、PI3Kが免疫細胞の分化や機能に重要な役割を果たすことが知られ、Th17細胞の分化にも関与されていることが予想されているが、具体的にどのように関わっているかについては不明であった。
研究グループではまず、PI3KとTh17細胞の関係を調べるため、未分化のT細胞をTh17細胞に分化させる時にPI3Kの酵素活性を阻害する薬剤を加え、Th17細胞への分化が抑制されることを発見。また、PI3Kを破壊した未分化のT細胞をTh17細胞に分化させる実験も行い、同様に抑制されることを確認した。
次に、PI3Kとともに機能するたんぱく質に注目して研究を実施した。PI3Kの活性化はAktと呼ばれるたんぱく質リン酸化酵素の活性化を促し、AktはmTORC1というたんぱく質複合体を活性化することが知られているが、このAktの活性を人為的に増強させたところ、Th17細胞の分化が促進されたという。また、mTORC1阻害剤(ラパマイシン)で処理した場合や、mTORC1の機能を破壊したT細胞でも、Th17細胞への分化が抑制されることを確認した。

|
|
図1 PI3K-Akt-mTORC1経路はTh17細胞の分化を促進する
A:未分化なT細胞を、クラスIA PI3Kを破壊した(p85α-/-)マウスあるいは対照(p85α+/-)マウスから取り出し、Th17細胞に分化させた。Th17細胞の分化を示すIL-17A産生量は、p85α-/-細胞では対照(p85α+/-)に比べて低く抑えられている。
B:未分化なT細胞を野生型マウスから取り出し、クラスIA PI3K阻害剤であるIC87114処理(PBSとあるのは阻害剤を入れていないことを示す)を加えて、Th17細胞に分化させた。IL-17A産生量は、阻害剤処理によって低く抑えられている。
C:未分化なT細胞を野生型マウスから取り出し、mTORC1阻害剤であるラパマイシン処理(PBSとあるのは阻害剤を入れていないことを示す)を加えて、Th1あるいはTh17細胞に分化させた。Th1細胞の分化を示すIFNγ産生量に違いはないが、Th17細胞の分化を示すIL-17A産生量は、阻害剤処理によって低く抑えられている
|
さらに、実際に自己免疫性の大腸炎を発症するモデルマウスにラパマイシンを投与してみたところ、Th17細胞の分化誘導が抑制されるとともに、その症状が軽度になることが判明したという。

|
|
図2 ラパマイシンの投与によって大腸炎が軽減する
A:未分化なT細胞をT、B細胞欠損(Rag2-/-)マウスに移植すると、自己免疫性の大腸炎を発症して体重減少が観察されるが、ラパマイシンを連日投与することによって体重減少が見られなくなる(PBSは阻害剤を入れていないことを示す)
B:未分化なT細胞移植6週間後に、マウスの腸間膜リンパ節あるいは脾臓に存在するTh1(IFNγ産生)細胞およびTh17(Il-17A産生)細胞の割合を調べた。対照(赤四角)(PBSとあるのは阻害剤を入れていないことを示す)に比べて、ラパマイシンの投与(青四角)によってTh17細胞の割合が減少した。
C:未分化なT細胞移植6週間後の大腸の組織像。対照(PBSとあるのは阻害剤を入れていないことを示す)では腸炎を発症して大腸の肥厚が見られるが、ラパマイシンの投与によって炎症が抑えられ、肥厚も見られない
|
これにより、PI3K-Akt-mTORC1経路を抑制することでTh17細胞の分化が抑制され、自己免疫性の炎症が抑制できることが判明した。
また、このPI3K-Akt-mTORC1経路によって、どのようにTh17細胞の誘導が引き起こされるかについて、その仕組みも調べた結果、この経路はTh17細胞の増殖を抑える「Gfi-1」と呼ばれる転写因子を抑制することが判明した。

|
|
図3 PI3K-Akt-mTORC1経路の活性化はGfi-1の抑制を介してTh17細胞の分化を促進する
A:Th17細胞におけるGfi-1転写因子の発現はPI3K-Akt-mTORC1経路の阻害剤(IC87114あるいはラパマイシン)処理によって増強される。
B:mTORC1の下流で働くことが知られるS6K1転写因子の強制発現(S6K1-CA)により、未分化なT細胞をTh17細胞に分化させると、対照に比べてEGR2およびEGR3分子の発現が増強される。
C:未分化なT細胞でEGR2遺伝子を強制発現させることでTh17細胞に分化させ、Gfi-1、RORγ、IL-17Aの各遺伝子の発現量を調べた結果。EGR2遺伝子を強制発現させた細胞(Egr2)は、RORγ遺伝子の発現量には影響がないものの、対照に比べてGfi-1遺伝子の発現が抑制されるとともに、IL-17A遺伝子の発現が増強され、結果としてTh17細胞の分化が促進された
|
加えて、Th17細胞の誘導に必須であることが知られていた転写因子「RORγ」を核に移動させ機能させるためには、PI3K-Akt-mTORC1経路が必要であることも明らかとなった。

|
|
図4 Th17Th17細胞の分化においてPI3K-Akt-mTORC1経路を阻害するとRORγの核移行が阻害される。
A:蛍光抗体法を用いたRORγ分子の細胞内分布。RORγはTh17細胞を特異的に発現して24時間以内に核に移行するが(青三角)、IC87114あるいはラパマイシンなどの阻害剤を加えておくと、RORγが細胞質にとどまっている様子が見られるようになる(赤三角)。
B:ウェスタンブロット法による細胞質内および核内に存在するRORγたんぱく質の検出。Th17細胞に発現するRORγは細胞質および核のどちらでも検出されるが、IC87114あるいはラパマイシンなどの阻害剤を加えると核で検出されるRORγたんぱく質の量が減少する。
C:RORγを発現する細胞の割合は、IC87114あるいはラパマイシンなどの阻害剤を加えても変わらない。
D:IC87114あるいはラパマイシンなどの阻害剤を加えることで、核内に存在するRORγの割合(青)が減少し、その代わりに細胞質にとどまっているRORγの割合(赤)が増加する
|
これらの結果により、PI3K-Akt-mTORC1経路がTh17細胞の分化を促進する仕組みが解明され、実際に経路阻害剤の投与により自己免疫疾患のモデルマウスの症状が改善されることが実証された。しかし、このPI3K-Akt-mTORC1経路はほかのさまざまな細胞機能にも関わっているため、この経路を阻害して自己免疫疾患の症状を改善しようとする場合は、副作用を避ける工夫が必要となると研究グループでは説明している。

|
|
図5 今回の研究成果。未分化のT細胞が、抗原刺激とTh17細胞分化に必要なサイトカインの刺激を受け取ると、PI3K-Akt-mTORC1経路が活性化される。活性化されたmTROC1はS6K1とS6K2の発現を介して2通りの経路でTh17細胞の分化を促進する。すなわち、S6K1の発現を介してEGR2転写因子の発現を上昇させ、Th17細胞分化を阻害するGfi-1転写因子の発現を抑えることで、結果的にTh17細胞の分化を誘導する一方、S6K2は核移行シグナルとしてTh17細胞の分化に必須のRORγと結合し、核内に移行してTh17細胞の分化を促進する
|
また、Th17細胞への分化はPI3K-Akt-mTORC1経路によって、少なくとも2通りに制御されていることが明らかとなった。特にRORγを核に移動させることによってTh17細胞の分化を促進しているという発見は、ほかの細胞には影響を与えずにTh17細胞の分化を抑制できる免疫抑制剤の開発に貢献することが期待されると研究グループではコメントしている。