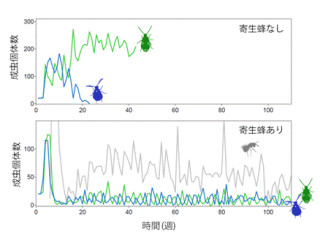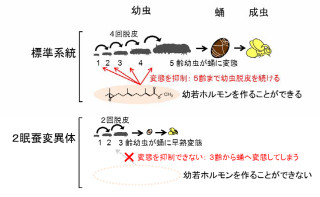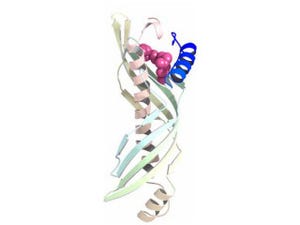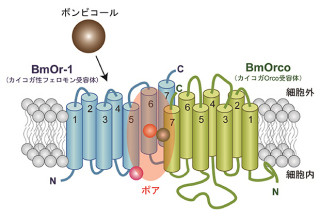東京大学、玉川大学(玉大)、金沢大学(金大)の3者は3月15日、神経興奮のマーカー遺伝子を用いて、攻撃行動の「熱殺蜂球」を形成している「ニホンミツバチ」の脳では、昆虫の高次中枢の「キノコ体」の一部の神経細胞が興奮していることを見出したと発表した。
成果は、東大大学院理学系研究科生物科学専攻の久保健雄教授、同國枝武和助教、同博士課程1年の宇賀神篤氏、玉大学学術研究所ミツバチ科学研究センターの故・吉田忠晴教授(当時)、玉大大学院農学研究科応用動物昆虫科学研究分野の小野正人教授、金沢大学理工研究域自然システム学系の木矢剛智特任助教らの共同研究グループによるもの。詳細な研究内容は、米オンライン科学誌「PLoS ONE」に日本時間3月15日付けで掲載された。
ミツバチというと一般的には「刺す」虫というイメージを持つ方が多いはずだ。しかしながら、小野教授らは1995年に、日本在来種のミツバチであるニホンミツバチは、天敵である「オオスズメバチ」が巣内に侵入すると、数100匹の働き蜂がスズメバチに一斉に殺到し「蜂球(ほうきゅう)」と呼ばれる集団を形成し、刺すのではなく、飛翔筋を震わせ、発熱してオオスズメバチを「蒸し殺す」ことを発見した。
この時、蜂球内の温度は46~47℃という高温になるが、オオスズメバチの上限致死温度(約45℃)がニホンミツバチ(約49℃)に比べて若干低いため、オオスズメバチは蒸し殺されてしまうのである。
この熱殺蜂球形成は、西欧原産の「セイヨウミツバチ」では見られないことから、東アジアに棲息するオオスズメバチの存在という「淘汰圧」のもとに、ニホンミツバチが独自に獲得した防衛行動と考えられてきた。
なお、生物個体や形質がある環境要因のもとで世代を経るごとに、その数や集団内での割合が変化することを淘汰といい、その要因となる環境要因のことを淘汰圧という。
この熱殺蜂球形成が、脳のどのような活動により引き起こされるのかという疑問を解くため、研究グループは「熱殺蜂球形成行動中にニホンミツバチの脳内で活動(神経興奮)している領域」を同定することを目指して研究を開始した。
木矢特任助教らは、2007年にセイヨウミツバチから神経興奮のマーカー遺伝子として「初期応答遺伝子(神経興奮が起きてから一定時間後をピークとしてその神経細胞に発現誘導される)」を同定し、「kakusei」と命名した(麻酔から「覚醒」させたミツバチの脳から発見されたことに由来)。
今回、研究グループはニホンミツバチのkakusei(Acks)を同定し、これを神経興奮のマーカー遺伝子として利用することで、蜂球を形成しているニホンミツバチの脳の興奮領域を探すことにしたのである。
Acksは神経興奮が起きてから30~60分後に発現がピークに達するという特徴を持つ。そこで、針金の先に固定した囮のオオスズメバチをニホンミツバチの巣内に挿入し、その周りに人為的に熱殺蜂球を形成させ(画像1~4)させた。
そして、蜂球形成直後・30分後・60分後に蜂球の表面からニホンミツバチの働き蜂を少しずつ採集して、Acksが脳のどの領域で発現しているかを「in situハイブリダイゼーション(ISH)法」(組織切片の上で、標識した相補的RNAとのハイブリダイゼーションを起こさせることで、生体内で発現しているRNAの発現領域を同定する方法)により調べたのである。
その結果、蜂球形成直後に比べ、30分後と60分後の働き蜂の脳では、高次中枢のキノコ体、とりわけ「クラスIIケニヨン細胞」でAcksを発現している細胞が多数検出された(画像5・6)。このことから、これらの神経細胞が蜂球形成直後から約30分後にかけて活動したことがわかったのである。
なお、キノコ体とは昆虫の高次中枢で、ミツバチなど一部の昆虫では特に大きく発達しており、視覚・嗅覚・味覚といったさまざまな感覚入力を受けると考えられている。
そしてケニヨン細胞は、キノコ体を構成する神経細胞(ニューロン)のことだ。ミツバチのケニヨン細胞は、細胞体が傘部の内側に集合するクラスIと、外側表面に集合するクラスIIに大別される。それぞれの役割にはまだ不明な点が多い。

|

|
|
画像5。ニホンミツバチ右脳半球の模式図。蜂球形成30分後と60分後に採集した働き蜂で検出されたAcks発現細胞を、黒点で模式的に示している |
画像6。AとBはそれぞれ画像6の赤枠内に対応する部分のISH法の結果。蜂球形成直後(左列)に比べ、30分後(中列)と60分後(右列)では多数のAcksの発現を示す黒いシグナルが観察された。特に下段のクラスIIケニヨン細胞で密度が高い。スケールバー:100μm |
続いて、蜂球形成の神経興奮をもたらした原因を探るために、蜂球内でニホンミツバチの働き蜂がさらされる状況として、46℃という高温と、ミツバチが外敵の存在を仲間に伝えるために分泌する「警報フェロモン」の成分である「酢酸イソアミル」(熱殺蜂球からも放出される)への暴露をそれぞれ実験室(虫かご)内で再現し、脳でのAcksの発現が調べられた。
その結果、ニホンミツバチの働き蜂を蜂球の内側と同じ46℃という高温にさらしたところ、熱殺蜂球形成時とよく似た脳の領域でAcksの発現が検出されたのである。
一方で、酢酸イソアミルにさらした際には、こうしたAcksの発現は検出されなかった。このことは、熱殺蜂球を形成しているニホンミツバチの脳では、高次中枢で高温情報が処理されていることを示唆しているというわけだ。
さらにミツバチでは触角で高温が感知されるが、触角を切除したニホンミツバチの働き蜂を46℃という高温にさらした場合には、活動するクラスIIケニヨン細胞の数が約半分に減少することを確認。このことから、高温情報は触角とそれ以外の経路を経て高次中枢であるキノコ体へと伝達されると考えられたのである。
今回の研究では、世界で初めて、熱殺蜂球を形成したニホンミツバチの脳で神経興奮が起きている領野を同定することに成功した。ただし、キノコ体において高温情報はどのように「処理」されているのかはまだ明確ではない。
熱殺蜂球形成では蜂球内温度が一定(46~47℃)に保たれることが極めて重要なことから、1つの可能性として、今回検出された神経興奮が蜂球内の温度モニタリングに関わるというものがある。蜂球内の温度が46℃に近くなるとキノコ体が興奮し、飛翔筋の活動を抑えることで蜂球内の温度を一定に保つ仕組みがあるのかも知れないという。
キノコ体が高温情報処理に関わるという知見はこれが初めてであり、昆虫脳の高次中枢の働きを調べる上で格好の研究対象になると思われると、研究グループはコメントしている。
そして、今後、どの神経回路を介して高温情報がキノコ体に伝達され、そこでどのような「処理」がなされ、どの神経回路を介して飛翔筋の運動制御がされて、「サーモスタット」のような温度調節が実行されるのか、解明される必要があるとした。
さらに、高温条件下での脳の神経活動を、熱殺蜂球形成行動をほとんど取らないセイヨウミツバチと比較することで、進化の過程でニホンミツバチが独自に獲得した、熱殺蜂球形成行動を可能にする脳の仕組みがわかるとも期待され、進化生物学的観点からもさらに興味深い課題であると、研究グループは述べている。