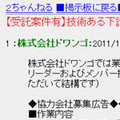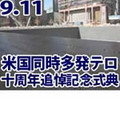ニコニコ研究会は12月6日、東京都港区のニコファーレにて第1回ニコニコ学会βシンポジウムを開催した。発起人がニコニコ研究会の設立意図や活動内容を説明した後、業界著名人による対談や、大学教授らによる研究発表などが催された。

|
|
開会の挨拶を行う産業技術総合研究所の江渡浩一郎氏 |
ニコニコ学会開催の意図
シンポジウムを主催したニコニコ研究会は、11月21日に設立されたばかりの研究団体。早稲田大学教授 兼 東京大学名誉教授の竹内郁雄氏が技術顧問を務め、著名大学の教授/准教授、国立研究機関の研究員ら21人が発起人に名を連ねている。
ニコニコ学会βシンポジウムに登壇した、産業技術総合研究所の江渡浩一郎氏は、研究会設立の意図について「現在はユーザー参加型コンテンツ全盛の時代で、創造的な活動がネット上で広まっている。研究においてもこれを取り入れて、インタラクションが進むような世界、未来像を作りたい」と説明した。
さらに江渡氏は、ニコニコ学会βの目的についても言及。「ニコニコ学会βはあなたの学会です」「ニコニコ学会βはオンラインの学会です」「ニコニコ学会βはユーザー参加型の価値を追及します」という3つの理念を紹介し、だれでも発表したいもの発表できる場であり、オフラインの良さとオンラインの良さを取り入れた学会であり、さらにユーザー参加型学会というスタイルをとりながら"ユーザー参加型"自体の研究も進めていくことを明かした。
特に3つ目のユーザー参加型に関しては、「最前線の研究者とネット上の創作活動者でシナジーが起こせるのではないか」とコメント。自身が学生時代に「ジョイメカファイト」というゲームソフトを、任天堂のトップクリエイターであった宮本茂氏らに教わりながら開発した経験を紹介したうえで、「最先端の現場を間近に感じながら開発を進められたことは、非常に良い経験になった」と述べ、そういった経験ができる"場"を提供するべく、ニコニコ学会βの開催に至ったことを説明した。
初音ミクがニコ動に登場した背景
江渡氏による挨拶の後は、ドワンゴ会長の川上量生氏とチームラボ社長の猪子寿之氏による講演『作るを作る』や、ニコニコ動画の開発総指揮を務めたドワンゴの戀塚昭彦氏と、初音ミクを生みだしたクリプトン・フューチャー・メディア社長の伊藤博之らによる講演『作るアーキテクチャを作る』、大学教授らによる研究100連発など、さまざまなセッションが行われた。
川上氏と猪子氏の講演では、「ゲーム→着メロ→ニコニコ動画」と続いてきたドワンゴのパラダイムシフトに同社の社員のほとんどが関わっていなかったこと、ニコニコ動画はオープン当時に全盛だったカッコイイ雰囲気のサービスとは真逆の方向性で進もうと考えていたことなど、さまざまな裏話を披露。また、川上氏は、「国によって文化が異なるが、どの国においても若い世代ほど新しいものへの抵抗が少なく、日本色の強いサービスやコンテンツも受け入れられる傾向にある」といった見解を示したうえで、「ニコニコ動画のオープン当初は、コメント表示機能が個人的にどうしても許せなかったが、1ヵ月経つと受け入れられるようになった。ということは、海外でニコニコ動画のようなサービスを作ろうという人はそういないだろうし、受け入れてくれる人たちもいるだろうから、海外でも通用するのではないかと思った」といったエピソードも紹介した。

|
|
左からドワンゴ会長の川上量生氏、チームラボ社長の猪子寿之氏、産業技術総合研究所の江渡浩一郎氏 |
また、戀塚氏と伊藤氏の講演では、初音ミクがニコニコ動画に登場した背景について言及。「クリプトン・フューチャー・メディアが生み出した初代ボーカロイド『MEIKO』がニコニコ動画で取り上げられて再度売上を伸ばしていたことから、ニコニコ動画に注目した」と明かしたうえで、「そういう動画を作るユーザーがいることがわかったが、モチーフがなければ作りづらいだろうという思い、初音ミクのパッケージのイラストをダウンロードできるようにしたことが最初の一歩。ユーザーの作り出すものが面白くて、われわれも楽しんでいた。とにかく想定外の連続だった」と当時を振り返った。

|
|
左から日本技芸の濱野智史氏、ドワンゴの戀塚昭彦氏、クリプトン・フューチャー・メディアの伊藤博之氏 |
次回のニコニコ学会は、ニコニコ研究集会というかたちで、ユーザーが発表する場として開催される予定。来年4月の開催が検討されている。