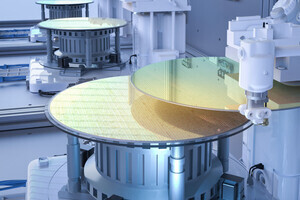2010年10月5日から9日までの5日間にわたり、千葉県幕張メッセにて、IT・エレクトロニクスの総合展「CEATEC JAPAN 2010」が開催されている。今年のテーマは「Digital Harmony - もっと快適に、もっとエコに」で、技術の進化と快適性の両立を実現するデジタル技術、製品、サービス、コンテンツの調和が奏でる次の地球、社会、ビジネス、暮らしの活力を世界に向けて発信することを目指したという。今回は、同展示会の「電子部品・デバイス&装置ステージ」を中心に、目に付いた技術などを紹介したい。
SiC技術など最新技術をアピール
大手半導体ベンダとしては国内外通して唯一の参加となったローム(子会社のOKIセミコンダクタも参加)のブームではLEDなどの展示のほか、9月4日に発表したSiCインバータモジュールの実機を用いたデモなどが行われている。
同SiCモジュールは高耐熱部材を用いることで225℃動作を実現したほか、放熱効果を最大限に発揮するためにワイヤレス構造を採用している。また、トレンチMOSFETの採用によりDMOSに比べてオン抵抗を1/3に低減したほか、SiのIGBTモジュールと比べ、体積は約1/10に小型化することに成功している。
インホイールモータなどへの展開を目指しているが、実用化に向けては信頼性評価などの過程が残されており、今しばらくは時間がかかる見込みとのこと。
また、同社ブースではSiCのほか、開発品としてフレキシブル有機ELデバイスや有機ELフラッシュ、CIGSイメージセンサなども展示されている。
フレキシブル有機ELデバイスは、従来有機ELに比べて約1/6の薄さを実現したほか、重量も同1/8程度となる0.05g/cm2を実現しており、半径25mmの折り曲げが可能であり、デザイン照明や機内照明などへの応用が可能とのこと。
一方の有機ELフラッシュは瞬間輝度10万cd/m2を実現しており、キセノンランプ方式で必用な約400Vの高圧回路が不要となるほか、ランプ方式で必要な反射鏡やレンズも不要となるため、コストの削減が可能。また、発光輝度を調整することで、フラッシュではなく、ライトとして使用することも可能となっている。
CIGSイメージセンサは、太陽光発電でも用いられているCIGSの薄膜フォトダイオード(PD)を半導体デバイス上に積層し、最表面に構成することで高い開口率を実現した撮像素子。SiのPDより広い1200nmまでの帯域感度を実現しており、これを活用することで近赤外カメラなどへの応用が可能となる。
デモでは、近赤外光を用いた血管透視ができるというシステムを設置、手のひらや甲をかざすと、血管がくっきりと見て取ることができるというものをやっている。同社としては、ある程度中身が見えることから検査装置などの需要があるとしており、まずはVGAモノクロイメージセンサ(1/3.0型、約30万画素)を2011年末の量産目指して開発していくとしている。