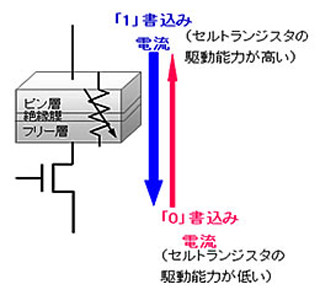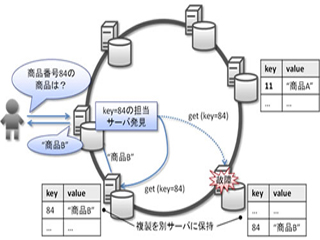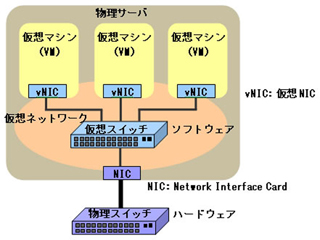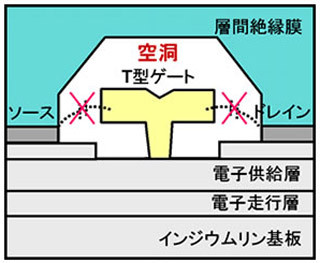富士通研究所と名古屋大学は8月2日、食中毒の原因となる毒素たんぱく質を従来検出方法に比べ100倍程度高速化することが可能となる技術を開発したことを発表した。
同技術は、同社と独ミュンヘン工科大学ウォルターショトキー研究所が共同開発したDNAを素材に用いた信号変換器に、毒素タンパク質を捉える人工抗体(DNAアプタマー)を組み合わせ、毒素たんぱく質の有無を検出するセンサを作製したことで可能となった。
毒素たんぱく質は、ヘビやサソリの毒素、ボツリヌス毒素、黄色ブドウ球菌腸管毒素(エンテロトキシン)などさまざまなものがあり、その毒性が強いと人を死に至らしめることがある。今回の実験では、エンテロトキシンの高速検出を目指した技術が開発された。

|
|
富士通研究所の安藝理彦氏 |
こうした毒素たんぱく質の検出について、富士通研究所の安藝理彦氏は、「毒素たんぱく質の中でも特に食中毒を引き起こすものは、もし含まれていれば、それを販売すれば大変なことになる。結果として迅速かつ精度良く検出しなければならないが、従来の検出技術では濃縮時間などを含めれば一般的なもので24~48時間程度かかることとなり、かつ微量な毒素たんぱく質の検出が困難などの課題もあった」と、これまでの検出方法においては、微量の(それでも食中毒を引き起こす可能性のある)毒素たんぱく質の検出は難しかったと説明する。
また、名古屋大学の山田景子助教は、「エンテロトキシンは2000年に大きな食中毒事件を引き起こした原因となったものだが、微量なため検出が難しく、法律上の検査対象となっていない。今回我々が開発したような技術が実用的なものとなれば、そうした微量のものも検出できるようになり、より安全な食というものを提供できるようになる」とその意義を説明する。

|
|
名古屋大学の山田景子助教 |
具体的にはDNAの骨格構造にアミノ酸の修飾側鎖を組み合わせ化学合成を行うことで人工抗体のライブラリを構築。そのライブラリの数は1014という数を現在揃えているという。この内、今回は名古屋大学と共同でエンテロトキシンと人工抗体の結合によるどこにどんなアミノ酸が入っているのかなどの構造情報を解析し、化学合成を行い、センサに活用した。
従来の動物性たんぱく質による抗体は、動物の免疫システムを活用するもので、コストが高かったり、生物が元のため、品質のバラつきが大きかったりといった課題があったほか、生物由来のため、毒性も高い毒素たんぱく質などは不向きであるといった問題もあった。
DNA+アミノ酸側鎖による人工抗体は、試験管内で化学合成による生成のため、品質を一定に保つことが可能なほか、毒素たんぱく質にも対応が可能となる。
この人工抗体のDNA部分と信号変換器のDNAを結合させることでバイオセンサを構築、たんぱく質を効率よく人工抗体がとらえられる流量や速さを名古屋大と共同で最適化を実施、これによりエンテロトキシンの有無はほぼ10分で完全に判明。「あるかないかだけであれば、30~60秒程度の観測点で変化が生じることから、ある程度、サンプル中に存在していると判断することが可能となる」(安藝氏)という。
同技術の実用化については、「牛乳といった食品そのものから何もしないで有無を確認するための技術開発が必要」(同)なほか、「エンテロトキシンにも複数種類があり、それぞれで症状が重かったり軽かったりと変化するため、法律上ではそうした種類の特定まで求められる。今回の技術はあくまでエンテロトキシンという存在そのものすべてに反応してしまうため、そうした細かく特定する技術を開発する必要がある」(同)とし、将来的に実用化のめどが立てば、技術アライアンスでデバイス(バイオセンサ)を計測企業などに提供していきたいとした。しかし、同技術開発は2009年度で一旦終了しており、興味があり、研究継続に協力してくれるパートナーと今後の実用化に向けた開発を進めていきたいとしている。