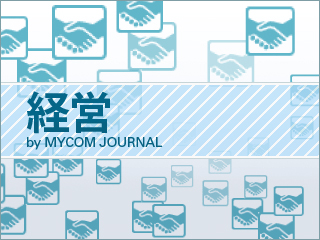東芝は5月7日、2009年度(2009年4月~2010年3月)の決算概要を発表した。これによると売上高は前年度比4.1%減の6兆3,815億9,900万円、営業損益は前年度の2,501億8,600万円の損失から1,171億9,100万円の利益へと益転を果たした。また、継続事業税引前純損益は前年度の2,792億5,200万円の損失から249億6,200万円の利益へと益転したものの、株主帰属純損益は前年度の3,435億5,900万円の損失から約3,200億円改善し197億4,300億円の損失となった。
セグメント別の売り上げは、デジタルプロダクツが前年度比%減の2兆3,636億円、電子デバイスが同%減の1兆3,091億円、社会インフラが同%減の2兆3,029億円、家庭電器が同%減の5,798億円、その他が同%減の3,158億円となった。
また、営業損益はデジタルプロダクツが前年度の142億円の損失から133億円の利益に改善したほか、電子デバイスが前年度3,232億円の損失から242億円の損失へと赤字幅を縮小、社会インフラが同20.4%増の1,353億円、家庭電器が前年度271億円の損失から54億円の損失へと赤字幅を縮小、その他が前年度5億円から43億円の損失へと赤字転落した。

|
|
東芝 代表取締役副社長の村岡富美雄氏 |
会見した同社代表取締役副社長の村岡富美雄氏は、「2009年度の売り上げは下期に前年度比8%の増収を達成したものの上期の同15%の減収の影響を受けた。結果的に全セグメントで減収となったが、営業損益は期初目標の3,000億円を上回る4,300億円の固定費削減効果などもあり全セグメントで前年度比で改善が進んだ。特に半導体が前年度の2799億円の損失から23億円の黒字と益転を果たしたほか、社会インフラが高い水準を維持したことが大きい」と説明する。また、197億円の純損失となったことに関しては、「法人税などの税金が297億円、この内100億円程度が法人税でその他が地方税などとなっている。この地方税などについては繰延を行っていないためこのような結果となった」としている。
事業別に見た場合の営業損益の各種要因としては、先述の半導体が改善したことによる事業全体の黒字化に加え、PCを除いたデジタルプロダクツの業績改善で508億円の利益確保などがあったものの、PCが出荷台数1,500万台を達成も欧州を中心とした売価ダウンや低価格化などの影響もあり減収となり、原材料価格の上昇などの影響もあり、営業損益も年度第3四半期までは6億円の黒字だったものが、第4四半期で94億円の損失となり、PC全体としても88億円の損失を計上したこと結果、全体としては1,172億円の営業利益となった。
大きな利益改善が進んだ半導体だが、その内訳はNAND型フラッシュメモリの価格安定と需要増による増収がシステムLSIの減収を補う形で黒字化を達成したという。具体的な売上高は、ディスクリートが前年度比1.3%増の1,961億円、システムLSIが同15.0%減の3,464億円、メモリが同25.0%増の5,275億円で合計は同4.6%増の1兆7,000億円となり、営業損益も年度第2四半期より黒字転換を達成、同第4四半期では3事業すべてが黒字化し286億円の利益となった。一方の液晶事業は携帯機器、PC、車載機器などの需要減が響き前年度ほぼ横ばいの361億円の損失となった、
なお、2010年度の通期業績については、売上高が前年度比6.7%増の7兆円、営業利益が同113.3%増の2,500億円、税引前純損益が同6倍の1,500億円、純損駅が700億円の利益との見通しをしている。セグメント別では、全セグメントでの増収増益を見込んでおり、中でも半導体は1,000億円の利益を見込むとする。この内訳としては、「上期が400億円で、100%がメモリ。下期が600億円でその内500億円がメモリ」(村岡氏)とフラッシュメモリが主となっていることを強調する。そのフラッシュメモリだが、稼働率は現状100%となっており、2010年度後半には2Xnmプロセス品の生産を開始する予定としているほか、Fab5の建設にも着手、2011年夏頃の稼働を目指すとしている。