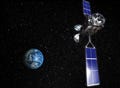宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、Googleが本日からサービスを開始した「Moon in Google Earth」に、月周回衛星「かぐや」のデータを提供したことを明らかにした。
かぐやは、月の起源と進化を解明する目的で、2007年9月14日、H-IIAロケットによって打ち上げられた。そして、2009年6月11日に運用を終え、月面に制御落下した。
JAXAがGoogleに提供したのは、レーザ高度計(LALT)によって得られた月の全球形状および南極や北極にあたる月の極域地形図。これによりGoogleでは、これまで平面だけたった月の地形を、3Dで立体的に表現することができるようになった。
今回の「Moon in Google Earth」プロジェクトは、1年ほど前、Googleの20%ルールによって生まれたという。20%ルールとは、勤務時間の20%を自分の好きなことに利用して良いというGoogleの社内ルール。今回のプロジェクトは、ある社員のアポロ計画の40周年を記念して何かをやりたいう発案のもと、賛同者と募り開始されたという
今回のかぐやのデータの提供にあたって、JAXAはかぐやデータの広報、普及、啓発を目的に、今年の7月Googleとコンテンツライセンス契約を締結。これにより、3次元の月の全球データ閲覧が可能になったほか、地形カメラの特定領域画像などが公開された。
そのほか、かぐやのハイビジョンカメラの映像は、これまでYouTubeのJAXAチャンネルで公開されてきたが、今後は「Moon in Google Earth」とも連携される。そして、現在は1/16度のデータ提供に留まっているが、今年の11月には1/64度の、より解像度の高いデータも提供されるという。
JAXAでは、今後も宇宙開発、地球環境保全において、Googleの協力関係を続けていくほか、Google 製品開発管理担当副社長のジョン・ハンキ氏も、今後はGoogle Earthで森林や砂漠化をモニターできる機能を搭載していきたいと述べた。