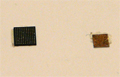そこで、同社ではデータセンターの電力容量問題に抜本的な取り組みを開始したという。まずは、5年後の環境として「サーバは性能向上による消費電力の増加や小型化の傾向にある。しかしその一方で第一データセンターには電力容量の制限があり、これらを勘案すると、概ね5年後に使用できる床面積は現在の2/3へ減少する」と予測。
こうした状況を踏まえ、同社では「4年後までに第一データセンターのサーバを半減させ、その上でその後のデータセンターをゼロから構想する」と改善目標を策定した。さらに、問題解決の方向性として(1)企業の競争力を落とさずに、データセンターでの消費電力を削減する、(2)電力容量不足を引き起こす原因を除去して抜本的な対策を施す、という2点を掲げた。
初めに行われたのが、データセンターの電力容量不足の原因分析だった。その結果、同社が導いた主要因の第1点は「x86系のサーバを適用業務ごとに導入している」。これに対し、あらかじめ用意しているサーバを新規の適用業務で利用したり、今後は適用業務個別にサーバを導入したりと、サーバの共同利用の徹底を図ることで対処したという。
関口氏によると、サーバの共同利用はサーバを層化することで実現したという。「プログラムとデータベースを分離して配置した。アプリケーション層にはサーバを複数配備し、各々のサーバに同じプログラムを配置することで、サーバをスケールアウトで拡張できるようにした。データベース層では、サーバを本場用と待機用を配備し、すべてのデータを1つのデータべースに配置し、サーバのスケールアップで拡張できるようにした」
また、2つめの要因として分析された「類似用途のサーバの導入」については、仮想化ソフトによるサーバの統合で対処したという。仮想化ソフトを採用した理由について、関口氏は「x86で使えるOSであれば種類やバージョンを問わず、移行ツールで実際のマシンから仮想マシンへ移行できる。さらに、サーバの導入費用や保守費用の増加抑制や、システム開発後のテスト用サーバにもなり、短期間でサーバの準備ができる」と説明。さらに、「実際、採用した翌年には、導入費用が1,350万円 保守費用140万円の削減につながった」と明かし、仮想化ソフトの導入効果を強調した。