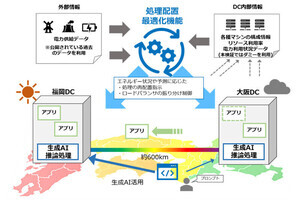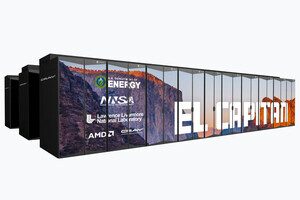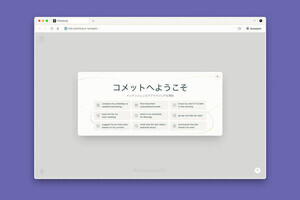慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)の研究成果を発表する産学連携イベント「慶應義塾大学SFC Open Research Forum 2008(ORF2008)」が21日から2日間、東京都港区の六本木アカデミーヒルズ40で開催されている。13回目となる今回のテーマは「clash of eXtremes」。前夜祭となった20日のオープニングセッションでは、「平均」でない「極限(extremes)」の中から新しい知を見出し、破壊的な創造を生む方法論について、3人の教授が語りあった。
新たに「スーツケース・デモ」などを実施
今回のORFには、SFCのほか、慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所(G-SEC)、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(KMD)、慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構(DMC機構)も参加。
新しい試みとして、学生が、日々の研究活動の成果をスーツケースにコンパクトにまとめて会場を巡回しながら、呼び止められれば中身を披露する「スーツケース・デモ」を実施。
また、全てのメインセッションにおいて、セッションが終わった後あらためて30分時間をとり、来場者とパネリストが語り合う時間を設けているのも特徴となっている。
前夜祭となった20日のオープニングセッションでは、マイクロソフトの社長、会長を務めたKMD教授の古川享氏、NTTドコモ出身で慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授の夏野剛氏、SFC研究所所長で総合政策学部教授の國領二郎氏の3人を中心に、他の教授らも飛び入り参加しながら、ORF2008の狙いなどについて語り合った。
セッションの司会を務めた國領氏は最初に、今回のORFのテーマとなっている「clash of eXtremes」について説明。「eXtremesという言葉は昨年から使い出したが、学問的に考えると平均値を研究するのは駄目で、極限値を研究することにこそ新しい発見があるという意味を込めた。また、『先導』『先端』という意味もあり、常に先導的にならなければという狙いを込めている」と述べた。
昨年まではなかったオープニングセッションの開催については、「ちょっととがった事や、変な事をやっている3人があえてここに集まり、どんなことができるか、そんな意味を込めて企画した」と話した。
宝の山の活用が必要、ORFで何らかのきっかけを
夏野氏はeXtremesという言葉について、「この20年、ITの世界はものすごく速いスピードで変化してきており、企業の経営においても、極限値を考えざるを得ない」と述べ、「僕もeXtremesだったからやめさせられたのかもしれない」とNTTドコモを辞めた経緯を話すと、会場からは大きな笑いが起こった(関連記事)。
古川氏は慶應義塾大学の教授になったことについて、「個人として貢献するだけでなく、突出した素晴らしい技術を持つ研究者が、外に向けてどうやってコミュニケーションをしていいか分からない際、社会に向けてつないでいく役割を果たしたいと思ったから」と話した。
國領氏は二人に、「大学の先生になった感想はどうですか? 」と質問。
夏野氏は、「給料が安い。下手したらSFCまでの交通費で消える」と笑わせ、「とにかく講義が大変。今の学生には、過去の講演などの資料の使いまわしはきかないし、教室にパソコンを持ってきている学生はキーワードが出るとすぐググるので、変な事は言えない。昔の先生は良かった。今の先生はタフでないと無理」と再び笑わせた。
古川氏は、「SFC以外でも、すごい技術を見つけた。何とかこれを世の中にデビューさせたいと思っている。大学に入って思ったのは、とにかくマーケティングと広報が絶望的にできていなかった。営業もいないし、経営方針もどうなっているのか。例えば米国のスタンフォード大学では、知的財産の売り上げが213億円もあるが、日本は昨年トップの名古屋大学でも、1億4,000万円くらい。この100倍くらいあってもおかしくない。宝の山をどう活用するか、ORFで何らかのきっかけをつかんでほしい」と話した。
「来場する人は学生の本質を見つけてほしい」
この発言に対し國領氏は、「それでは、SFCの経営をされている常任理事の村井純さんに話を聞きたい」と、セッションを聞いていた環境情報学部教授の村井純氏に発言を促した。
村井氏は「宣伝できないところも大学のいいところ」と笑わせた後、「ORFは最初はキャンパスで開催していたので、この六本木でやるのはすごい英断だった。今回のORFはG-SEC、KMD、DMCも参加し、いろんな所の先端が集まっている。『慶應は面白い奴がいる』と言われるために頑張っており、学生にとっては面白いことができていると思うので、許していただきたい」と話すと、会場は笑いの渦に包まれた。
また、夏野氏は現在の学生について、「教室の一番前に座っていた女子学生があまりにも若いので聞くと『1990年に生まれた』と言い、びっくりした。彼女の世代は、携帯、PCは当たり前で水のように使っている。この会場にいる人達は、存在そのものがeXtremesになりつつある」。
「課長が同じ会社で社長になるという漫画もあるが、これも若い世代にとってはeXtremes。そうした意味では、全てがeXtremesになりつつあるわけで、そういうもんだと思ってやって楽しみながらやっていきたい」と述べた。
古川氏は、「ORFでブースの前に立っている学生達は、スーツを着るのも初めてという学生も多い。彼らはすごく緊張していると思うので、来場する人達はぜひ彼らの内側、本質を見つけてあげてほしい」と呼びかけた。
会場には多くのブースで学生らが研究成果を紹介しているほか、22日は、國領氏や村井氏による「ICTと地域活性化の未来を語る 次世代に"使われる"インターネットの設計」と題したメインセッションなどが行われる予定。