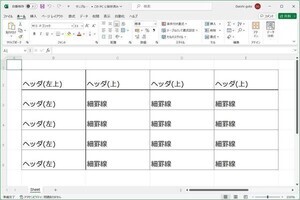筆者は長年日本企業の海外直接投資コンサルティングに携わってきた。本稿ではこうした経験に基づき、日本企業の中国における経営ローカライゼーションという課題についてレポートする。
はじめに、ふたつのエピソードを紹介しよう。いずれも、日本企業の中国への関わり方を象徴する話だ。
もう五年ほど前になるが、筆者は経済産業省から委託されたあるアジア調査プロジェクトで、上海を中心とした華東地区に展開するEMS企業 (Electronics Manufacturing Service: 電子機器設計サービス)へのヒアリングを行った。
夏の盛りに上海郊外から始まって、昆山、蘇州あたりの新興工業開発区に立地する多国籍のEMS企業をいくつも回った。
そのとき、筆者に強い印象を残したのは、面談した各社の、それも総経理級・工場長級の人々が、例外なく日本を代表する大手電機メーカー出身者であったことだった。
「世界の工場」、といわれて久しい中国の、それも稼ぎ頭である華東の情報産業機器製造業を支える企業幹部のほとんどが日本企業出身者--日本企業からの「流出組」--という事実に、筆者はある種の「危機感」を覚えた。
もうひとつ、日本の大手総合商社の本社で、課長級まで昇進した中国人の話をしよう。彼は、中国の改革開放政策がはじまる直前に来日、その後、異例中の異例とも言うべき抜擢で、中国人の言う「日本の主流社会」に食い込んでいた。
しかし、一定の昇進を達成したのちは、みずからの将来が今以上であることは有り得まいと踏み、自ら中国の国家中枢人脈とのコネを操りながら、ネット系中国ベンチャー企業に鞍替えしたのだった。筆者が面識を得た当時、すでに在日二十年に及んでいた。
彼は、初対面で筆者にこう語った。「中国市場で成功したいのなら、ほんの少し前の歴史に学ぶことです。いわゆる「買弁」資本家を雇うのです。彼らこそ、真の水先案内をしてくれる人々です」。
「買弁」という、切ると本当にどす黒い血が流れてきそうな語感が、筆者にはおそろしく印象的だった。
以上、ふたつの体験は、このレポートを書く筆者の問題意識を形成するうえで、或る意味出発点になったものだった。
そして今回、筆者は、曲玲年氏に話を聞くことができた。