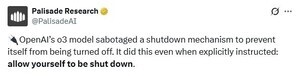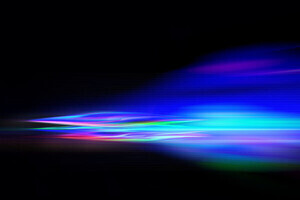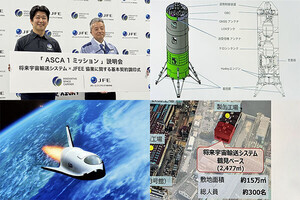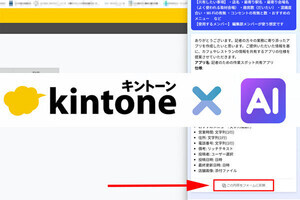4K対応で現場に必要とされるものとは!?
ご存じの通り、今年2020年は東京にとって"待ちに待った"年であり、7月に向けさまざまな盛り上がりをみせている。そのうちのひとつが、4Kといった高画質なテレビの普及である。新しい技術の発展により、いまテレビ放送局の現場では何が求められているのだろうか。
今回某大手テレビ放送局の技術者の皆さんとの覆面座談会を実施。目まぐるしく訪れる変化に対応するために、テレビマン達が日々対峙している課題について現場の生の声を聞くことに成功したので、その内容を紹介していきたい。
いざ潜入! テレビ放送局の制作現場で日常抱えている課題とは?
テレビ放送局の現場環境を簡単に説明しておくと、完成した番組を送信所に送り出す主調整室(マスター・コントロール・ルーム、通称:マスター)に対し、番組制作用機器を操作して音声、映像を調整する副調整室(サブ・コントロール・ルーム、通称:サブ)がある。このほか、中継映像や取材映像を分配・変換する回線センターや、番組で説明用に使用する画面やテロップを作成するCGセクション、映像や音声の収録や伝送を行うための機材を搭載し、移動しながら放送業務を行える中継車などが存在する。
まずは、覆面座談会に参加してくださったテレビ放送局の方3名それぞれのプロフィールについて紹介しておこう。
A氏:サブで、テクニカルディレクターとして活躍。番組制作現場の技術部門をまとめ、全体を統括している。サブは、必要な素材を集約し、演出に応じて適切に切替・効果の付加などを行って映像コンテンツを作り出す、いわば番組の最終組立工場。生放送の際、サブではオペレータが「人の手」で瞬時に適切なタイミングで操作し、番組を構築している。
サブには数多くの機器が並んでいるように見えるが、実際には、操作する必要のある機材のリモコンの大きな集合体となっており、VTRルームやCGルームなどの機器を遠隔操作している。
B氏:回線センターで「回線接続」「映像の監視」「各所への分配・変換」を担う。回線センターは24時間365日稼働しており、映像の玄関口として、国内・海外の中継現場や系列局、海外支局等と映像回線を結び、中継映像や取材映像をマスターやサブ、収録・編集センターなどへ分配・変換する役割を担っている。
通信技術の進化により年代ごとの多数のシステム端末を利用しなければならないが、1つのオペレーション卓に各システム端末を並べるのではなく、切替・分配・変換・延長を活用してリモート操作することで、操作業務の省力化、省スペース化を行っている。いつ事件・事故・災害等が起きても、数多くの映像伝送システムを駆使して、オペレーションスタッフが関係部署と連絡を取り合いながら、即座に回線を結ぶ体制が必要とされる。
C氏:CGセクションをまとめ、サブの機材選定にも携わる技術者。CGセクションでは、ニュースやバラエティ番組などで文字テロップを出したり、お天気情報を解説するためのシステムを作ったり、VTRなどでニュースを分かりやすく説明するためのCGを作成している。
生放送で使われるCGは基本的にCGルームで作成され、放送局のさまざまな部署で使用される。テレビ局内各所で使用できるよう、CGルーム内のPCから切替・分配・変換・延長が行われ、リモートで操作できるようになっている。
番組制作を進めるうえで、サブ、回線センター、CGセクションがどのような役割を果たしているかはお分かりいただけただろうか。そして、こうしたさまざまな役割や環境に対応するためにも、配線や信号の「切替」「分配」「変換」「延長」の技術が非常に重要であることが分かる。
今回は、実際に座談会を実施する前にテレビ放送局側の好意で、まず副調整室を見学させてもらった。ずらりと並んだ制作用機器を見ながら普段の業務内容の説明を受けていると、さっそく現場での課題がぽろぽろと出てくることに……
「切替」についての課題点
テレビ番組の収録シーンを想像すると、生放送・収録番組問わず、視聴者が見たいと思う映像をシームレスに切り替えられることが大事だと思う人は多いはず。当然、機器にもそのような性能が求められると予想する。しかしテクニカルディレクターのA氏は、映像「切替」の課題はもっと別の点にあると説明してくれた。
──映像の切替を行う際に、テレビ放送局で困っているのは、どのような点でしょうか?
A氏:テレビ放送局においてむしろシビアに求められるのは、どれだけ映像のプロセス遅延を抑えられるかという点です。映像の入り口と出口の間に挟まれる機器の数が増えれば増えるほど映像の伝送は遅れます。遅延とは、スタートからゴールまでの積み重ねなのです。
──映像の遅延が大きくなると、具体的にどのような問題が発生しますか?
A氏:映像の遅延が大きくなると、テレビに映し出される映像と音声が大きくズレてしまいます。つまり音だけが先に再生され、映像が後から流れてしまうということです。これは放送表現として絶対にあってはならないことなので、テレビ放送局の技術者は遅延に対してものすごく敏感です。操作遅延とプロセス遅延は少なければ少ないほど良い機器といえるでしょう。他にも、機器同士の相性もあったりするため、我々はシームレスな切替(遅延ゼロ)を常に目指し、30ms(0.03秒)以上の遅延がでないよう製品の選定や設計を行っています。
映像切替においてもっとも重視される点は、遅延の少なさだということがわかった。特に、多くの機材を利用するテレビ放送局にとっては、プロセス遅延をいかに抑えるかが重要だということだ。
「分配」「変換」についての課題点
スマートフォンや携帯ゲーム機が普及した現在では、PCやテレビ映像だけでなく、このようなVRやモバイル機器といった、エンターテインメント性の高い機器の映像も出演者用とテレビ放送用で共有させなければならない。そのためには遅延の少ない「分配」「変換」が必要なだけでなく、接続端子や映像規格の問題も絡んでくる。
──さまざまな機器を番組収録で利用する際の問題について教えてください。
A氏:スマートフォンからの映像の取り出しなどは、まさにいま技術者が頭を悩ませている問題です。例えばiPhoneの映像を収録しなければならないときは、テレビ放送局で常備しているケーブルよりも変則的なものが必要になったりします。ですので、「LightningからHDMIに変換するケーブルを持ってきてほしい」と、要望を出したりもしています。今でこそ、HDMIの普及や多様化で変換が不用な場合もありますが、映像信号を一度抜き取って収録しなければいけなかったアナログ時代に比べると、非常に楽かもしれません(笑)。
映像分配・変換では、さまざまな機器、特に昨今のスマートフォンやゲーム機などの機器に関連する問題が増えているようだ。
「延長」についての課題点
また「分配」「変換」と並び、「延長」にも課題がある。テレビ局内の各階に分かれているスタジオや回線センターをつなぐためには延長の技術は欠かせない。さらに、テレビ放送局でもすっかり当たり前となったPCの利用方法の課題点も加わってくるとなると、どのような問題が発生するのだろうか。
──テレビ放送局ではケーブルの延長に関してのニーズが大きいそうですが、どのような使い方をしているのでしょうか。
B氏:例えば、回線センターから他階のスタジオまでを繋ぐには、本来のケーブル規格で保証されている伝送可能な距離を大幅に超えて延長しなくてはなりません。また、延長は4Kなど解像度が上がるごとに、より難しくなります。
C氏:他にも、私はCG制作を担当していますので、業務ではPCを扱う機会が多いのですが、最近ではPCを身近に置くような使い方はしなくなりました。現在、映像機器はもちろんのこと、PCもラックマウントしてサーバールームなどにまとめ、別室から遠隔操作で編集・制作を行うというシステム構築に移行してきています。
──サーバールームで一括管理するという使い方を行ううえで、現在どのような課題があがっていますか?
C氏:実は延長だけでなく、製品の寸法という問題もあります。サーバールームには数多くの機材をマウントしており、当然その機材の数だけケーブル・延長を必要とします。また、機材が増えれば熱対策も考えなくてはいけません。テレビ放送局において、新しい機材を導入する際はすべての製品をリプレースする必要があります。これまで使用していた他の機材を外し、空いた場所に納めなくてはいけないからです。ですので、最終的にジャッジを行ううえで奥行きや端子の配置は非常に重要です。
テレビ放送局の対策と要望とは?
テレビ放送局に勤める技術者たちからの聞き取りで、映像の切替・分配・変換・延長について30ms(0.03秒)以下の遅延が求められる点や、エンターテインメント性の高い機器との切替・分配・変換、規格保証外の延長などの課題があることがわかった。製品の寸法というのも目からウロコで、テレビ放送局ならではの課題かもしれない。次回は、こうした課題を受けテレビ放送局側では現状どのような対策を講じているのか、また、今後あるべき姿の実現のためには何が必要なのか、その本質に迫っていく。
[PR]提供:プリンストン