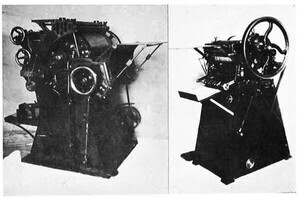フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)
怒涛の特許申請
写真植字機研究所の工場責任者は信夫だった。邦文写真植字機の実用機製作に向けて、1927年 (昭和2) 年初から取り組みはじめた信夫の機械改良の勢いはすさまじかった。なにしろ1929年 (昭和4) 1月1日には、一気に6件もの特許を出願している。
① 特許第84793号「写真装置」
出願:1929年 (昭和4) 1月1日、公告:1929年 (昭和4) 8月23日、特許:1930年 (昭和5) 1月9日
② 特許第84794号「写真装置の『シャッター』」
出願:1929年 (昭和4) 1月1日、公告:1929年 (昭和4) 8月9日、特許:1930年 (昭和5) 1月9日
③ 特許第84795号「写真装置の改良」
出願:1929年 (昭和4) 1月1日、公告:1929年 (昭和4) 8月30日、特許:1930年 (昭和5) 1月9日
④ 特許第84796号「写真装置暗箱の改良」
出願:1929年 (昭和4) 1月1日、公告:1929年 (昭和4) 8月28日、特許:1930年 (昭和5) 1月9日
⑤ 特許第88525号「写真植字機の改良」
出願:1929年 (昭和4) 1月1日、公告:1930年 (昭和5 ) 5月19日、特許:1930年 (昭和5) 9月30日
⑥ 特許第88890号「写真印字機の改良」
出願:1929年 (昭和4) 1月1日、公告:1930年 (昭和5) 7月18日、特許:1930年 (昭和5) 10月27日
いずれも特許権者 (発明者) として石井茂吉、森澤信夫の順に名を連ねている。どんな改良を加えたのだろうか。
ライターをヒントに
試作第2号機での印字テストを経て、印字のムラや文字の並びのガタつきなど、欠点は見えていた。それらをひとつひとつ潰していくように、実用化に向けての改良は加えられた。
まず、数個のレンズをピストルの弾倉のようにターレット式に配列し、このターレットを手で回すことにより、それぞれ倍率の違うレンズを中空管に接続できるようにする「回転レンズ箱」を設けた。レンズをターレット式に配列するアイデアは、試作第1号機ですでに取り入れられていたが、邦文写真植字機を実用化するにはすくなくとも10種類ほどの倍率の異なるレンズが必要と想定されたため、あらためて特許を申請した (① 特許第84793号「写真装置」) 。[注1]

-

特許第84793号では、10種類のレンズを装着できるように改良し、あらためて特許を申請 (特許情報プラットフォーム J-PlatPat https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ より)
つぎに、シャッターの改良だ。最初はふつうのカメラに使用されているシャッターを使ってみたが、写真植字機ではおそらく1日に1万回ものシャッター開閉をおこなう必要がある。ふつうのカメラ用のシャッターでは、そのようなひんぱんな開閉には耐えられず、すぐに壊れてしまうだろう。信夫はあれこれ工夫をしてみたが、なかなかうまくいかない。
ある日、信夫は銀座を歩いていて、あるライターに目を留めた。そのライターは、中にある丸やすりに3つのボッチがついていた。押すとフタが開き、そのときに3つのボッチのうちの1つがフタで引き上げられて点火するしくみだった。
「これだ!」
信夫はこれにヒントを得て、3つボッチ式のシャッターを開発した。「突起を押す」という一操作でバネを巻き、そして戻すという作動を繰り返せるシャッターだ。一操作でこれをおこなうため、露出時間がつねに一定に保たれる。しかも容易に壊れない耐久性をもっていた (② 特許第84794号「写真装置の『シャッター』」) 。[注2]
相次ぐ試作と実験
写真植字機では、文字盤から1文字を選んでレンズの位置に合わせて撮影し、印字をおこなう。このとき、選んだ文字の中心とレンズの中心がぴったり合っていないと、印字した文字の並びが上下左右にずれてガタガタになってしまう。これがずれずに固定できるしくみは試作機のころからかんがえられていたが、より簡単な操作で精度の高い印字ができる改良も加えた。ハンドルを上下させる操作だけで文字盤のXY方向が固定されるよう、歯棒とこれにかみあう鈎止レバーの改良をおこなった (③ 特許第84795号「写真装置の改良」) 。[注3]
さらに、暗箱の改良もおこなった。これまでの実験によって、フィルムを巻きつける暗箱内の円筒ががたつくと、印字中にフィルムの位置が安定せず、撮影した文字の並びが不ぞろいになることがわかっていた。これを解決するために、フィルムを巻きつけた円筒に1枚の黒布を巻きつけ、この黒布の一端を巻き取り軸にかけ渡して、この軸にフィルム円筒の回転方向に反発する力を与えるぜんまいバネを取りつけた。こうしてつねに一定方向に引きつけることで機構のがたつきをなくし、文字の並びが正確になるようにした (④ 特許第84796号「写真装置暗箱の改良」) 。[注4]
ここまでの4つの特許は、出願翌年の1930年 (昭和5) 1月9日付で付与されている。
さらに茂吉と信夫は、文字同士の間隔を思いのままに調節できるようにする改良 (⑤ 特許第88525号「写真植字機の改良」)と、印字にあたって各行の始めの文字の位置を正確にするとともに、各行の長さを必ず所定のサイズにそろえる改良 (⑥ 特許第88890号「写真印字機の改良」) の2つの特許も、おなじく1929年 (昭和4) 1月1日に出願した。これらはそれぞれ1930年 (昭和5) 9月30日、1930年 (昭和5) 10月27日に特許が付与された。[注5]
-

特許第88890号「写真印字機の改良」特許明細書より。印字する各行の開始位置を正確にそろえ、かつ、各行の長さを所定のサイズにそろえられるようにした (特許情報プラットフォーム J-PlatPat https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ より)
わずか2年ほどのあいだに、これだけの研究開発を続けたのである。こうしたしくみを考案するには、当然、試作や実験が必要だ。工場には工員がおり、彼らの食事や身のまわりの世話も必要だった。茂吉自宅に構えた研究所にも、計算助手の柴田などを住まわせていた。文字盤をつくるために雇ったひとたちもいる。
茂吉と信夫が最初の特許を出願したのが1924年 (大正13)。星製薬を退職して邦文写真植字機の開発に取り組み始めてから、ふたりには一銭の収入もなかった。茂吉の妻いくが営む米屋 (神明屋) の収入と石井家の蓄財だけでは、出る一方の費用をまかないきれるはずがない。しかも費用は増すばかりなのだ。石井家の蓄財は、いよいよ底を尽きていった。 (つづく)
[注1] [注2] [注3] [注4] [注5] 馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974 pp.114-116
【おもな参考文献】
馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974
『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969
「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975
『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965
森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960
産業研究所 編『わが青春時代 (1) 』産業研究所、1968
「邦文写真植字機遂に完成」『印刷雑誌』大正15年11月号、印刷雑誌社、1926
「発明者の幸福 石井茂吉氏語る」『印刷』1948年2月号、印刷学会出版部
【資料協力】株式会社写研、株式会社モリサワ
※特記のない写真は筆者撮影