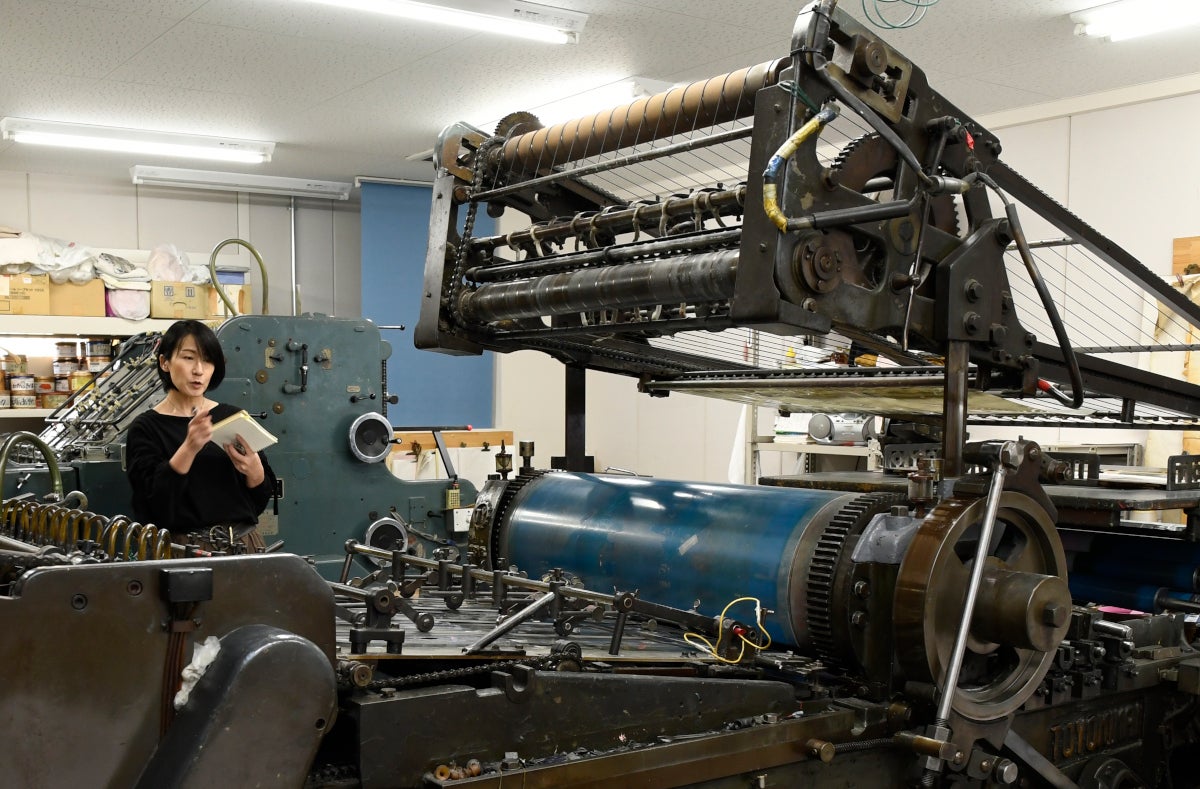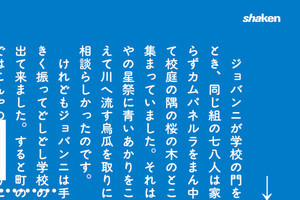フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)
心強い賛意
星製薬図案部長の長沢青衣から「写真で文字を組む方法」の話を聞いて着想を得たとき、星一社長のほかに、森澤信夫が相談した人物がもうひとりいた。東京帝国大学の機械科出身で、神戸製鋼所への12年間の勤務を経て星製薬に入った、高級機械技師の石井茂吉だった。
第19回でもふれたが、ちょうど信夫が写真植字機の着想に取り憑かれていたのと時期を同じくして、1924年 (大正13) 3月24日、郡山幸男による「写真植字機と国字問題」という記事が朝日新聞に掲載された。当時の信夫は知らなかったかもしれないが、郡山幸男 (こおりやま・さちお/1885-1950) は、1891年 (明治24) に創刊された初代『印刷雑誌』を引き継ぎ、1918年 (大正7) に新『印刷雑誌』を創刊して、後には日本印刷学会の設立・運営にも力を注いだひとだ。[注1]
記事では、刊行されたばかりの1924年版『ペンローズ年鑑』に掲載されていた「バウトリー式写真植字機 (当該記事では「バウツリー及びリー写真植字機」と紹介)」をくわしく紹介しつつ、当時日本で盛んに論議されていた「国字問題」について、郡山の見解が述べられていた。[注2]
信夫はこの記事の切り抜きを片手に、星製薬の先輩技師たちに「邦文写真植字機」の構想を話した。信夫にはアイデアはあるが、機械の専門知識はない。専門の学問を修めたひとたちの話が聞きたかった。しかし多くの技師は、製薬会社とは関係のない (とおもわれる) 機械の話をする信夫を、相手にはしてくれなかった。[注3]
そんななかで、ひとりだけ興味をもってくれたのが、高級機械技師の石井茂吉だったのだ。
信夫は茂吉に新聞記事を見せた。
「長沢部長から、イギリスでは活字を使わずに写真で文字を組む機械が研究されていると聞いたんです。これを日本語でやってみたいと考えているんですが、どうでしょう?」
茂吉は記事に目を通すと、ポツリ、ポツリと言った。
「うん、おもしろそうじゃないか。きみ、やる気があるなら、やってみてはどうだ」
実のところ、このときの茂吉には、そこに深入りする考えはなく、軽い気持ちでの賛意表明だった。その後も、たまに信夫に声をかけることはあったが、それほど気にとめずにいた。[注4]
しかし信夫にしてみれば、14歳年長の高級機械技師である茂吉が星社長に続いて賛意をしめしてくれたことは、さぞ心強く、力となる出来事だったにちがいない。
下宿を研究室にして
信夫はまず、模型をつくりはじめた。彼は直感のひとである。頭のなかにある機械をかたちにするのに、設計図を引くよりも先に手を動かすのが信夫だった。
五反田の駅近く、三田万吉という主人がいとなむ乾物屋・萬屋の一室が、信夫の下宿だ。机がひとつと、道具箱がひとつあるきりの殺風景な部屋だった。しかしこの道具箱に、信夫が必要とする材料がおさめられていた。[注5]
この部屋で信夫は、模型づくりにはげんだ。それは銅板を主材としてつくられた、卓上サイズとしてもコンパクトな、ちいさな模型だった。
つくるのは、写真で文字を組む機械。文字盤の文字を1つずつフィルムに感光して並べていく機械である。
写真植字機の「文字のもと」となる「文字盤」は、機械の下部に水平に置ける構造にした。「文字盤」はガラス板につくった透明な文字の集合物を想定していたが、今回の模型では構想のみで、信夫はまず、機械自体の構造をしめすことに主眼を置いた。[注6]
文字盤のうえに、やはり水平に1個の暗箱を置く。暗箱のなかにはフィルムを巻いた円筒を収容する。この暗箱から垂直に1本の中空の円管を立てて、そのなかにレンズをおさめる。このレンズで文字盤の文字を1つずつ写して、暗箱のなかのフィルムを感光させていく。
文字盤は、たとえば5,000なら5,000字の集合体である。そのなかから必要な文字を選んで写すしくみとしては、暗箱を前後左右に移動自在にした。そして、写そうとする文字の位置で暗箱を固定するにはギザギザの歯のついた棒を使い、暗箱に接続している小片を、この歯棒の歯にかみあわせてカチッと固定できるようにした。
1字写したら、1字の幅の分だけ、フィルムを送る必要がある。これは、ラチェット輪を暗箱のなかの円筒の軸につけて、レバーを押し下げては戻すと、ラチェットを1字分の距離だけまわすようにした。ラチェット (ratchet) とは「歯止め (装置)」の意で、一方向にしか回転しないよう制御する機構のことだ。
こうして1行分の文字を写したら、改行する。レンズ管を横に1行分だけずらせるようにすることで、これを可能にした。
「できた!」
-

1924年 ( 大正13 ) に森澤信夫が製作した、日本初の「邦文写真植字機」の模型『写植に生き、文字に生き 森澤親子二代の挑戦』( ベンチャーコミュニケーションズ協会ビッグライフストーリー編集局、1999 ) 口絵より
信夫は完成した模型を星社長のところに持っていった。
「星先生! こんなものをつくりました」
「もう模型をつくったのか」
星は感心しながら模型をながめると、信夫にこう言った。
「森澤くん。考えてみると、きみはとんでもないものに取り憑かれたな。発明にとってかんじんなことは、持続ということだ。いったん始めた以上、最後までやりとおさねばならん。必ずやりとげるという信念が必要だ。途中で放棄するくらいなら、はじめからやらないほうがいいし、だめだと判断したら潔く見切りをつける。これも発明にとって大事なことだよ」[注7]
信夫は星の言葉を肝に銘じた。「邦文写真植字機」の発明に駆ける決意を、彼はのちにこのように書き残している。
〈人のまねをするのがきらいで、半面一種の変人である私は、(多くの人が私をそう呼んでいる。) 飛行機の発明者ライト兄弟や、世界の大発明王エジソンの夢をみて、盛んに青春の血を燃やし、写真植字機の完成!こそは、われに与えられた天職である。何物を犠牲にしても、どんな苦難をしのんでも、これを成し遂げなければならぬと、堅く々々決意したのであった。〉[注8]
星の助言を胸に、信夫は「邦文写真植字機」の模型を持ち、おなじ星製薬五反田工場に勤める石井茂吉のもとに向かった。
(つづく)
[注1] 郡山幸男の名前の読みは「国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス」の記述に基づいた。 (2023年5月28日参照)
また、郡山幸男の経歴については、「印刷学会出版部」ウェブサイトの「沿革」を参照した。 (2023年5月28日参照)
[注2] 郡山幸男「写真植字機と国字問題」『朝日新聞』1924年3月24日付、東京朝刊3面
[注3] 倭草生「恩賜金御下賜の栄誉を担った 写真植字機の大発明完成す ―石井、森澤両氏の八年間の発明苦心物語―」『実業之日本』1931年10月号 (実業之日本社)p.158
[注4] 『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969) pp.80-81、橘弘一郎「対談第9回 書体設計に菊池寛賞 写真植字機研究所 石井茂吉氏に聞く」『印刷界』1961年10月号 (日本印刷新聞社) p.93
[注5] 馬渡力 編『写真植字機五十年』(モリサワ、1974) p.91
[注6] 信夫のつくった模型の説明は馬渡力 編『写真植字機五十年』(モリサワ、1974) pp.75-76
馬渡本では、「文字盤」は白い紙に黒インキで印刷した数千の文字を集めた板、あるいはガラス板につくった透明な文字の集合物と書かれているが、白い紙に黒インキで印刷した文字盤は最初の特許明細書に記されていない。暗箱のなかにおさめられているのも、フィルムまたは印画紙と馬渡は書いているが、「印画紙」という言葉は最初の特許申請時には出てこない。おそらくは後々の内容を馬渡が補足して書いたとおもわれるため、本稿では「白い紙に黒インキで印刷した」文字盤と「印画紙」の文言は、ここでは入れなかった。
[注7] 馬渡力 編『写真植字機五十年』(モリサワ、1974) p.76、産業研究所編「世界に羽打く日本の写植機 森澤信夫」『わが青春時代(1) 』(産業研究所、1968) p.230
[注8] 森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』(モリサワ写真植字機製作所、1960) pp.7-9
【おもな参考文献】
『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969)
森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960
馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974
産業研究所編「世界に羽打く日本の写植機 森澤信夫」『わが青春時代(1) 』産業研究所、1968
日刊工業新聞編集局『男の軌跡 第五集』にっかん書房、1987
『「印刷雑誌」とその時代――実況・印刷の近現代史』 (印刷学会出版部、2007)
橘弘一郎「対談第9回 書体設計に菊池寛賞 写真植字機研究所 石井茂吉氏に聞く」『印刷界』1961年10月号 (日本印刷新聞社)
郡山幸男「写真植字機と国字問題」『朝日新聞』1924年3月24日付、東京朝刊3面
倭草生「恩賜金御下賜の栄誉を担った 写真植字機の大発明完成す ―石井、森澤両氏の八年間の発明苦心物語―」『実業之日本』1931年10月号、実業之日本社、1931
『写植に生き、文字に生き 森澤親子二代の挑戦』ベンチャーコミュニケーションズ協会ビッグライフストーリー編集局、1999
【資料協力】
株式会社写研、株式会社モリサワ
※特記のない写真は筆者撮影