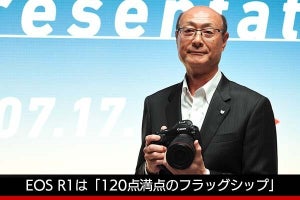“キヤノンのミラーレスカメラのフラッグシップモデル”と銘打った高性能ミラーレス「EOS R1」が2024年、満を持して登場しました。AF性能をはじめとする撮影性能や画質はとても高く、フラッグシップモデルの名にふさわしい仕上がりになっているとプロやハイアマチュアから評価を得ています。
キヤノンは、2021年9月に縦位置グリップ一体型の高性能モデル「EOS R3」を発表したものの、EOS R3はフラッグシップモデルではないとしていました。EOS R1は、どのような機能や装備を搭載したことで、晴れてフラッグシップの名を冠することができたのでしょうか? フィルム、デジタルでEOS-1シリーズを使い続けてきた吉村 永カメラマンが、Webサイトやカタログなどでは語られてこなかった部分をキヤノンの開発メンバーに直撃しました。
キヤノンのフラッグシップの基準となる要素は
――EOS R1、正式発表前までは「飛び抜けたスペックになるのではないか!?」と期待する声が多く聞かれました。しかし、連写速度はEOS R6 Mark IIと同じ、画素数もEOS R3と変わりませんでした。とがったスペックを期待していた人は「想像を超えるものではなかった」と感じたかもしれません。この仕様にした企画意図や、キヤノンのミラーレスのフラッグシップ機のコンセプトについて教えてください。
野々村さん:確かに、EOS R1はスペックシートだけを見れば進化を感じにくいかもしれません。しかし、実際に使ってみれば、大きく変わっていることが実感できるかと思います。
キヤノンのフラッグシップの基準となる要素については、先代のEOS-1系モデルからすべての面で進化していることが基準です。今回のEOS R1は、AFやファインダー、幕速も含めてEOS-1D X Mark IIIをお使いのユーザーに対しても自信を持って乗り換えを勧められるカメラに仕上がりました。
今回、EOS R1では新たにクロスAFを搭載しています。また、新開発の映像エンジンシステム『Accelerated Capture』とディープラーニング技術を組み合わせることで、さらなるAFの進化も実現しました。EOS R3でも被写体検出は高く評価いただいていましたが、水泳選手の帽子の部分、バレーボールのネット越しの被写体、サッカー選手が交錯するシーンなど、苦手なシーンが残っていました。今回、EOS R1ではこのようなシーンを克服しています。
フラッグシップ機は、あらゆる状況で高い総合力を持つことが求められます。その点で、EOS R1はAFの進化が総合力の向上に貢献しているといえます。
――EOS R3の発表時、「キヤノンの基準的に“1”の名を付けるには至っていない」と明確に言われました。では、EOS R3ではダメで、EOS R1で基準を満たした決定的な要素は何だったのでしょうか? 1シリーズはよく「信頼性が高い」と言われますが、それだけでは具体性に欠けます。「EOS R3は壊れやすいの?」「EOS R3は雨に弱いの?」と誤解される可能性もあります。3年間EOS R3を使用してきた私の経験では、そのようなことはありませんでした。防滴性能について、EOS R3は「“1”基準の防滴」を備えていたと聞いています。それでもEOS R1との差があるなら、その違いを具体的に教えてください。
野々村さん:EOS R3からEOS R1への進化点は、大きく分けて3つあると考えます。
1つ目は、先ほどお話ししたAFの圧倒的な進化です。EOS R3で残っていた苦手なシーンを完全に克服し、フラッグシップにふさわしいAF性能を実現しました。
2つ目は、EOS史上最高のファインダーを搭載した点です。これまでで最も大きく、明るく、見やすいファインダーとなっています。スペック的には944万ドット、倍率約0.9倍で、EOS R3と比べて約3倍の明るさとなっています。
3つ目は、CMOSセンサーの読み出し速度の向上により、遅延なし・ブラックアウトフリーの撮影、ローリングシャッター歪みの大幅な低減が可能になりました。光学ファインダーの見やすさにこだわって、EOS-1D X Mark IIIからミラーレスに乗り換えられない人もいると思いますが、もう胸を張って勧められる性能になったと感じています。
荒川さん:実は、R3は幕速やファインダーにおいて、EOS-1D X Mark IIIを超えたとまでは言い切れませんでした。だから“1”の名は付けられなかったのです。
機種名はなぜ「EOS R1」になったのか
――ネーミングについてもお聞きしたいのですが、なぜ「EOS R1」という名前になったのでしょうか?
野々村さん:もともと、一眼レフのEOS-1シリーズでは「EOS」と「1」の間にハイフンが入っていました。これは、数字の「1」がアルファベットの小文字の「L」や大文字の「I」と誤認されるのを防ぐためです。しかし、EOS Rシリーズでは「EOS」の後に「R」という英字があるため、ハイフンなしでも「1」を正しく認識できると判断しました。その結果、EOS Rシリーズのほかの機種との統一性を持たせるために「EOS R1」というネーミングにしました。
――私は「EOS-1R」になると予想していました。EOS-1は長年継承されてきたネーミングであり、フィルムからデジタルに変わっても引き継がれた名称だったので、そこは変わらないと思っていたんです。
野々村さん:補足すると、「ハイフン」+「1」という名称を最初に採用したのは、1971年に発売した「F-1」でした。F-1が最初のプロモデルのカメラということで、それを踏襲してEOSでも「EOS-1」という名称にしたわけです。その流れがEOS-1D X Mark IIIまで続いたという感じですね。
カメラ内アップスケーリング機能の長所は
――EOSシリーズの画像処理エンジン「DIGIC」ですが、初代からDIGIC 8まで世代が変わるごとにナンバリングが変わっていました。DIGIC Xが登場してから相当時間が経ったと思うのですが、今回のR1も同じ名前のDIGIC Xを搭載しています。これは、今までとハードウエア的にまったく同じものなのか、それともハードウエア設計が変わっているのに名称は据え置いたのか、どちらなのでしょうか?
唐橋さん:名称だけでなく、ハードウエアとしてもこれまでと同じ「DIGIC X」を搭載しています。
――ハードウエアも同じなんですね! 登場から4年半近く経っていながら、フラッグシップのEOS R1にも搭載しているのですから、ずいぶんと性能を先取りした設計だったんですね。驚きました。EOS R1では、撮影後に画素数を縦横2倍に拡大する「アップスケーリング機能」が搭載されました。PCでの後処理と比べて、カメラ内で行うメリットは何でしょうか?
加納さん:ワークフロー上のメリットとして、まず撮影現場でPCを使わずに画像を完成させられる点があります。また、トリミングと同時に適用できるため、スポーツや報道の現場で画質劣化を最小限に抑えながら迅速に編集できます。加えて、ニューラルネットワークによるノイズリダクション機能も搭載しており、RAW撮影すれば両方とも適用可能です。
――PCでのアップスケーリングと比べて画質の違いはありますか?
加納さん:EOS R1のニューラルネットワークのモデルは、撮影した画像をカメラ内で処理するのに最適化したものを使用しているため、効果が高いです。一方で、PC版のアップスケーリングでは、どのカメラの画像にも適用できる柔軟性を持たせたモデルを採用しているため、EOS R1に限らず他のカメラで撮影した画像にも対応できることが大きな利点のひとつです。最終的には、ユーザーのワークフローに応じて適切に使い分けていただければと思います。
クロスAFでさらに進化したオートフォーカス
――センサー全体にデュアルピクセルのAF位相差検出可能な画素が配置されていることは理解していますが、2400万画素すべてがデュアルピクセルなのでしょうか? もしそうであれば、そのうちの1/4がすべて横線検出画素になっているのですか?
福田さん:はい、その通りです。センサー自体は全面ベイヤー配列でレッド、グリーン、グリーン、ブルーの並びになっており、そのうちグリーンは2画素あります。従来はすべてフォトダイオードとして1つのマイクロレンズを使用していましたが、そのうち1つのグリーンの部分だけが上下に分割されているんです。
左右に分割している部分は、右上のグリーンの部分で横線AFが機能しているんですが、横分割にすると人間の目でいうところの目が左右にある状態に似て、縦線に対して視差が生じます。そのため、横分割は縦線の検出に使われるんですね。
一方、左下のグリーンの部分は上下に分割されています。こちらは、目が上下に位置しているような感じで、横線に対して視差が生じるため、縦分割は横線を検出できるという仕組みです。
見た目には非常に不規則に見えるかもしれませんが、右上と左下のグリーンを見ていただくと、横分割と縦分割が対称になっていることが分かります。この配列の特徴として、グリーンの横分割と縦分割をできるだけ密に配置し、解像度を上げることにより、AFの性能が最大化されるようになっています。
AFにとって最も重要なのはグリーンです。人間の目の解像度にも関連していますが、ベイヤー配列で解像度的に最も効果的なのはグリーンです。グリーンが2倍含まれており、レッドとブルーは色を調整するために使われます。AFとしても、解像度がしっかりと確保され、ピント合わせに最も使われるのはグリーンの成分です。
AFの性能を最大化するため、横分割と縦分割のグリーンをしっかりと配置し、精度を高めています。1/4をすべて縦分割とし、ベイヤー単位で全面に配列することで、横分割と縦分割のグリーンが最も対称性が高く、最も密な周期で配置され、クロスAFの性能が最も高くなる配列となっています。横分割と縦分割をきちんと配置することが、クロスAF性能の向上につながるのです。
――EOS R1は、どのようなシチュエーションでも、最後まで位相差AFのみでピント合わせするのでしょうか?
福田さん:EOS R1やEOS R5 Mark IIなど、最新の機種ではすべて位相差AFのみで動作しています。非常に暗い状況でフレームレートが低下することで、相対的にAFの速度が落ちることはありますが、それでも暗い状況下としては十分なAF速度と考えています。
――他社はコントラストAFを併用したハイブリッドAFを採用していますが、キヤノンがそれを採用しない理由は何でしょうか?
福田さん:デュアルピクセルAFを採用しているため、最大で撮像エリア100%の広いAFエリアで、明るい環境から非常に暗い環境まで位相差AFのみで十分に対応できるからです。また、レンズの絞りも明るい絞りから小絞りの暗い絞りまで位相差AFのみで機能するため、最近ではディープラーニングを用いた被写体検出や、トラッキングAFと組み合わせることで総合的なAF性能を向上させています
位相差AFだけで完結することで、広いAFエリアでディープラーニングによる被写体検出と位相差AFの連携処理をリアルタイムに高速で行えるため、被写体トラッキングAFとの相性が良くなり、高速連写時のシーケンスを維持しやすくなります。また、相対的にフレームレートが下がる場合でもAF性能を保ちやすいというメリットもあります。
例えば、EOS R1にF1.2のレンズを装着した場合、肉眼ではほとんど何も見えないような暗所でもAFが機能します。このような限界性能を実現できるため、位相差AFのみで十分対応できるのです。
――先日、イルミネーションの中で人物撮影をしたのですが、EOS R1は非常に優秀で、AFの動作が明らかに変わったと感じられ、技術の進化を実感しました。かつてのAFは点光源に弱い傾向がありましたが。
福田さん:AF性能は確実に向上しています。特にEOS R1では、ディープラーニングにより、顔近くの障害物を除いた顔や頭の領域を検出し、かつ、クロスAFを活用することで、周囲の障害物の影響を最小限に抑えながら、スポーツなどの動きの激しいシーンでも人物の瞳や顔、頭にAFが正確に動作するよう工夫しています。
――クロスAFだから点光源に強いというよりも、AFしづらい点光源を避けるディープラーニングが搭載されているのでは?と想像しましたが、どうでしょうか?
福田さん:点光源に対して、ディープラーニングを直接使っているわけではありません。ただし、先ほどご説明したように、ディープラーニングにより周囲の障害物を除いた顔や頭の領域を検出し、検出された領域の中の複数のクロスAFポイントから同時に情報を取得し、その中から最適なポイントを選択する処理に工夫を凝らしています。
クロスAFでは、同じAFポイントでも縦方向・横方向の両方で検出できるため、より安定した情報を得られます。その結果、AFの信頼性が向上し、狙った被写体に正確にピントを合わせやすくなっています。
また、クロスAFはネット越しの被写体にも強く、画面の隅でも高精度なAFを実現できます。スポーツ撮影では、選手が画面端に移動しても構図を優先して撮影できるように設計されています。
――一眼レフでは、そもそも画面周辺部ではAFできませんでしたからね。
福田さん:デュアルピクセル Intelligent AFでは、シチュエーションを認識する新たな機能として、サッカーやバスケでのシュート、バレーボールでのアタックなどの決定的なプレーを自動認識し、重要なプレーヤーに高速にAFを切り替えるアクション優先機能を搭載し、より快速・快適・高性能なAFとしています。
バリアングル液晶が180度開かないワケ
――EOSのフラッグシップ機は代々、大型のバッテリーを採用していますが、バッテリーの電圧が異なることでパフォーマンスに何か影響はあるのでしょうか?
荒川さん:はい、関係があります。LP-E6系とLP-E19系の違いについてのご質問かと思いますが、確かに影響があります。
例えば、電子シャッター幕速の話にも関連しますが、幕速が速いほど電子シャッターのローリングシャッター歪みの低減につながります。これを実現するためには、LP-E19の大きな電力供給が重要なポイントとなります。そのため、バッテリーの違いはカメラの性能に関係しているといえます。
――これはもうずっと以前から言われている都市伝説のような話なのですが、「EOS-1系は大容量バッテリーを使用しているため、レンズ内モーターの駆動電圧も他機種より高くなり、モーターの回転が速く、トルクも増してAFが速くなる」といった話をよく耳にするのですが、実際のところはどうなのでしょうか?
荒川さん:詳細はお答えできませんが、電源条件に応じて各種制御の最適化は実施しています。
――EOS R1の背面液晶は約210万ドットと、R3の約415万ドットに比べて少なくなっているのはなぜでしょうか?
荒川さん:確かに、EOS R3ユーザーが疑問に感じられる点かと思います。実は、EOS-1D X Mark IIIと同じ仕様に揃えたのです。また、今回EOS R1と高画素モデルのEOS R5 Mark IIの併用を推奨する意図があり、あえてEOS R5 Mark IIと同じ約210万ドットのパネルを採用しました。
我々としてもこの点は気にしていたのですが、発売前に試用していただいたプロの方から「不満がある」といった声は今のところ届いていません。その点については、ほっと胸を撫で下ろしているところです。
――キヤノンのバリアングル液晶は、なぜ180度まで開かないのでしょうか?
荒川さん:液晶を閉じるとき、最後の方で吸い込まれるような力がかかっていると思います。この力を確保するために、180度の開放角度を犠牲にしているのです。もし180度開くことを優先すると、最後に閉じる際の吸い込み力、つまり引き込み力が確保できなくなります。180度にすると、製品の個体差で少しカタカタしたり、安定感に欠けることが発生する可能性もあります。それを避けるために、数度だけ角度を犠牲にし、吸い込み力をしっかり確保できるような構造にしているわけです。
ローパスフィルターを搭載し続ける理由、メカニカルシャッターを省略しなかった理由
――ローパスフィルターはEOS-1D X Mark III に比べて進化しているのでしょうか?
加納さん:はい。ローパスフィルターはEOS-1D X Mark IIIと同様にGDローパスフィルターを採用しています。GDローパスフィルターは、ガウスフィルターを光学的に再現したもので、高い解像性能とモアレ低減のバランスが特徴です。今回、EOS R1用に最適化したものを使用し、より精細な描写を可能にしています。
――EOS R3よりも細かい部分の描写が優れているように感じることが多いのですが。
加納さん:高性能な光学ローパスフィルターでモアレを抑えつつ、高周波成分をより積極的に取り込めるようになっています。またローパスフィルターの特性を最大限活かせるように画像処理を最適化していますので、その効果を感じていただいているのだと思います。
――一時期、カメラ界隈ではローパスフィルターを付けると解像度が下がってよくないのでは、という考え方が広がりました。キヤノンも「EOS 5Ds R」などローパスフィルターレスの機種を出していましたが、それ以降はずっとローパスフィルターを搭載し続けています。これはポリシー的なものなのでしょうか?
加納さん:カメラの機種ごとに解像性能とモアレ耐性のバランスを考え、ローパスフィルターレスの選択肢も含めて仕様を検討しています。その結果として、EOS R1ではGDローパスフィルターを採用しました。
――つまり、キヤノンとしては「必ずローパスフィルターを搭載する」と方針が決まっているわけではなく、各機種ごとに最適な判断をしているわけですね?
加納さん:ローパスフィルターがないと、洋服や建築物などでモアレや偽色が発生する場合があるため、解像感だけではなくモアレや偽色とのバランスは大事に考えています。光学的な画質劣化を補正するデジタルレンズオプティマイザなどの画像処理とローパスフィルターを組み合わせることで、解像感の維持とモアレや偽色の低減の両立を実現しています。ローパスフィルター搭載の有無は、その機種の特性や画質を考慮して機種ごとに最適な判断をしています。
――カメラ側やアプリ側の処理で精細感を高める工夫はされているのですか?
加納さん:ローパスフィルターで高周波の信号は落ちるんですが、完全になくなってはいないので、カメラ内のデジタルレンズオプティマイザでそのあたりは問題にならないレベルまで補正しています。さらに、純正ソフトのNeural network Image Processing Toolにはニューラルネットワーク レンズオプティマイザという機能がありまして、レンズの収差も含めて光学的な画質劣化をより強力に補正できます。
――アプリの話が出たところで思い出しましたが、CaptureOneやAdobe Lightroom Classicなどの現像アプリを試してみて、やっぱりEOSは純正アプリのDPPでの現像が画質的には一番、というのが僕なりの結論です。ですが、もうちょっとUI(ユーザーインターフェース)や処理速度を現代的に洗練できないものかと感じています。バージョン4でインタフェースを刷新した、といったお話があったと思うのですが、この進化が激しい世界の中では他社の進化にちょっと追いついていない印象があります。
吉江さん:ユーザーの方からも、特に処理時間など使い勝手の面でご意見をいただくことがあります。我々としてもそのあたりの課題は認識していまして、次期バージョンがいつ出るというのはコメントできないのですが、しっかり考えています。
――メカニカルシャッターと同等以上の読み出し速度を持つ高性能センサーを採用したにもかかわらず、メカニカルシャッターを省略しなかったのはなぜでしょうか?
荒川さん:カメラとしては電子シャッターをデフォルトとしたので社内でも議論があったのですが、EOS R3を使う大手通信社のカメラマンを中心に「メカシャッターがあって助かった」という声を多くいただいていたことが大きな理由です。LED照明やデジタルサイネージの影響を受ける環境でも、メカニカルシャッターがあればフリッカー現象を回避できる、ということです。他社の動向も意識しましたが、フリッカー対策で今回はあえてメカシャッターを残す判断をしました。
2段階化したAF-ONボタンの狙い
――2段階化したAF-ONボタンの目的や、便利な使い方について教えてください。
荒川さん:このボタンの狙いですが、撮影中にAFを保ちながら、指の位置を変えずに一時的に設定を変更できるようにすることです。撮影の際、グリップを維持しながら瞬時に設定を切り替えたいシーンは多々あります。そのような場面に対応するため、2段階押しのAF-ONボタンを採用しました。
このボタンを活用すると、連続撮影モードの切り替えや、一時的に瞳AFに切り替えるといった使い方が可能になります。こうした設定変更を、指の動きを最小限に抑えながら瞬時に行えるのが大きなメリットです。
ただし、このボタンの操作感については、プロのカメラマンの方々の間でも好みが分かれるようで、撮影中に親指は人差し指ほど繊細に動かしにくい、という点が課題として挙げられました。しかし、慣れれば十分に活用できる場面があると思っていますので、ぜひ活用いただけたらと思っています。
――EOSは他の機種も含めて、シャッター幕のうち1枚だけがつや消しになっているように見えます。これはなぜですか?
荒川さん:シャッター幕は4枚構成になっており、そのうち1枚だけ材質が異なるためです。開閉を繰り返すシャッターは高い耐久性が求められますが、1枚だけ別の材質を採用して強度を上げることで耐久性を確保しています。
EOS R1のデザインコンセプトやこだわり
――EOS R1のデザインに込められたテーマについて教えてください。
柏木さん:R1のデザインコンセプトとしては、従来のキヤノンのエルゴノミクスを継承しながらも、新たな要素を取り入れています。これまでの流体的なフォルムを活かしつつ、そこに硬質なイメージを付与することで、「しなやかさ」と「硬質さ」の共存を目指しました。
――EOS-1D系のカメラというと、ルイジ・コラーニのデザインコンセプトを受け継いだ「グニャッ」とした流線形のフォルムが特徴的ですよね。ですが、EOS R1を見たときに「いつものデザインなのにかっこいい」と思ったんです。よく見ると、曲線が少なくなってシャープなエッジや張りのある面が増え、非常に現代的な印象を受けました。このあたりのデザインの変化について、どのように考えていますか?
柏木さん:ありがとうございます! アイコニックなシルエットや、1D系らしいエルゴノミクスは継承しつつも、細部の造形は現代的なアプローチで作り込んでいます。例えば、Canonロゴの周辺はフラットに近い面で構成し、左右に面の折れを感じるV字のハイライトが入るような造形を施しています。一方で、手に触れる部分は従来と同じく柔らかい造形にし、全体として硬質さとエルゴノミクスのバランスを取っています。
――貼り革のパターンが変わったのは、何か意図があるのでしょうか? 実際に撮影してみると、R3よりも持ちやすくなったと感じます。指の掛かりがよくなり、ストラップなしでも安心感が高まった印象です。
柏木さん:グリップ部分のデザインは、縦位置と横位置のフィーリングを統一できるように試行錯誤を重ねました。新しいグリップパターンには凸型の幾何学パターンをを採用しています。このパターンは滑り止め効果が高く、水切れ性能も優れているため、悪天候や汗をかいた状態でもグリップ力が落ちにくい設計になっています。
――ボディの張り革がマウント上部にもつながっているのが特徴的ですが、これはスペースに余裕が生まれたからでしょうか? 従来、この部分には張り革はなかったですよね。
柏木さん:EVFの大型化により新たに生まれたスペースを有効活用する形でラバーを回し込んでいます。これにより、レンズ交換時の心理的な負担を軽減する効果も期待できます。単にデザイン的な要素ではなく、使用感の向上という面も考慮しています。
――本日は長時間にわたり、機能からデザインまで細かな疑問にもていねいにお答えいただき、ありがとうございました!