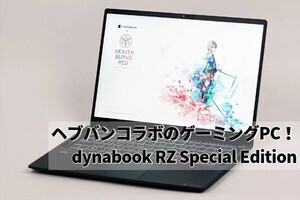Dynabookが1月23日に発表した「dynabook XP9 CHANGER」(個人向け店頭モデル名称。法人モデルは「dynabook X94」、Web専売モデルは「dynabook XPZ」)は、これまでの同社“CHANGER”同様に劣化したバッテリーパックをユーザー自身で交換できる「セルフ交換バッテリー」を主要な訴求ポイントとしている。
しかし、それと合わせて「当社(=Dynabook)が考えるAI時代を牽引するモバイルノートPC」(同社Webページに掲げられた文章)として「Copilot+PC準拠」を訴求していることも見逃せない。
-

dynabook XP9 CHANGE。1㎏を切る(想定)軽さの14型のCopilot+PCとなる。CPUはLunar Lakeの開発コード名で知られるIntel Core Ultraプロセッサ(シリーズ2)を搭載。発売は2025年4月中旬で、店頭予想価格は290,000円台前半
*【 関連記事】:Lunar Lake搭載のdynabook! セルフ交換バッテリー搭載の14型Copilot+ PC「XP9」が4月発売
NPUを組み込んだIntelのCPU「Meteor Lake」「Lunar Lake」プロセッサーファミリーが訴求する「AI PC」を、Dynabookも2024年から自社製品のプロモーションで積極的に打ち出している。dynabook XP9 CHANGERでいうところの「AI時代を牽引するモバイルノートPC」「Copilot+PC準拠」も、その系列の訴求といえるだろう。
しかし、Dynabookの“中の人”に話を聞くと、その流れとは別の、独自に描いているAI PCの将来像があるという。“中の人”たちは、どんな思いで AI PCと訴求しているのだろうか。その意味を深掘りすべく、Dynabook商品統括部統括部長の須田淳一郎氏と、Dynabook商品統括部グローバル商品開発部 開発第三担当(筆者注:ソフトウェア開発担当)グループ長の渡辺淳史氏に話を聞いた。
AI PCはスタンドアローンでAIが使えることが利点
インタビューの冒頭から須田氏は「AI PCなのですが、正直に申しますと業界で何がAI PCなのかという明確な基準というのはなく、皆さんいろんな視点で呼んでいるのが現実ですね」と、なかなか“ぶっちゃけた”発言をぶつけてきた。「ただ、基本的に一貫して言えるのは、ローカルでAIの推論を行うことができるPCということでAI PCは定義されています」(須田氏)
その上で、「じゃ、それをAI PCと呼ぶと何がいいのかっていうと、はっきり言ってしまうと“スタンドアローンでAIが使えるようになる”、これが1番のメリットになります」と単純明快に示してくれる。「セキュリティーの観点でいうと外に情報漏れません。これは非常に大きなアドバンテージ」(須田氏)
とはいえ、精度の高い出力ができるAIには大規模なエンジンが必要だ。ChatGPTやMicrosoft Copilot、Gemini、Claude、Llamaに匹敵する大規模言語モデル(LLM:Large Language Models)なんてローカルにはとても置けない。しかし、PCで(もしくはICTで)AIを活用する場面は、別に大量の資料を要約させたり、頭に浮かんだ言葉から精密な絵に描かせたりするだけではない。
「生成AI以外にも、世間にはいろんなAIがあります。ただ、LLMで多くのユーザーが“びっくり”されたので生成AIが非常に脚光を浴びていますが。今はいろんな使い方をまだ模索している状態です。生成AIだけじゃなく、最適化するもの、あるいは予測AIと言われているものなども、AIとしては非常に有用なもので、我々はこれらを区別せずに全てをAIと呼ぶようにしています」(須田氏)
須田氏が言うように、多くのユーザーにとって「AI」という言葉はクラウド側にあるLLMを動かす生成AIが一般的に認識されている。ならば、ローカルで使うAIは、それらとは違うAIとして訴求するのがいいのではないだろうか。
「違いを区別できる、AI技術に造詣が深いユーザーには理解してもらえます。一方で、“AIってなに?”というユーザーはまだ多くいます。そこに向けてLLMがどうで生成AIがどうで、これは予測系だから違います、と説明しても理解していただくのは難しいです」(須田氏)
4つの独自AI機能を開発。ローカル環境で動くAIへの想い
このような認識の中、Dynabookに限らず多くのPCベンダーはインテルがAI PCを唱え始めた2024年(AIアクセラレータを実装したCore Ultraのプロモーション開始に合わせて)から、クライアントPCにおけるAI利活用を訴求していた。
ただ、少なくとも2024年時点ではローカルPCでAIを利活用できるアプリケーションは限られて(ユーティリティなどでローカル環境でもAIを利活用していたものの)、そのメリットをエンドユーザーに理解してもらうのは難しい状況にあった――という経緯がある。
2025年になって、Dynabookが「Copilot+PC」準拠として改めてAI利活用を掲げる今回の「dynabook XP9 CHANGER」では、ローカルPCでAIを利活用できるオリジナルAI機能として「dynabook AI アシスタント」「AIパワーオプティマイズ」「AIプライバシーアシスト」「AIハンドコントロール」といった4つのユーティリティを導入した。
このうち、AIパワーオプティマイズとAIプライバシーアシスト、そして、AIハンドコントロールは、環境設定、セキュリティー、マンマシンインタフェースにおけるデバイス設定でAI機能を利活用する、2023年から導入してきた方向性のさらなる進化=機能強化だ。
しかも「dynabook AI アシスタント」は、ユーザーからの自然言語=話し言葉による問いかけに対してその内容を理解し適切な回答を推論して提示するという、ChatGPTやClaudeといった“一般的な”生成AIと同様の機能をローカルPC環境で(それもスタンドアローンPCで)実現しようとしている。
AIの利活用というと(超個人的な考えなのかもしれないが)、「ユーザーの使い方をAIが学習することで、そのユーザーにとって最適化された回答が出力される」と考えてしまうが、現時点においては「将来的にはそういったものを取り込んでいく可能性はありますが、今はまだその時期ではないと思っています」(須田氏)という。
「例えば、その人のスケジュールを組んで月曜日に会議があるからその前にノートPCを充電しておこう、といった予測にAIを使うことは可能ですが、そのスケジュールをクラウドから参照する(筆者注:前提として最近のスケジューラーはクラウドにデータを置いていることが一般的)場合スタンドアローンではできないことがあります。ただ、コンシューマーの使い方を考えると、明日自分が何をするのかをAIが予測している世界は快適ではないかと思います」(須田氏)
-

のぞき見アシスタントは、PC利用者の背後から画面ののぞき見があった際にAIが検知する機能。のぞき見を検知すると画面上にアラートバーが表示され、ホットキー操作で表示画面をブロックする。アラートをどう表示させるかが難しかったポイントとのこと
-

AIハンドコントロールは、PC利用者のジェスチャーをAIが認識し、動画試聴時やプレゼンテーション時に、再生や次のコンテンツ表示といった操作を行う機能。これまでも同様の機能を搭載するPCはあったが、AIの導入で認識精度が大幅に高まったという
今後は1人1人に合わせたさらなる“最適化”を目指す
これも筆者の超個人的な考えかもしれないが「AIができること」と聞くと「ユーザーの使い方を学習して最適なアドバイスを提案してくれる(もしくは自動でやってくれる)」ぐらいのことを期待してしまう。
しかし、須田氏は「AIは大きく分けて学習フェーズと推論フェーズに分かれます。学習フェーズは大きなコンピューティングパワーを必要とするので、いまエッジ側で注力するのは、学習済みデータを使ってどう推論していくのか、という部分だと思っています」という。
ちなみにDynabookが現時点で用意しているAIパワーオプティマイズでは、クライアントPCの利用状況、具体的には内蔵カメラのオンオフやネットワークを利用しているアプリを監視して、AIが「あ、このユーザーは今リモート会議をしている」と判断したら、バッテリー消費を抑える設定へ自動的に移行してリモート会議中のバッテリー切れを極力回避する。この“仕掛け”を応用して発展させれば、将来的には多様な場面で同様のことが可能になると渡辺氏は語る。
「現時点ではリモート会議時に、バッテリーを長持ちさせる最適化だけ実現していますが、この他にBluetoothを使っていたとか画面の輝度をかなり落としていたとか、そういう情報を蓄積してユーザーごとに使いやすい環境を提供することも今後は考えられる」(渡辺氏)
その進化の過程において、現在はカバーしていない「学習のフェーズ」はどのタイミングで組み込まれるのだろうか。須田氏は「まさにもう議論しているところで」というが、まだ着手されていないという。いまは4月の出荷を目指してdynabook XP9 CHANGERに実装するローカルAIのチューニングを進めているところだ。
ただ、開発に向けたロードマップは策定しているという。そこでは推論フェーズはローカルPCで、演算パワーを要する学習フェーズは「クラウドで」という形態を想定している。ネットワーク越しのセキュリティーの不安は「オンプレミス環境で学習させる」(須田氏)ことで回避するとしている。
PCをもっとパーソナルな存在に。Dynabook AIの未来像
DynabookとしてはAI利活用の開発はまだまだ始まったばかりだ。これから時間をかけ、ユーザーにとって使いやすい、意味のあるローカル環境に置けるAI利活用を用意していく。その先を見据えたマイルストーンとして、Dynabookの製品発表会で用意された資料には、企業向けAI PC、個人向けAI PCのそれぞれで“3種類”のキャラクターイラストが描かれていた。
企業向けのAI PCでは若葉マークをあしらった新人社員から中堅社員を経て「優秀なアシスタント」となり、個人向けAI PCでは“昭和40年代”を彷彿させるロボットから平成アニメの戦闘メカを経て愛玩的な「愛着のあるキャラクター」メカが描かれている。
そのイラストに込めた意味として須田氏は次のように語ってくれた。
「一部の方はAIを敵視しているところがあって、それは自分の仕事を奪われる恐れだったり、人類を超えて支配される恐れだったりするのですが、我々が目指しているのは、ミツバチと花のように、お互い共栄できるような関係がAIと人類で作れればいいのではないかと。人類もAIの知見を必要とし、 AI側は人類のインプットを得て共に栄えていく。共生していく世界っていうのをどう作っていこうかっていうのが我々の未来かなと」(須田氏)
今、AIという言葉は「流行り言葉」のように使われている。だが、AIは技術であって長い時間をかけて堅実な研究開発を重ねて本当に使える“道具”となっていく。ChatGPTの影響でこの数年に限った最新技術と多くの人とは思うかもしれないが、その萌芽はニューロコンピューティングと言葉と共に昭和と平成の境目から脈々と続いている。
一時のプロモーション的なブームに惑わされることなく長い目でDynabookのAI PCの進化を見据えていることが分かる須田氏の言葉だったといえるだろう。