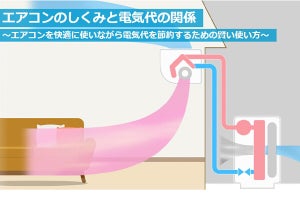ダイキン工業(以下、ダイキン)は、2種類の暖房を同時に使える遠赤外線暖房機「ハイブリッドセラムヒート(WRH134AS-H)」を2023年10月に発売しました。ダイキンのサイト「DAIKIN LAUNCH X」での価格は73,000円です。
暖房にはさまざまな種類がありますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。そこで、ハイブリッドセラムヒートは遠赤外線ヒーターと温風ファンヒーターの両方を搭載することで、それぞれの長所を生かした製品です。ところでこの製品、スポット暖房ながら直販価格が73,000円とそれなりに高価ですが、ダイキンによると売れ行きは好調とのこと。気になる実機をダイキンでチェックしてきました。
スポット暖房のいいとこどりしたハイブリッド式
エアコンは省エネかつ快適な暖房ですが、部屋全体を暖める必要がない場合はオーバースペックになりがち。また、暖かくなるのに時間がかかるというデメリットもあります。
そこで活躍するのが、狭い範囲をすばやく暖めるスポット暖房。速暖性の高いスポット暖房を導入すれば、エアコンが部屋の温度を上げるまで寒い思いをしなくてすみます。加えて、エアコンの設定温度を下げてスポット暖房で足元を暖めるなど、使い方しだいで快適性を損なわず省エネにもなります。
-

ハイブリッドセラムヒートもスポットタイプの暖房。本体サイズは高さ幅500×奥行き226×高さ522mm、重さは10kg。写真はマイナビニュース +Digitalの林編集長とサイズを比較。それなりのサイズ感ですが、本体デザインがシンプルだからか圧迫感はありません
ハイブリッドセラムヒートは「遠赤外線ヒーター」と、温風が吹き出す「ファンヒーター」の2種類を使い分けられる点が大きな特徴。
遠赤外線ヒーターは空気を加熱しない暖房方式で、光の一種である遠赤外線を放射します。放射先の障害物の分子を振動させることで対象を直接加熱するので、遠赤外線ヒーターは部屋の空気を暖めません。このためエネルギーのロスが少なく、風の影響も受けません。また、人に当たると身体の分子を震わせて温めることから、「身体の芯まで暖まりやすい」という点もメリットです。一方、遠赤外線が当たる肌表面が熱く感じすぎる場合もあり、置き場所や距離の調整が必要。
-

ハイブリッドセラムヒートの前面パネルを外したところ。2本ある黒い棒が遠赤外線を放射するセラミックコーティングシーズヒーターです。セラムヒートは遠赤外線の中でも人の肌に吸収されやすい波長を利用しています。なお、ダイキンはセラミックコーティングによる遠赤外線暖房のみの「セラムヒート(ERFT11ZS)」も販売しています
遠赤外線ならではのデメリットを抑えるため、ハイブリッドセラムヒートは本体上部にシロッコファンを配置。本体内部で発生した熱を集めて足元から温風として吹き出す「ファンヒーター」としての機能も搭載しました。スイッチを入れて約10秒で温風が吹き出し、すばやく身体を暖められるほか、遠赤外線ヒーターによくある「身体表面だけ急に熱くなる」という不快感もありません。
ハイブリッドセラムヒートは遠赤外線ヒーターのみを使用する「輻射」と、温風のみを吹き出す「温風」モードが切り替えられますが、標準は両方をバランスよく利用する「自動」モードです。自動モード時はまず温風によってすばやく足元を暖め、時間とともに徐々に温風をゆるめて、最終的に遠赤外線ヒーターをメインにします。
-

ハイブリッドセラムヒートの操作パネル。手前の「温風」「輻射」ボタンでヒーターの種類を切り替え。両方が点灯すると自動モードになります。最大消費電力は1,250W。電力量がデジタル表示されるのもわかりやすくて好印象です
安全性の高さはさすがダイキン、とはいえ気になるところも?
ダイキンは以前から遠赤外線単体の暖房器具「セラムヒート」シリーズを販売しています。今回のハイブリッドセラムヒートで遠赤外線と温風のハイブリッドタイプになったことで、「暖かさ」以外にも安全性という大きなメリットが生まれました。
最初に「遠赤外線は対象物を直接暖める」と説明しましたが、暖房器具の本体、とくに本体前面のパネル(ガード)などは、遠赤外線を多く吸収するため熱くなりがち。一般的にこのパネルは面積も大きく、子どもが手で触れてしまう可能性もあり危険です。
ハイブリッドセラムヒートは前面パネルの熱をファンが回収して温風として排出するため、遠赤外線暖房の使用中にパネルを触ってもあまり熱さを感じません(安全のためパネルは触らないようにしてください)。
-

800Wで加熱中のハイブリッドセラムヒートの前面パネルに触る林編集長。「奥からの遠赤外線で手のひら全体は熱く感じるのに、金属のパネル部分はむしろヒンヤリと冷たい……。熱いと冷たいが混じって不思議な感覚」(林)
本体下の温風吹き出し口は最高で85℃ほどになりますが、前面パネルは最大の1,250W運転でも約50℃にしかならないそうです。温風の出ない輻射モードで動かせば、子どもがいても安心して使用できるのではないでしょうか?
「子どもやペットがいるけど温風も使いたい」という場合は、温風を含めて本体の表面温度が50℃以上にならない「ひかえめモード」という設定がおすすめ。ほかにも「チャイルドロック」や、本体の温度が下がるまで前面パネルが外せない「パネルロック」、消し忘れ防止6時間タイマー、2重の転倒保護スイッチなど、さまざまな安全機能を搭載しています。このあたりは日本メーカーならではの安心感ですね。
省エネを意識した機能もいくつか備えています。たとえば「リズム」モードでは、遠赤外線ヒーターの暖かさに強弱をつけて暖房。暖かさに強弱をつけると、パワーを抑えて運転しても寒く感じにくくなるそうです。人感センサーモードをオンにすると、人を検知できなくなって10分後にパワーを下げ、15分後に電源を自動でオフにします。
このほか、部屋の温度が22℃以上になったとき、自動的にひかえめ運転に切り替えて消費電力を抑える機能も。安全性と省エネ性に配慮した賢い機能ですが、ちょっと気になったのは「22℃以上でひかえめ運転になる機能はオフにできない」こと。外出先から帰宅後すぐなど、部屋が22℃以上でも「寒い」と感じるシーンはあります。人によって寒く感じる温度帯も違うので、ひかえめモードに入る温度を自分で選べるとよかったと思います。
とはいえ、デザイン、機能、安全性、いずれもなかなか魅力的。スポット暖房としてはそれなりの価格ですが、実機に触れてみると好調に売れているのも納得です。この冬、スポット暖房の購入を考えているなら、量販店などで実機をチェックしてみてください。