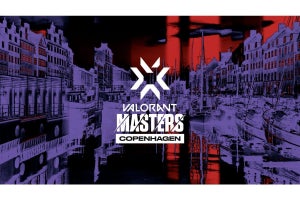昨今ますます注目度が高まっている、タクティカルFPS『VALORANT』のeスポーツシーン。世界3位を獲得したプロゲーミングチーム「ZETA DIVISION」(以下、ZETA)の歴史的快挙をきっかけに、『VALORANT』の大会に興味を持った人も多いのではないでしょうか。
プロのハイレベルな撃ち合いはそれだけでも十分に魅力的ですが、『VALORANT』のルールを知っていれば、より楽しく観戦できます。そこで今回は、『VALORANT』の大会を観戦するにあたって、知っておきたい基本ルールをおさらい。それぞれの項目には、『VALORANT』の大会でキャスターを務めるリーゼフェルトさんから、ワンポイント解説をいただきました。見どころを踏まえて、ぜひ観戦を楽しみましょう。
アタッカーとディフェンダー、それぞれの勝利条件は?
『VALORANT』は、「サイト」と呼ばれるエリアに「スパイク」(爆弾)を設置するアタッカーサイドと、それを阻止するディフェンダーサイドに分かれ、5対5のチームで対戦します。
12ラウンドで攻守を交代。先に13ラウンドを先取したチームが勝利となります。アタッカーサイドとディフェンダーサイド、それぞれのラウンド勝利条件は下記の通りです。
・アタッカーサイド
相手チームを全滅させれば勝利
スパイクを設置したあと、起爆させれば勝利
・ディフェンダーサイド
相手チームを全滅させれば勝利
制限時間内にスパイクを設置させなければ勝利
スパイクが設置されたあと、解除すれば勝利
■リーゼフェルトさんのワンポイント解説
勝利条件に関わるスパイクの設置と解除については、両サイドにとって必要な時間を知っておくと、観戦がよりおもしろくなります。
まず、ラウンドの制限時間は1分40秒です。スパイクの設置にかかる時間は4秒なので、アタッカーサイドはラウンドの残り時間が4秒を切る前に、設置を完了させなければなりません。スパイクの設置に成功すると、起爆まで45秒の時間が追加されます。
ディフェンダーサイドは45秒以内にスパイクの解除を目指しますが、解除には7秒かかります。解除を半分の3.5秒まで進めた場合、一度手を離しても、再び解除を始めたときに残り3.5秒で解除が完了します。この「ハーフ解除」はよく使われるので、ぜひ覚えておきたいですね。
装備を購入するクレジットの仕組みを知ろう
『VALORANT』では、ラウンドごとにクレジット(お金)で装備を購入して戦います。クレジットで購入できるのは、武器やアーマーと、一部のアビリティ(スキル)。クレジットは、ラウンドの勝敗やキル数、スパイクの設置解除などに応じて、各ラウンドの開始時に付与されます。
使わなかったクレジットは、自動的に次のラウンドへ持ち越されるほか、生き残ったラウンドでは、所持している武器やアーマーが次のラウンドに持ち越されます。装備の購入に関する主な用語は、下記の通りです。
・フルバイ
必要な武器とアーマーをすべて買うこと。基本的には、ファントムやヴァンダルなどのメイン武器と、ヘヴィーアーマーを買うことを指す。3,900クレジット以上が必要。
・エコラウンド
次のラウンドで十分な装備を買うために、最小限の装備で戦うラウンドのこと。
・ハーフバイ(調整バイ)
次のラウンドで必要なクレジットを残し、買える範囲の装備を買うこと。
・フォースバイ(強制バイ)
クレジットが少ない状況で、無理やり買える範囲で装備を買うこと。
・セーブ(キープ)
次のラウンドに武器を持ち越すため、生存を優先すること。
■リーゼフェルトさんのワンポイント解説
クレジットが高い武器ほど、ダメージが高く、有利に戦うことができます。しかし、単純に毎ラウンド所持しているクレジット分だけ装備を買えばいいわけではありません。ラウンドの勝利のためには、できるだけ味方と装備状況をそろえることが重要です。
クレジットが足りない場合は、次のラウンドで十分な武器を買いそろえるために、最小限の武器で戦うエコラウンドなどを挟みます。観戦画面でも、ラウンド開始時に装備状況が表示されるので、ぜひチェックしてみましょう。
エコラウンドは、当然ながら不利な戦いになります。もちろんラウンドを勝利できればベストですが、主な狙いは1人でも多くの相手を倒すこと。相手を倒せば、その分相手のクレジットを消費させられるため、次のラウンドを有利に迎えられます。
4つのロールに分かれる、個性豊かなエージェントたち
現在、『VALORANT』のエージェント(キャラクター)は、全部で19人。定期的に新たなエージェントが追加されており、そのたびにさまざまな戦略が生まれています。
個性的なアビリティを持つエージェントたちは、デュエリスト、コントローラー、イニシエーター、センチネルの4つのロールに分けられます。それぞれのロールの主な役割と該当するエージェントは、下記の通りです。
・デュエリスト
主な役割:先陣を切ってエリアに突入し、チームの最前線で戦う。
エージェント:ジェット、レイズ、フェニックス、レイナ、ヨル、ネオン
・コントローラー
主な役割:スモークを使って相手の視界を塞ぎ、味方を支援する。
エージェント:オーメン、ブリムストーン、ヴァイパー、アストラ
・イニシエーター
主な役割:敵の位置の把握や、相手への妨害を行う。
エージェント:ブリーチ、ソーヴァ、スカイ、KAY/O、フェイド
・センチネル
主な役割:相手を足止めし、エリアの守りを固める。
エージェント:セージ、サイファー、キルジョイ、チェンバー
■リーゼフェルトさんのワンポイント解説
オーソドックスなエージェント構成は、4つのロールを1人ずつ入れ、特定のロールを1人プラスする構成です。例えば、デュエリスト1人、コントローラー1人、イニシエーター1人、センチネル2人、などですね。
どのロールを2人以上にするかは、チームの戦略やマップの特徴によってさまざま。観戦する際は、どのロールを2人以上にしているのかをチェックすると、そのチームの狙いがわかりやすくなるでしょう。例えば、デュエリストが2人なら攻撃的な構成、センチネルが2人なら防衛的な構成だと言えます。
そのほか、普段あまり大会でピックされないエージェントや、追加されたばかりの新エージェントがピックされた場合は、そこが見どころになりますね。これまでは見られなかった新しい戦術が展開される可能性が高いので、注目したいポイントです。
7つのマップが持つ特徴と、マップ選択のルール
現在、『VALORANT』には7つのマップが存在します。正式リリース時には、スプリット、ヘイヴン、バインド、アセントの4つでしたが、その後、アイスボックス、ブリーズ、フラクチャーが順に追加されました。各マップの主な特徴やギミックは、下記の通りです。
・スプリット:マップ中央が高台になっており、高低差が大きい。
・ヘイヴン:A~Cまで3カ所のサイトがある。
・バインド:一方通行のテレポーター(ワープ)がある。
・アセント:開閉できるシャッターがある。
・アイスボックス:前後移動のジップラインがあり、高低差も大きい。
・ブリーズ:広大なマップで、交戦距離が長い。
・フラクチャー:マップ中央を横断するジップラインがある。
大会におけるマップ選択のルールは、何本先取で行われるかによって異なりますが、基本的には、両チームがマップのバン(禁止)とピック(選択)を順に行います。ピックされたマップでは、そのマップを選んだチームの相手チームが、攻守どちらのサイドからスタートするかを決定します。
なお、「VALORANT Champions Tour」(以下、VCT)の国内大会では、主にBo3(3マップ2本先取)が採用されており、Playoffsの決勝のみBo5(5マップ3本先取)で行われます。
■リーゼフェルトさんのワンポイント解説
マップ選択でバンを行う際は、自分たちが苦手とするマップや準備が不足しているマップ、もしくは相手チームが得意とするマップをバンするのが基本です。どちらの理由でバンしたのか、予想しながら観戦できるとおもしろいですね。
また、ランクマッチなどでは、アタッカーサイドが有利だとされるマップを「攻めマップ」、ディフェンダーサイドが有利だとされるマップを「守りマップ」と言うことがありますが、プロシーンにおいては、それほど大きな影響はないと考えられます。
たしかに、マップによる攻めやすさや守りやすさはありますが、プロシーンではそれに対する十分な対応策が練られています。そのうえで、いかにチームの練度を高められているか、どれだけ戦術の手札を持っているか、などが勝敗につながると言えるでしょう。
大会ならではの観戦画面の見方をチェックしよう
大会の観戦画面では、アタッカーサイドが赤、ディフェンダーサイドが緑で表示されます。画面右上には、誰がどの武器で誰を倒したかを示すキルログが、画面左上には、マップ上のどこに誰がいるかを示すミニマップが表示されています。
また、プレイヤー視点が映されている場合は、画面下側にプレイヤー名が表示されます。さらに、画面下側の両サイドには、そのラウンドで生存しているプレイヤーが表示され、所持している武器や残り体力などの情報がわかるようになっています。
(画面左上)
・この試合で使われるマップと結果
・ミニマップ
(画面上)
・ラウンド取得数
・ラウンド残り時間
・スパイク設置状況
・マップ取得数
(画面右上)
・キルログ
(画面下)
・視点が映されているプレイヤーの名前
・プレイヤーの生存状況と、所持している武器や残り体力など
■リーゼフェルトさんのワンポイント解説
大会配信では、主にプレイヤー視点を切り替えながら画面が映し出されます。しかし、今映されている視点で起きている撃ち合い以外に、別のところでも戦闘が起きている場合があります。
右上のキルログや左上のミニマップには、今映っている視点のほかにも、さまざまな情報がつまっています。観戦に慣れてきたら、キルログやミニマップもチェックできるようになると、より戦況を把握したうえで、さらにおもしろく観戦できるようになるでしょう。
「VALORANT Champions Tour」(VCT)とは?
『VALORANT』の公式大会である「VCT」は、地域大会の「Challengers」、国際大会の「Masters」、そして世界王者を決める世界大会の「Champions」の3段階で構成されます。日本では、「Challengers」は国内大会として行われ、優勝チームが国際大会「Masters」への出場権を獲得します。
2022年の「Challengers」と「Masters」の開催は、年2回。この「Challengers」と「Masters」の戦績に応じてサーキットポイントが付与され、その順位に応じて地域ごとに世界大会「Champions」への出場チームが決定します。
また、8月に各地域で開催される「ラストチャンス予選」(以下、LCQ)でも、「Champions」への出場権を獲得できます。今後予定されているVCTの開催スケジュールは、下記の通りです。
・6月:「Challengers 2」
・7月:「Masters 2」(デンマーク・コペンハーゲンにて開催)
・8月:「LCQ」(日本は、日本と韓国のAPAC North地域で出場)
・9月:「Champions」
■リーゼフェルトさんのワンポイント解説
日本国内の「Challengers」の最大の見どころは、やはり「ZETA」を打ち破るチームが現れるかどうかでしょう。日本から国際大会の「Masters」に出場できるチームは、わずか1チームのみ。この1枠をかけて、国内プロチームによる熾烈な争いが繰り広げられます。
そして、国際大会の「Masters」や世界王者を決める「Champions」には、各地域を代表する強豪チームが集結します。そのなかで、前回ベスト3まで上りつめた日本チームが、次はどのような結果を残すのか、世界から注目が集まっていると言えます。
『VALORANT』の国際大会は、各地域の代表チームの入れ替わりも激しく、まだ絶対的な王者と言えるチームは存在しません。次はどの地域のチームが活躍するのか、なかなか予想がつかないのもおもしろいところです。
直近では、国内大会「VCT 2022 Stage2 Challengers」の最終週となるPlayoffs Day4~5が、さいたまスーパーアリーナを会場として、有観客オフラインで開催されることが発表されました。史上最大規模で行われるオフライン大会での戦いを、ぜひお見逃しなく!
記事に使用した大会配信アーカイブ「VCT Masters Reykjavík 2022 — Group Stage Day4」
記事に使用した大会配信アーカイブ「VCT Masters Reykjavík 2022 – Bracket Stage Day10」