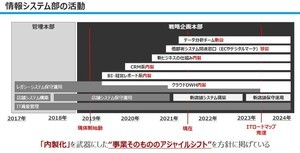MBDで大幅な効率化に成功
今、マツダにはもう1つ、開発プロセスの革新に向けた一番ピンがある。冒頭で紹介したMBDだ。
従来の開発は、試作してはテストを行い、問題が出れば次期試作で改善するという流れで行われていた。
実機を使った試験で全ての問題が出てくることはなく、ロバスト性(環境の変化に対する頑強性)が不足し、品質問題の発生につながってしまう。すると、慢性的な工数不足に陥り、次の開発プロジェクトへの人員配置が遅れ、結果としてコスト高になる。また、工数不足により開発チームがチャレンジを避けるようになれば、次第に技術力は低下し、人材育成も進まないという悪循環を抱えることにもなる。
「こんな状況では、優秀な人材を先行開発に回そうという発想は出てきません」(人見氏)
この課題を解決すべくマツダが取り組んだのが、MBDだった。
MBDとは、開発における一連の流れを全て「モデル」を使って行う考え方である。まずは、前段で述べた7つの制御因子間を2次制御因子、3次制御因子と掘り下げ、それらがCAE(Computer Aided Engineering:コンピュータで開発をシミュレーションするシステム)でどこまで検討可能であるか、検証を進めていった。その結果、年を経るごとに検証率は急上昇し、信頼度も上がっていったという。
加えて取り入れたのが、コモンアーキテクチャ構想だ。
部品の共通化よりも、もっと本質的な部分を共通化するというもので、エンジンの開発で膨大な時間をかけていた「適合」(エンジンのコンピュータに教え込む作業)に適用した。空気の流動や燃料の噴霧といったパラメータをCAEで計算可能にし、エンジンの排気量に関わらず燃焼の特性を共通化することで、適合の開発効率が大幅に向上したという。
「以前なら、実車を使った適合率は75%くらいだったところが、MBDを導入したことで今は机上で75%くらいまでに持っていけるようになり、さらに95%くらいまで突き詰められるようになったのです」(人見氏)
MBDの効果は絶大だった。開発における車両の試作台数は大幅に削減できるようになり、開発生産性は15年前と比べて2~3倍に向上したという。技術がどんどんと高度化していく中にあって、これは大きな成果だ。
効率化と高品質化が可能になったことで、コストの低下や収益の向上にもつながり、仕事の円滑化、長時間労働の削減といったさまざまな課題解決にもつながった。何よりも、「次世代に向けての投資を行う余裕ができたことが大きい」と人見氏は言う。
まさに、MBDこそが、開発プロセス改善における一番ピンだったというわけだ。
パラダイムシフトで新規参入者に備えよ
これまでの自動車業界は、数年に一度のペースで大きな投資をしてフルモデルチェンジを行うというハード中心の機能進化がメインだった。他社が実装した機能を自社の車に実装したり、ノウハウを手の内化することで低コスト化を進めたりした。それらは堅実ではあるが、「独自の顧客価値を創出しているとは言えない仕事だった」と人見氏は振り返り、次のように指摘する。
「ITジャイアントなどの新規参入者は、常に投資に対して生まれる“お客さま価値”の最大化を目指しています。そして、従来の自動車業界が時間とお金をかけてやってきた“製品の形を作る、形を変える”という作業は外注しています。(従来のやり方で)こうした新規参入者に勝てるでしょうか」(人見氏)
だからこそ、と人見氏は続ける。
「極端かもしれませんが、この脅威を利用してパラダイムシフトを起こさなければなりません。独自の価値を生む部分――すなわち一番ピンを選択し、時間とお金を集中させるのです。やることを減らした上で、デジタルで効率化し、独自価値創出にもデジタルを使う。これにより実現するトランスフォーメーションこそが、デジタルトランスフォーメーション(DX)なのです」(人見氏)
かつて、苦境に立たされたマツダの起死回生の一手となった「一番ピンの選択と集中」。多くの課題に振り回されることなく、課題の鎖をつなぐポイントを冷静に見切って投資したことが、現在の成功につながった。
一番ピンの重要性は、何も自動車業界だけの話ではない。急激に変化するビジネスシーンで生き残っていくために、あらゆる業種において重要になる考え方だ。マツダの事例を参考に、改めて自社が抱える課題の“一番ピン”を見極めてみてはいかがだろうか。