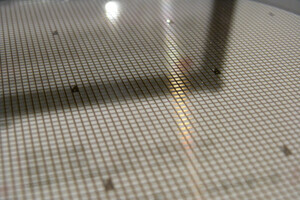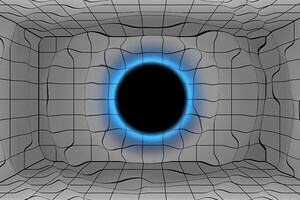名古屋大学(名大)は1月12日、旧人と新人というふたつの人類集団の空間分布動態を表現すると同時に、集団間の資源競争による人口密度の変化を示す数理モデル「生態文化分布拡大モデル」を用いた人類進化史の説明に成功したと発表した。
同成果は、名大博物館・大学院環境学研究科の門脇誠二講師、明治大学 総合数理学部の若野友一郞教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、科学誌「Quaternary International」にオンライン掲載された。
ここ最近10年間の人類進化史の研究における進展はめざましく、現在の中学校や高校の歴史や生物の教科書が追いつかない状況となっている。それら教科書では、我々ホモ・サピエンスこと新人は、ネアンデルタール人などのさまざまな旧人よりもあとに登場し、より発展した文化を最初から持っていたと説明されている。しかし、もはや大きな更新が必要だという。
まず新人の登場時期が、約30万年前から約4万年前の間で、旧人や原人の一部と同時期であることが明らかとなってきた。またアフリカからユーラシアへと拡散した新人は、拡散先にいた旧人のネアンデルタール人やデニソワ人と共存・交雑していたことが、古代DNA研究により示された(実際、ネアンデルタール人など旧人のDNAを受け継ぐ現代人も少なくない)。その当時の新人は旧人と同様の石器を用いて、同じように狩猟生活を送っていたことが遺跡調査から確かめられている。
そして約5万年前から約4万年前になると、新人はユーラシアのステップや高山地帯、極北地域、南方の熱帯雨林や海洋諸島域などさまざまな地域に拡散し、それぞれの環境に敵した資源利用や道具の製作などが行われるようになった。
このように、旧石器時代における新人の拡散と旧人との関係、そして文化進化には大きく2段階があるということが、経験的記録からわかってきた。しかし、そのような2段階がなぜ生じたのかについては、謎のままだったのである。その謎に対して初めての理論的説明となるのが、今回の研究成果である生態文化分布拡大モデルだ。
-

新人が出アフリカとユーラシアへの拡散を示す模式図。第1波では、小規模な新人集団がシンプルな技術で拡散し、旧人と交流・交雑した。第2波では、環境収容力に寄与する技術の発達に支えられて新人集団が増加し、旧人を同化・吸収した。ふたつの拡散波に対応する考古記録の年代はka(千年前)で示されている。左下の挿図グラフは、生態文化分布拡大モデルのスナップショット。赤線が新人の分布を示し、青線が旧人の分布を示す。第1波では両集団の人口が均衡するのに対し、第2波の場所では新人が急増した一方で旧人は現象・絶滅している (出所:名大プレスリリースPDF)
同モデルは、新人と旧人というふたつの人類集団の空間的分布動態を、反応拡散方程式によって表現すると共に、集団間の資源競争による人口密度の変化を示したものだ。また人口密度は、文化(環境収容力に寄与する技術)とフィードバック関係を持つように設定されているという。
このモデルを用いたシミュレーションの結果、人口密度と文化にふたつの状態が生じることが判明した。ひとつは、新人と旧人の集団が生態学的ニッチの違いにより共存する「低人口・低文化」状態だ(第1波)。そしてふたつ目が、新人の集団において、環境収容力に寄与する技術が人口密度と共に高まり、一方の旧人集団は減少する状態である(第2波)。
このモデルが示す第1波は、新人が初めてアフリカを出て西アジアに拡散した段階や、西アジアからヨーロッパ、北アジア、そして南ユーラシアにさらに拡散した段階に相当するという。各地で年代は異なるが、約19万年前から約4.5万年前までの間のことだ。
この時期は、ネアンデルタール人と同じ石器技術(ルヴァロワ方式)や、それに類似した石器技術(上部旧石器時代初期)が用いられていた。この段階では新人と旧人の間で文化の差は小さく、小規模な新人集団が旧人とのニッチの違いを利用して分布範囲を拡大していったと説明される。文化差が小さいため、交流・交雑があったことも理解できるという。
次の第2波は、新人が各地の環境に応じた資源利用を発達させ、人口を増加させた段階に相当する。たとえば欧州や西・中央・北アジアでは、小石刃と呼ばれる石器が多用されるようになった。小石刃は投擲具(とうてきぐ)などに用いられていたと考えられている。
また南方では、熱帯雨林のたとえばサルなどの動物や、植物資源を食料や道具素材に利用した。そして海洋諸島域では航海技術を発達させてたくさんの島々を開拓し、マグロ漁などの遠洋漁を含む海産資源の獲得を増加させた。こうした技術行動の発達にさせられて増加した新人集団が、旧人のニッチにも深く侵入することにより、旧人が同化・吸収されてしまったと説明することができるという。
今回の研究は、現象数理学と考古学という珍しい組み合わせの共同研究の成果だ。考古学による人類史の研究は、遺跡調査から得られる経験的証拠を積み重ねて過去の人々の文化史を構築する。また古人類学や古代DNA研究の進展により、過去の人類集団の系統や移動、交流に関する証拠が急増しているという。
今回の研究による数理モデルの「生態文化分布拡大モデル」は、人類進化しに関する他分野の研究成果を関連付けながら整理し、包括的な人類進化のプロセスを解析する理論的基盤とする。また今回の研究は、数理科学と人文科学の融合という、従来にない新しい研究分野を非理開くことが期待されるとしている。