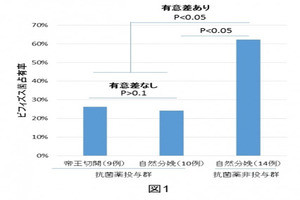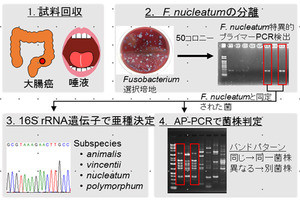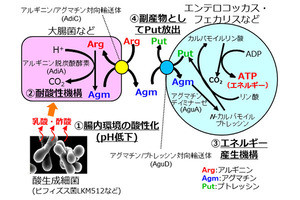沖縄科学技術大学院大学(OIST)は、哺乳類の腸管表面の粘液層に定住する腸内細菌が、「キチン」を主要素としたバリア免疫機構を失うことと引換えに成立していること、また、それが動物進化の観点から見ると新しい存在であることが明らかになったと発表した。
同成果は、マリンゲノミックスユニットの中島啓介研究員らの研究グループによるもの。詳細は英国科学雑誌「Nature Communications」に掲載された。
ヒトを含めた哺乳類の消化管には多様な細菌が存在し、消化吸収はもちろん、神経系や免疫系の発達においても重要な役割を果たすことが知られている。こういった腸内細菌は腸管表面に定住し、粘液層の主構成タンパクであるゲル形成ムチンの糖鎖部分を消費しているとされ、この役割は多数の動物に共通しているものと考えられてきた。
一方、昆虫などいくつかの無脊椎動物において、腸管表面から分泌されるキチンナノファイバーが網目状のチューブ(囲食膜)を形成し、栄養分は通過するが細菌は通過できないという、バリア免疫機構として機能することがわかっていた。
哺乳類の粘液層と無脊椎相物の囲食膜の働きは、腸内細菌への対処や消化吸収への貢献という意味ではよく似ているものの、それぞれの動物グループで成立した別個な存在と見なされてきた。そこで、無脊椎動物の昆虫と哺乳類の間を埋める知見が得られるとの考えから、脊椎動物を対象に研究は進められた。
まず、ホヤにおいて、昆虫同様に囲食膜の存在し、これが腸内細菌に対するバリアとして機能することを確認した上で、同様の構造がナメクジウオ・ヌタウナギ・真骨魚にも存在することを確認した。
これまで、真骨魚の腸管表面は哺乳類同様に粘液層に覆われ、そこには腸内細菌が定住していると考えられてきたが、今回の研究によると、囲食膜の存在により、粘液層に直接触れることはなかったという。これに対し、哺乳類であるマウスの腸管にはキチンは検出されず、粘液層に大量の腸内細菌が定住していた。
この結果から、キチンによるバリア免疫機構は、脊椎動物にとっては祖先的な特徴に過ぎないとされ、今もなお多くの動物グループで保持されているものの、少なくとも哺乳類においてはそれは失われ、初めて腸内細菌による粘液層への定住が可能になったという説が得られるという。
研究グループは、今回の成果は、動物とその腸内細菌の共生関係がどのように成立したかという進化的な疑問への回答であるとともに、哺乳類の腸内細菌の特殊性を説明するものになるとしており、同成果が、ヒトの予防医学や、畜産や魚の養殖などの研究に役立つことが期待されるとしている。