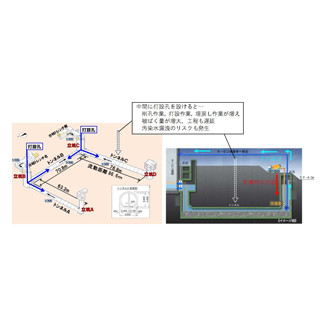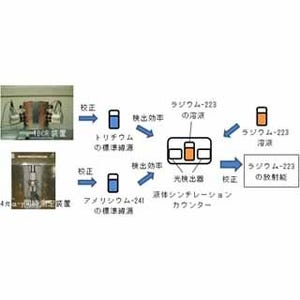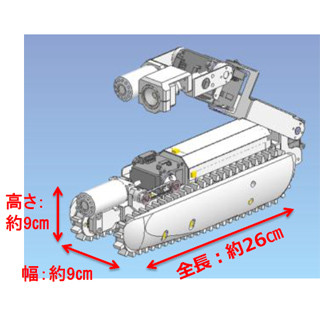九州大学(九大)は、福島県の土壌から福島第一原発のメルトダウン時に形成された核燃料成分であるウラン(U)酸化物を含む粒子を発見し、超高分解能電子顕微鏡を駆使した原子レベルでの解析に成功したと発表した。
同成果は筑波大学、東京工業大学、Manchester大学、Nantes大学、Stanford大学とともに原子力災害からの復興に貢献することを目指して行われた共同研究の成果であり、九州大学大学院 理学研究院 宇都宮聡 准教授、理学府修士の落合朝須美氏らの研究グループによるもの。詳細は、アメリカ化学会誌「Environmental Science & Technology」に掲載された。
2011年の福島原子力災害により放出された放射性セシウムの一部は水に溶けにくい高濃度放射性セシウム含有微粒子(CsMP)として環境中に放出された。現在も残るCsMP自体がメルトダウン時の炉内の情報をそのまま記録している媒体となる。
研究グループは今回、球面収差補正透過型電子顕微鏡を駆使して、CsMPとともに存在する2種類のウラン酸化物ナノ粒子を分析した。その結果、燃料の主成分であるUO2+Xの構造をもつ最大70 nmの大きさのナノ結晶が鉄酸化物に包まれた状態、燃料の被覆材であるジルコニウム(Zr)との共融混合物(U、Zr)O2の状態として存在することが明らかになり、メルトダウン時に炉内で溶けた燃料がどのような挙動をとったのか、その一部を把握することができた。
-

左上図は、U-Zr酸化物固溶体ナノ粒子の電子顕微鏡像と元素マップ。左下図は、Fe酸化物ナノ粒子とそれに含有されたU酸化物ナノ粒子の電子顕微鏡像。右図は、拡大した高分解能原子像。鉄原子の配列とウラン原子の配列が連なっていることが分かる (出所:九州大学Webサイト)
研究グループは同成果に関して、「まだ放射線量が高くて近づくことのできない炉内に残された燃料デブリ(溶けた燃料と原子炉構造物の混合物)の性質を部分的にだが示すもの。これから長期にわたる廃炉工程においてもっとも困難な工程である燃料の取り出しのために必要なデブリ性状把握に貢献できると期待される」とコメントしている。