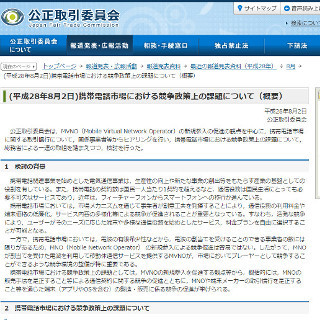減価償却方法の変更も決算に与えた影響は大きい
さらに、2016年度第1四半期については、減価償却方法の変更等による影響(250億円)と、「ずっとくりこし」等による影響(180億円)、合計430億円がプラス要因となっている。
このうち後者については、2015年6月に導入されたサービスで、それまでの「ファミリー割引」がパケットの未使用繰り越し分を2カ月まで保持できたのに対し、「ずっとくりこし」では上限額までは期間無制限で保持できるようになったというもの。一見改善に見えるが、上限額を超えた繰り越し分は消滅してしまうため、実質ドコモの利益になる。この変更分だけで180億円もの「利益」が出ているというのは、企業的にはプラスだが、ユーザーから見るとあまり嬉しい感じはしないだろう。いずれにしてもこうした細かな部分でも利益を稼げる体質になっているようだ。
なお、加藤前社長時代から引き継いでいる経営の効率化・低コスト化が功を奏し、営業費用が321億円減と大きくコストダウンに成功している。LTE-Advancedのさらなる高速化や基地の高度化、5Gの開発といったインフラ投資は引き続き行なわれている中でこれだけのコストダウンを両立できるあたりが、同社の好調ぶりを物語っているようだ。
通信事業に今は影響なし
総務省のタスクフォースなどの影響により、新規/MNPでの端末購入費用が上がったことで、収益にもマイナスの影響があるかと思われたが、端末の売れ行きは落ちても、通信事業そのものには大きな影響はないようだ。
ごく一部を除けば通信プランそのものにメスが入っていないのだから当然ではあるだろうが、ドコモの場合はMNP転出が減ったことやiPhoneの扱いができるようになったことなど、ここしばらくの動きがことごとくプラスに回っているように見える。成長著しいMVNOの台頭も、結果的にはほとんどがドコモ回線を使う=ドコモの収益になるわけで、同社の好調ぶりには生半可なことでは影響を与えにくいといえそうだ。