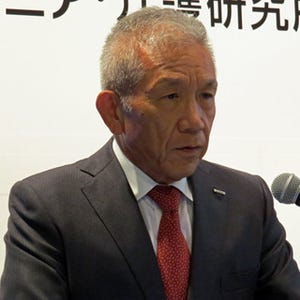進研ゼミプラスの最大の特徴は、BYODを使ったオンライン学習が行えること。個人所有のiPadを使って学習できるようになり、加えてこれまで取り組んできたテキスト用紙と先生による添削も併用できる。オンライン学習とテキスト用紙による学習を組み合わせることで、ライバル企業との差別化が図れるのだ。なお、同サービスのスタートにより、BenePaは終了させる方針だ。
さらに、2021年から導入される大学入試改革への対応も迫られる。これまでの“知識の暗記・再生”という学習ではなく、“思考力・判断力・表現力”が試される試験になるという。そうした学力を伸ばせるプログラムをいかに訴求するかも課題となる。
前述したとおり、国内教育事業はベネッセにとって最大の柱。個人情報流出事件以降、離れていった消費者をいかに取り返せるかが最大のテーマといえる。現在の生活様式にあった学習方法に進化した進研ゼミプラスに、これまで40年以上積み重ねてきた進研ゼミのノウハウをいかに生かせるか……福原新社長の手腕に期待がかかる。

|
進研ゼミプラスのキャッチは「Good-bye,進研ゼミ Hello,学び革命。」と刺激的なもの。特に「さようなら進研ゼミ」という意味を込めたところにベネッセの意気込みがうかがえる(ベネッセホームページより) |
ベネッセの今後を支える注目事業
“脱進研ゼミ”を進めなくてはならないのも新社長の役目だろう。“進研ゼミ立て直し”と“脱進研ゼミ”とは矛盾しているのではないかと思われるかもしれないが、国内教育事業にこれまで頼り切ってきた体制を変えていかなくてはならない。その期待を背負うのが海外事業開発と介護・保育事業部門だ。
海外事業開発の売上高は約271億円と、グループ全体の売上高からみると、まだまだ小さい。だが、前期比29.1%という高い伸び率で増収。これは、中国での通信教育講座の在籍者数が増えたことなどが大きな要因だ。中国といえば人口抑制策「一人っ子政策」が緩和される方針で、今後、教育を必要とする層が増えるとみられている。そうした需要をうまく取り込めれば、将来、国内教育事業と並ぶ柱になれるだろう。
一方、介護・保育事業への期待も大きい。ご存じのとおり、日本は“超高齢化社会”に向かっており、介護に対する需要が増大するのは明らかだ。保育についても、女性活躍推進法が施行され、出産後に職場に戻る女性が増えると容易に予想でき、その必要性が高まっている。こちらの介護・保育セグメントは約950億円の売上高となっており、すでにベネッセの主力事業といってもよいだろう。
原田氏に話を戻そう。進研ゼミの改革は氏の悲願だったと聞く。生え抜きの経営者の場合、それまで長いこと企業を支えてきた中核事業に大なたを振るうのは二の足を踏んでしまいそうだ。だが、進研ゼミを大きくリニューアルしたこと、2年で経営から退くことを決めたこと、これらは“プロ経営者”である原田氏ならではの判断の早さといえるのではないだろうか。