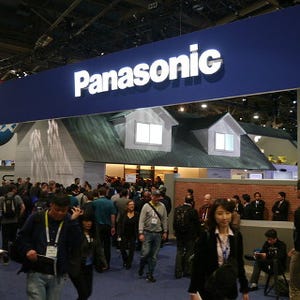日本企業が苦手な「サービスとの連携」
「ハードウェアに独自の機能を載せて進化させる」ことは、日本企業の得意分野ではある。ただ、今回のCESでは、東芝やシャープが出展していないこともあり、白物家電における日本の存在感が薄まった。
さらに、日本企業が苦手な「サービスとの連携」が必要になってくると、日本企業がIoT時代を先導するのは、このままでは難しいだろう。ソニーは白物家電を持たないため、今回もIoTに関する言及がほとんどなかった。Life Space UXがそれに近い存在かもしれないが、いまいちサービスとの連携に欠ける。
Samsung、LGの韓国勢も、「サービスとの連携」の点で攻めあぐねているように見える。スマートフォンがハブになることから、Google、Appleのプラットフォーマーの動向は気になるし、AppleのHomeKitのようなデバイス連携技術が重要になってくるだろう。ただ、Appleはサービス開発では特別存在感がないし、Googleは冗談を抜きにしても「家庭的」ではない。
IoTはあらゆるものがインターネットに繋がる分、サービスが多岐にわたり、そのサービス同士が連携したものになるはずだ。CESは家電を中心とした展示会であるため、サービスも家庭向けのものが望まれるだろう。Netflixがテレビの視聴スタイルを変え、CESの基調講演に立つように、新たな勢力が家庭内のIoT普及の起爆剤になる可能性はある。
それが家電メーカーになるのか、新興のサービス企業がその座を奪うのか、それとも新たなメーカーが現れるのか、今回のCESではそれがまだ見えてきていない。今年の9月、ベルリンで開催されるIFAでは、白物家電のIoT化がどう進展しているのか、そして来年のCESでは新たな動きが見られるのか。
今年のCESは、IoTの今後を占う以前の段階。まだ混沌としてIoTが無秩序に存在していただけ、そんな印象だった。