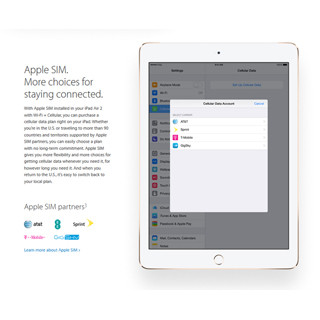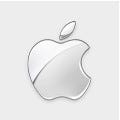NFCをなんとかしてほしい
もう1つ、気になるのはNFCだ。
Appleは8月11日に、近距離無線通信規格の策定を行っているNFC Forumのボードメンバーとして参画している。今後のiPhoneでNFCを活用したコミュニケーションや便利な機能の追加などが行われることに期待を寄せている。
一般的なNFC搭載のスマートフォンでは、同様にNFCを搭載したBluetoothワイヤレスヘッドフォンと近づけるだけでペアリングを行ったり、テレビにスマホを近づければ、スマホの映像を大画面で見られたりする機能を実現済みだ。
iPhone 6とApple WatchにはすでにNFCが搭載されているが、現状Apple Payにしか利用できない仕組みとなっている。前述の例からすれば、ものめずらしいアニメーションの二次元コードをiPhoneのカメラで撮影してペアリングするのではなく、iPhoneとApple Watchを近づけて設定を完了できてしかるべきなのだ。
技術としてはNFCを利用するが、Appleとして、何らかの新しい規格名をつけて、デバイス間の近距離通信に新たな付加価値をつけていくのではないか、と推測している。 スマートフォンは言うまでもなく、既に生活の一部として多くの人が利用するようになった。そのためか、本稿を書き進めてきた筆者としても、めざましい進化を求め続けているわけでもないことに気づかされた。
求めていることが、意外と地味だったからだ。
スマートフォン全体でいえば、バッテリーの問題が重要だ。処理速度と通信速度の向上を行いながら、しかし消費電力を少なくとどめる努力が必要になる。
それ以外はスマートフォンそのものの問題ではなくなっている。例えばカメラは高画素数であることに越したことはないが、写真を保存しておくスマホ本体あるいはクラウドの容量のほうが心配だ。通信にしても、通信速度以上に高止まりしているデータ通信料金が、不自由を作り出している。
こうした理想と現実の乖離が、デバイスのスペック向上によってより大きくなっており、デバイスメーカーがスペックをアピールできる領域が少なくなってきた。
スペック競争に乗らないようにしてきたAppleにとっては願ってもない展開だが、デバイスの進化に関しても、前編で触れた通り、外部要因によってユーザーへの訴求が削がれ始めている点は、難しさを感じざるを得ない。

|
松村太郎(まつむらたろう)
1980年生まれ・米国カリフォルニア州バークレー在住のジャーナリスト・著者。慶應義塾大学政策・メディア研究科修士課程修了。慶應義塾大学SFC研究所上席所員(訪問)、キャスタリア株式会社取締役研究責任者、ビジネス・ブレークスルー大学講師。近著に「LinkedInスタートブック」(日経BP刊)、「スマートフォン新時代」(NTT出版刊)、「ソーシャルラーニング入門」(日経BP刊)など。ウェブサイトはこちら / Twitter @taromatsumura