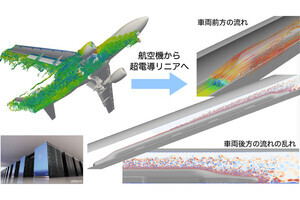セミトランスペアレント・デザイン(通称:セミトラ)は、ネット上の空間と現実の空間を結びつけ、相互に影響を与え合うデザイニングで知られている。彼らは多くのウェブ広告を制作してきたが、いずれも国内外から高い評価を得ている。今回、その一例として、SONY BRAVIA のキャンペーンサイト「Live Color Wall Project」の紹介を行った。
Guest 01 田中良治(セミトランスペアレント・デザイン)
2003年活動開始。デザイナー/デバイスデベロッパー/プログラマーからなるデザインチーム。Web、インスタレーション、写真、映像など、メディアの形態を問わない多くの作品を制作/発表し続ける。カンヌ国際広告祭、クリオ賞、One Show、New York ADC、D&ADなどの広告賞を多数受賞。
http://www.semitransparentdesign.com/
「サイト上で配信されているCM映像から、ユーザーが色を抽出する仕組みになっています。抽出された色は、銀座にあるソニービルの外壁に反映される。つまり、ネット上のインタラクションが、リアルスペースに対しても機能する設計になっています」

|

|
|
SONY BRAVIA のキャンペーンサイト「Live Color Wall Project」。ユーザーがスポイトツールを使ってサイト上に流れるCM映像から色を抽出し、ソニー銀座ビルの色をリアルタイムに変えることができる |
|
田中は、グラフィックデザインとウェブデザインの違いを、こう整理する。前者の特性は「CMYK、高解像度、固定的(物質的)」といったキーワードで、後者の特性は「RGB、低解像度、流動的(インタラクティブ)」といったキーワードで表現することができるのだと。
「デザインに関わるようになった頃は、グラフィック的な表現をWebでも実現したいと考えていました。しかしWebの場合、良くも悪くも、テクノロジーに依存している部分が大きい。そこから逆に、Web独自の表現とは何なのかを、改めて考えるようになりました。グラフィックの従属から逃れるためには、どうすればよいのか。そのための試行錯誤を続けてきました」
2008年、セミトラはNTTインターコミュニケーションセンター(ICC)で、時間軸を持ったフォント「tFont」を発表する。これはランダムな光の点滅が、アルファベットの輪郭を示しているというもので、シャッタスピードを落として撮影すると、通常の文字として読める仕掛けになっている。

|

|
| Webの特性でもある「時間軸」をグラフィックデザインの基本である書体に適応する実験でもあった「tFont」。カメラで撮影することにより、田中氏の作成した文字自体が写真を撮影する人の手に委ねられるWeb的な面白さが生まれるという | |
「たとえば他の人が撮影したとすると、手ぶれを含め、文字未満と言いたくなるような、ちょっと不思議なかたちが現れてきます。こうしたオリジナルと二次創作のような関係性は、Webの特性を象徴しているものでもある。Web上の文化は、複製、あるいは、二次創作されることで、広まっていくものが多いのです」
2009年には、山口情報芸術センター(YCAM)で、時間とフォントというテーマを深化させ、インスタレーション「tFont/fTime」を展開。こちらも好評を博した。さらに、会場での映像をアーカイヴし、その中の素材を用いたプロジェクト「JAPANESE SUMMER NOISE T-SHIRTS」も実施した(エキソニモとのコラボレーション)。いずれも、流動的(インタラクティブ)であることを徹底的に可視化した試みだ。

|

|
|
1週間限定のプロジェクト「JAPANESE SUMMER NOISE T-SHIRTS」。YCAMで展示した書体をアーカイブし、Tシャツ上で再現。時間とともに書体が崩れ、購入者は好きなタイミング(崩れ具合)で購入することができる |
|
「いま、考えているのは、短期インタラクションから長期インタラクションへの移行。時間軸というものを設定し、そこからグラフィックデザインを捉え直すことで、固定的な目的に向かわない方法論があるのではないかと思っています。グラフィックが何らかのメッセージを伝えるためのものだとしたら、ウェブは複数の行為を同期的に発展/発散させることができる。そこから新しいコンテクストも生まれてくるのではないでしょうか」