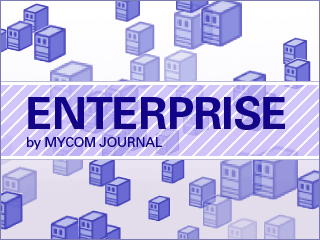周波数クランプ臨界導通モード(FCCrM)
周波数クランプCrM(FCCrM)は、ON Semiconductorが開発した独自技術で、NCP1605やNCP1631などのコントローラに組み込まれます。これらのコントローラは、最大周波数を設定する発振器を備えており、以下のように動作します。
- インダクタ電流が発振器の周期より長いときは臨界導通モードで動作。したがって、PFCステージは最もストレスの多い条件ではCrMで動作します
- 電流サイクルが短いときは固定周波数(DCM)で動作。スイッチング周波数は発振器周波数と同じです。
FCCrMコントローラは周波数をクランプするだけではありません。
CrM回路の周波数をクランプすると力率に大きく影響します。このため、FCCrMコントローラは、入力電流を適切に整形するために、DCM動作のオン時間も変調します。具体的に言えば、FCCrMコントローラは、各スイッチング期間にわたってデッドタイム相対持続時間を永続的にモニタし、この情報に基づいてオン時間を変調して補償を行います(詳細については、NCP1605またはNCP1631のデータシートを参照)。このように、FCCrM PFCステージでは、スイッチング周波数がクランプされても力率はほぼ1のままです。
より一般的には、これらのステージは、電力転送が不連続になることもなく力率も低下しないで、CrMからDCMおよびその逆方向に移行します。
ところで、このようなPFCステージはインダクタ値が十分に低く、電流サイクル周波数が周波数クランプより低く維持されている場合は、固定周波数で永久に動作することができます。ただし、これは推奨されるオプションではありません。デッドタイムのため、DCMは同じ供給電力でCrMの場合に比べてより高いピーク・インダクタ電流を必要とします。このため、DCMでは電流リップルが発生し、実効値レベルが大きくなり、大きな負荷条件で効率が低下し、インダクタおよびMOSFETに対してより高い電力ストレスが加わります。
他方、インダクタは最もストレスの高い条件でもCrMで動作し、軽負荷時およびACラインゼロ交差点付近ではDCMがスイッチング周波数を制限するように設計されます。このオプションはCrMとDCMの両方の利点を生かせます。
(最大)ピークおよび実効インダクタ電流はCrMモードの場合とほぼ同じです。これは、コンバータが最もストレスの高い条件(低ライン、全負荷)で動作するためです。この電流は次式で与えられます。

|

|
前述のように、システムが最低ACライン入力電圧、全負荷設計時、つまり最も厳しい条件のときに、正弦波の最高点においてCrMでシステムが動作するように、ブースト・インダクタを十分に大きくする必要があります。この式は、最小周波数を高くできることを除いてCrMの場合と同じです。実際、発振器周波数は一般に120kHzに設定され、最小周波数はこの値以下でなければなりません。例えば、マージンおよび最適効率のために、最小周波数((fsw)min)、 を約20%低く設定することができます(fn)。ここでは、100kHzを選択します。

|
1個の150-μH、EFD30コア・インダクタが、CrMのオプションに必要な2個のチョークの代わりに、この働きをします。