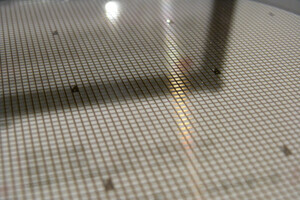同氏は富士通グループの新型インフルエンザ対策への取り組みも披露した。同グループは規模が大きいため感染者も少なくなく、4月末以降の対応からさまざまなノウハウが蓄積されているそうだ。
例えば、家庭内で新型インフルエンザ感染者と近距離で接触し、感染の疑いがある濃厚接触者の対処として、数日間の自宅待機をルールとしている企業も少なくないだろう。しかし、「現時点では、職場内での感染例や家族から従業員への感染例は極めて少なく、濃厚接触者の自宅待機の必要性は高いとは言えず、また、20代の若年層に感染が集中していることも明らかになっている」と同氏は説明した。
こうした事実を踏まえ、同グループでは当初策定されたBCPの内容を柔軟に変更しながら、現在の状況に最適化している。「新型インフルエンザ対策は長期戦となるため、"いかにその時点の環境変化に応じて柔軟な対応ができるか"がカギとなる。現時点での対策は低病原性の新型インフルエンザを対象としたものだが、これが高病原性であれば対応の仕方はまったく異なる」と同氏。さらに、「BCP自体は、"細かく作りすぎない"、"トレーニングを実施する"という2点が重要」と同氏は述べた。BCMにおいては、強力な対策本部機能も不可欠だという。
事業を継続するうえで必要な対応としては、次の5点が挙げられた。
- 事前に重要な業務を明確化
- 重要業務に携わる要員と要員の代替可否を可視化
- 重要な要員に対して発生早期の段階から、感染予防策(在宅勤務・時差出勤・作業場所の限定など)を実施
- 危機が発生した場合のシフト交替要員を事前にトレーニングし、発生早期の段階からシフト勤務を実施
- 事業所内での行動制限を設けることで、濃厚接触者の影響範囲を最小化
上記のうち、新型インフルエンザ対策という観点からは、「事前に重要な業務・業務に携わる要因を特定」が最重要と同氏は指摘した。同グループでは、社内外の実績に基づく300種類のテンプレートをライブラリ化した「新型インフルエンザ対応計画ライブラリ」を開発し、それをベースに新型インフルエンザ行動計画を策定している。
危機対応能力を強化するためのトレーニングは、BCP策定前に行うべきものと後に行うべきものとに分けられる。BCP策定前は経営者や組織構成員にBCPの必要性を気付かせ、策定後は「手順確認と徹底」、「検証と発展」を行う。
具体的なトレーニングには、災害模擬演習「モックディザスターエクササイズ」、手順書確認訓練「ウォークスルーエクササイズ」などがある。また、管理職に対し、メンバーリストを作成して、災害が発生したら、そのメンバーをどのように扱うかということをシミュレーションさせるというトレーニングも効果的だという。
伊藤氏は実際に巨大な富士通グループのBCPを管理しているという立場だけあり、その話もマニュアル通りではなく、リアリティに飛んでいて興味深かった。同氏が何度も口にしていたのが、「プランは細かく作りすぎるな」、「現状に応じて柔軟な対応をすべき」といったことだ。同グループもBCPを策定しつつも、試行錯誤で新型インフルエンザ対策を実施しているという。これから冬に入り、一部では新型インフルエンザが猛威を振るうと言われているが、何が起こっても事業が継続できるよう柔軟な体制を構築しておきたいものだ。