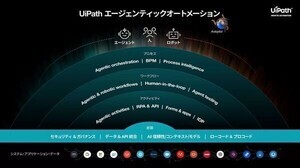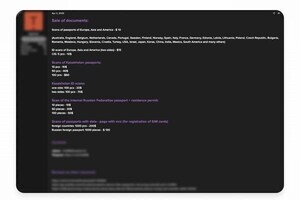限られた人員と予算で、地震や台風、豪雨など、未曾有の自然災害にどう備えていくべきか、多くの地方自治体が頭を悩ませている。NTT東日本グループは、各自治体に向け、インフラ面だけでなく、情報連係や住民の生活再建などのさまざまなソリューションを提供し、包括的な支援を行っている。
独自のノウハウで、自治体だけでなく地域住民の安心安全を守る
一口に防災といっても、備え方はさまざまだ。長きにわたり数々の災害復旧活動にあたってきたNTT東日本は「災害対応の5つのフェーズ」を提唱し、災害対策を5段階に細分化。被災地支援で培った知見を、独自の技術やアセットと組み合わせ、各フェーズでの防災ソリューションを展開している。
とはいえ、多くの自治体が限られた人員での対応を迫られる中、全てのフェーズにおいてソリューションを導入、活用することは難しい。そこで、防災のウィークポイントとなっている点はどこか、105個からなる質問項目でつくられたリスクアセスメント調査も実施しており、自治体ごとに特化したサポートも行っている。
なぜここまでのトータルサポートを実現できるのか。NTT東日本 基盤ビジネス推進部 担当課長の田中氏は、「東日本大震災で救えるはずの命を救えなかったという辛さを、多くの社員が身をもって実感しました。誰ひとり取り残さないための防災事業は、通信事業者としての私たちの使命です」と語る。
この5つのフェーズにおいて、災害発生時に地域住民の安全を左右するのが「意思決定支援」と「情報配信」におけるソリューションだ。発災後、地域住民の心身的負担に大きく影響する「災害復旧の下支え」におけるソリューションと併せて、担当者にポイントを伺った。
導入のしやすさから、災害発生時だけでなく平時での活用も広がる
-

東日本電信電話株式会社 ビジネスイノベーション本部 基盤ビジネス推進部 担当課長 田中 誉幸氏
地域住民の命を守るため、災害発生時にまず自治体に求められるのは「情報収集」「迅速な意思決定」だ。どこでどんな被害が起きているのか、被害情報を収集・整理し、自治体内で情報を共有することが災害対応の一歩となる。しかし、「今でもアナログな方法で行われている」と、基盤ビジネス推進部 担当課長の田中氏は語る。
「白地図に手書きで情報を書き込み、災害対策本部に行かないと同じ庁内でも情報がキャッチできないというお話しを数多くお聞きしました。情報連係が上手くできなければ、地域住民への情報提供や対応に遅れが生じる可能性があります。当社が提供する『地域防災支援システム powered by EYE-BOUSAI』は、関係機関や住民からの観測情報、被害情報などを地図上に重ね合わせ、被災状況を可視化することで、迅速な意思決定、情報提供を支援します」(田中氏)
こうしたシステムは災害時のみに利用されることが多く、発災時における活用への不安や、導入予算が確保しづらいという課題が立ちはだかる。「地域防災支援システム」は、ヘルプデスクや習熟支援等のサポートメニューをバンドル提供し、運用面での課題を払拭するとともに、災害対応の主要業務以外は、自治体の予算に応じてオプションにて機能を追加できるスタイルだ。また、同システムは、災害発生時だけでなく、平時での活用も可能だという。
「平時で活用されないシステムは、災害時も活用されません。地域防災支援システムは、道路陥没や鳥獣害の被害、感染症対応など、幅広い情報共有に活用いただけます」(田中氏)
地域防災支援システム powered by EYE-BOUSAI
災害発生時の情報を一元的に集約して可視化し、自治体の「意思決定支援」と「状況認識の統一」をサポートする総合防災情報システム。
被害情報などの一元集約や重要度や対応状況を俯瞰的に把握するクロノロジー機能、災害現場の場所・状況を把握する地図機能など、災害対応の主要業務をカバーする基本機能に加えて、NTT東日本によるサポートメニュー(ヘルプデスク、習熟支援など)もあわせて提供している。
通信事業者ならではの技術で、誰もが情報を受け取れるシステムを実現
-

(左)NTT東日本 ビジネスイノベーション本部 基盤ビジネス推進部 チーフ 吉田 直哉氏
(右)NTT東日本 ビジネスイノベーション本部 基盤ビジネス推進部 山口 洋平氏
自治体は、地域住民の命や財産を守るため、災害発生が予測される時点での避難誘導や発災後の安否確認を、適切かつ迅速に行うことが求められる。こうした災害時の情報伝達・収集をスムーズに実現するのが、同社が独自開発した「シン・オートコール」だ。東日本大震災で被災した岩手県陸前高田市と共同で開発したこのシステムについて、基盤ビジネス推進部 チーフの吉田氏はこう説明する。
「多くの自治体で防災行政無線が採用されていますが、雨風の影響で聞こえづらかったり、気密性の高い住居にいる場合は聞き損じてしまったりと、情報の伝達漏れの課題があります。SNSやメールなどによる伝達手段で補完しているものの、デジタルデバイスの操作に慣れていない高齢者などへの対応も課題でした。電話という誰もが使い慣れた情報伝達手段に着目したシン・オートコールなら、情報伝達・収集の漏れを減らすことが可能となり、"誰一人見逃さない防災"を実現できると考えています」(吉田氏)
通信事業者である同社だからこそ開発できたこのシステムは、電話を受けた住民が自分の肉声で安否を答えられる点が強みである。
「テスト段階ではダイヤル操作で回答してもらうシステムを構想していましたが、高齢者に体験してもらうと『スマホのダイヤルパッドの出し方が分からない』という声が多く、普段から慣れていない操作で必要な情報を伝達・収集することは難しいとわかりました。耳から離さず会話できるよう、声を認識する機能を開発したことで、通常の電話と変わらずご利用いただけます」(吉田氏)
架電時はAIによる音声だけでなく、録音した自治体職員などの声で発信することも可能だという。その使いやすさから災害時だけでなく、平時での活用も広がっていると、同部門の山口氏は語る。
「最近では、警察が特殊詐欺被害防止のための連絡に活用したり、介護福祉分野では自宅で過ごす高齢者の見守り用として活用したりと、さまざまな観点での採用も増えています。シンプルな作りだからこそ、フェーズフリーでご利用いただいています」(山口氏)
シン・オートコール
クラウド・AI技術と「電話」を組み合わせた、NTT東日本独自の自動音声一斉配信システム。自動架電にとどまらず、応対をDX化することでデータ活用できるほか、他サービスとの連携も可能。情報の発信者、受信者と仕組みを作り、地域と共に「進化」を目指した、新たなオートコールソリューション。
被災した自治体の声を反映したシステムで、迅速な生活再建支援を可能に
-

(左)NTT東日本 ビジネスイノベーション本部 基盤ビジネス推進部 白石 晶穂氏
(右)NTT東日本 ビジネスイノベーション本部 基盤ビジネス推進部 青木 薫乃氏
災害後、多くの被災者にとって「元の生活に戻れるか」という不安は大きい。特にり災証明書の発行や被災者台帳作成は、災害対策基本法の改正により迅速な対応が自治体の義務となっているが、「現場ではさまざまな要因が重なり、スムーズな対応が難しい」と、同システムのSEである白石氏は説明する。
「特に課題となるのが、建物被害の認定調査、調査結果の登録とデータ化です。昨年の能登半島地震でも道路の陥没により、建物被害の確認が難しいケースが多くありました。我々のチームのメンバーも1月4日から現地に入り支援を行いましたが、被災地の中には人が立ち入れない場所もあり、調査の効率化が課題でした。そこで、ドローンと200台のタブレットを使って建物調査を行い、り災証明を迅速に届けることができました」(白石氏)
NTT東日本では、新潟県中越地震や東日本大震災を教訓に「Bizひかりクラウド 被災者生活再建支援システム」を開発。10年以上にわたり、改善を重ねてきた。同システムの営業担当である青木氏は、各自治体の声を聞き、アップデートしていく意義についてこう語る。
「被災を経験したことがない自治体から、『有事にどう使えばいいかわからない』という声を多くいただきます。そこで、自治体同士で活用方法を共有できるユーザーカンファレンスを毎年開催し、実際に被災された自治体の方をお招きして、システムの運用方法や災害時はどのように活用したかをお話しいただいています。私たちもそこで得たご要望やご意見をシステムに反映しています」(青木氏)
同システムを導入している自治体は多いことから、災害時に自治体同士の応援・受援が円滑にできたという評価も届いているという。
Bizひかりクラウド 被災者生活再建支援システム
被災者の生活再建支援業務を円滑に遂行するクラウドサービス。建物被害認定調査、り災証明書発行、被災者台帳管理など多岐にわたる業務を一気通貫で対応できることで、迅速に地域住民の生活支援にあたれるほか、自治体職員の業務軽減にも寄与できる。全国310の自治体で導入(人口カバー率43%)されており、120以上の被災地で活用された。
「地域に根付く防災」を目指し、新たに防災研究所を設立
同社では、5つのフェーズに沿った防災ソリューションの展開に加え、「誰ひとり取り残さない防災」を実現すべく、防災研究活動も本格化。「地域で活用される防災をどう構築していくか」をミッションに、2025年4月1日にNTT東日本 防災研究所を新設する。
具体的な研究内容について、株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイーの杉山氏はこう説明する。
「例えば、避難所へ行くよう呼びかけても住民が避難しないケースがあることから、発災直後の『命を守る避難誘導』の実現に向けた研究を行っています。避難の仕組みをどう整えていくか、新しい避難の形はないか、プロトタイプを山形県置賜地域と協力して検証を始めています。他にも先端テクノロジーを活用した被害・避難状況の予測や、自治体の災害対策本部運営の最適化に関する研究を行っています」(杉山氏)
ただ研究するだけで終わるのではなく、実際に各自治体が実装できるよう、地域防災計画への反映や活用の定着まで伴走支援するなど、長期にわたって遂行できる点が同社の防災研究所の強みだ。
「防災はいくつものフェーズがあり、どこか一つだけを解決しても部分最適になってしまい、地域の防災力は上がりません。当社のICT技術やソリューションと、世の中の先端技術を組み合わせながら、新たな地域防災のモデルをつくりたいと考えています」(杉山氏)
-

株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー 社会インフラデザイン部 地域あんしん推進部門 あんしん共奏担当 担当課長 防災士 杉山 友理氏
少子高齢化や人手不足、地域コミュニティのあり方の変化など、さまざまな課題が自治体を取り巻く中、NTT東日本の100年にわたる防災・減災の知見は、新たな形となって地域住民の暮らしを守っていくだろう。
関連リンク
[PR]提供:NTT東日本