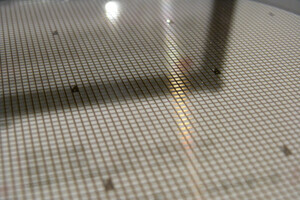「働き方改革」に取り組みながらも上手くいかないケースは多い。「新しいコンセプトがなかなか浸透しない」「ツールを導入したのに活用が進まない」「部門間の連携が取れないまま」こうした悩みを抱えてはいないだろうか。経営層として、あるいは担当者として、最も抑えておくべきポイントがある。Slack Japanの溝口宗太郎氏と、サーバーワークス代表取締役社長の大石良氏による、真の働き方改革に向けての対談をお届けする。
<企業紹介>
Slack Japan「ビジネスコラボレーションハブ」と銘打ったビジネス向けアプリケーション"Slack"を展開している。サービス開始から5年で、全世界での日間アクティブユーザー数は1,000万人を突破した。
サーバーワークス
日本で初めてアマゾン ウェブ サービス(AWS)の導入支援サポートを始めたクラウドインテグレーター。既存システムのクラウドシフトを通じたビジネスのデジタル化を推進している。
働き方改革とは「関係性」の改革
――はじめに、お二人の考える「働き方改革」について教えてください。
Slack Japan 溝口宗太郎氏(以下、溝口氏):
働き方改革とはあくまで「手段」であって、目的ではないと考えています。具体的に何か達成したいことがあって、そこに到達するための手段のひとつが働き方改革というわけです。Slackでは「個人のポテンシャルを最大限に引き出す」「組織としても足並み揃えて団結し、会社としてのパフォーマンスを最大化する」ことを目的に、Slack導入による働き方改革への貢献を進めています。
サーバーワークス 大石良氏(以下、大石氏):
私たちは「働き方改革」という言葉がまだない頃から、働き方をアップグレードするという思いのもと、さまざまな試行錯誤をしてきました。優秀な人材を採用したり、教育に力を入れたりするだけでは、組織が上手く成長しなかったのです。
あるとき、本当に改革しなければならないのは「関係性」だと気づきました。「会社が人を選ぶ」「常に上司の言うことを聞く」という関係ではなく、「上司にもストレートに意見を言える」「決まったあとは、みんなで同じ方向を向ける」関係こそが必要だったのです。
溝口氏:
働き方改革ではなく「関係性改革」というわけですね。私たちは、組織の団結を考える際、「アライメント」という言葉をよく使います。自動車のホイールアラインメントがわかりやすい例です。アライメントがきちんと整っていなければ、クルマはまっすぐ走りませんし、ハンドルに合わせて曲がることも、ブレーキを踏んだ分だけ止まることもありません。
組織もこれと同じで、大きくなればなるほど縦割りになり、事業部ごとにKPIが変わり、優秀な人が集まるにもかかわらず、組織同士が連携できなかったり、会社全体として能力を発揮できなくなる傾向にあります。こんな関係性の組織は、アライメントが取れていないというわけです。
大石氏:
私たちが関係性改革をしていく上で、大事にした原則が「オープンであること」でした。ものごとの経緯や情報をオープンにすればするほど、多くの力を結集することができるのです。例えば、距離が離れていてオフィスに通えなくても、プロジェクトにジョインすることが可能になります。Slackを知った時、これこそまさにオープンな企業文化のためのツールだと感じ、即座に導入を決めました。メールやビジネスチャットなどコミュニケーションツールはクローズドなものばかりですが、Slackにはオープンな関係性をつくる機能があったのです。
生産性向上という言葉にひそむ「あいまいさ」
――「働き方改革」という言葉が注目されるようになってから3年が経ちますが、実際の改革には苦労している組織が多数あります。こうした現状については、どのように思われますか。
大石氏:
一番のハードルは「成功体験」にあるように思います。小売業の現場では「売り場面積あたりの売上げを最大化すること」が正義です。製造業であれば「エラーの発生率を限りなく引き下げること」が正義です。しかし、こうしたロジックをオフィスにまで適応したらどうなるでしょうか。「仕事机は狭ければ狭いほどいい」「ミスをしないように今まで通りのやり方を続ければいい」という発想が生まれてしまいますよね。
つまり、「日本の会社は働き方改革がうまくいっていない」ではなく、「うまくいっている企業文化の負の側面があらわれている」のです。あらゆるものごとにメリットデメリットがあるにもかかわらず、一方のロジックばかりが使われてしまっていることこそが、真の問題だと思います。
溝口氏:
これまでの成功体験にない「働き方改革」をやるとなると、何をやればいいのかわからない。そういう混乱があるように感じますね。ともすれば働き方改革をやることそのものが目的となっているのではないでしょうか。例えば「従業員満足度を上げて、モチベーションをアップさせて、結果として会社の売上げを伸ばす」といったようなビジョンを持たずに、単に右へならえでテレワークを導入したり残業禁止にしただけでは、家に仕事を持ち帰ったりしていて、何も変わっていないこともあります。そもそも何が課題で、どう改善したいのか、働き方改革に取り組む前に、まず、そこを見つける必要があるのではないでしょうか。
大石氏:
ビジョンについてまったくの賛成です。還元すると、企業として掲げるべきものは「売上げを増やす」か「コストを減らす」のどちらかしかありません。
ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得する際に、憲法のような条文を書く必要があるのですが、私は第一条に「当社は売上げを増やすためにセキュリティを高める」といったことを書きました。「生産性を高める」なんて、とてもあいまいな言葉です。働き方改革によってコストを下げるのか、ニュービジネスを立ち上げて売上げをつくるのか、経営者はクリアにする必要があります。